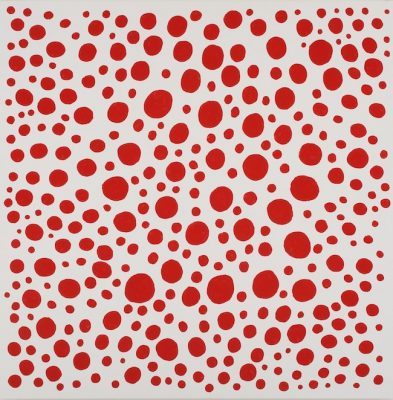ベス・オートンが昨年発表したアルバム『Weather Alive』は、彼女がその30年近いキャリアにおいて初めて自分でプロデュースした作品だった。レコーディングには、彼女の夫であり音楽家のサム・アミドンのほか、トム・スキナーやトム・ハーバートといった現在のジャズ・シーンを牽引する気鋭のミュージシャンが参加している。生楽器とエレクトロニクスが織りなす幽玄でアンビエントな音のレイヤー/テクスチャーが際立ち、瞑想を誘うように美しくも霊妙で実験的な感触をたたえたサウンドスケープ。その奥深い音の響きのなかで、オートンは過去の記憶、愛着と別れ、母性、憧れ、そして不確かな未来について思いを馳せている。「なぜ私は音楽を作るのか、なぜ音楽を作ることが好きなのかをあらためて感じることができた」。そう振り返るオートンの言葉をよそに、途中パンデミックによる影響で中断やスケジュールの変更に見舞われるなど、けっして平坦で順調なものではなかったというその制作過程。しかし、同時に『Weather Alive』はオートンにとって、アーティストとしての自身のアイデンティティを再発見し、それを新たなかたちで捉え直すような経験をもたらしたのではないだろうか、と想像する。
多くのメディアやリスナーの間で2022年を代表するレコードの一枚に選ばれるなど高い評価を受けた『Weather Alive』。年の瀬も迫った昨年12月の下旬、秋から続いたツアーを終えていち段落したオートンに話を聞く機会に恵まれた。
→ in English
――ニュー・アルバム『Weather Alive』を携えてのツアーはいかがでしたか。今回のサウンドをステージで表現する上で重視しているポイント、またこれまでと異なるアプローチがあれば教えてください。
ベス「良い調子です。乾いた世界の環境に囲まれながら湿った土の中で育てた小さな花を、その繊細さを壊さないようにステージにもっていって、それをリアルな世界の中で増幅させていってる感じ。それを繰り返して行く中で、ツアーがそれを祝福する場所になっていっている。今回のレコードを作ることは私にとって大きな成果だったし、ライブで披露することによって、それがもっと揺るぎないものになっていっている気がする。それは、私自身にとっても興味深いこと」
――『Weather Alive』は大きな称賛を集めていて、キャリアのベストに挙げる声も聞かれます。そうした評価や声をあなた自身はどう受け止めていますか。
ベス「ここまで高評価を得ることができたのは、私にも皆にとっても良いサプライズだった。アルバムがここまで受け入れてもらえているのは、本当に素晴らしいことだと思う。評価の内容もすごく詩的だし、アルバムに対する人々の感想も、私にとってはとても感動的。というのは、私自身がアルバムから感じることを、皆も感じてくれているのが伝わってくるから。今回のアルバムが私にもたらしてくれているもののおかげで、私はアーティストとしての自分を改めて取り戻すことが出来ていると思う」
――ご自身としても、今回のアルバムについてはこれまでの作品とは異なる手応えや思い入れが大きかったりするのでしょうか。
ベス「もちろん、すごく大きな存在。今回のアルバムは、他の人に聴かせることになるのかさえわからないまま作った作品。親が子供を育てるような感じで作っていて。親は、子供を愛しているから彼らを育てるでしょ? 自分が与えられるベストなものを彼らに与えたいし、彼らがベストになれることを願っている。そんな気持ちを持って作ったのがこの今回のアルバムです」
――それもあってか、今作はセルフ・プロデュース作ですよね。初めてのセルフ・プロデュースはいかがでしたか。
ベス「素晴らしかった」
――『Weather Alive』では、天候や自然、愛情、人間関係、記憶や時間の流れなど、私たちが目の当たりにしたり心の中に抱えていたりする様々な移ろいやすく不確かな感覚について歌われていて、その移ろいやすく不確かな感覚がサウンドでも繊細かつ鮮やかに表現されていると感じました。制作に際してはどんな姿勢で臨まれたのでしょうか。
ベス「今回はパンデミックの中での制作だったから、セルフ・プロデュースしか方法がなかった。それから、制作過程で私にとって大切だったのは、全ての曲で誠実さと完全性を保つこと。だからそのためには、やっぱりこのアルバムに参加してくれている素晴らしいミュージシャンたちの協力が必要だったし、彼らに参加してもらっても、自分で編集したりプロデュースすることで、曲のスピリットや雰囲気を維持することができたんです。それはすごく良かった。そして同時に、他のミュージシャンに入ってもらうことで、曲が持つ世界観を良い意味で広げることもできた。両方のやり方の長所をいかすことができたのはすごく良かったと思う」
――漠然とした質問になりますが、このアルバムを作ってみたことでわかったこと、驚かされたこと、あらためて気付かされたことなど、何かありましたら教えてください。
ベス「驚かされたことはたくさんありました。まず一つは、自分にあれだけの集中力があるなんて知らなかったし、全体を見渡す力があることもわかった。他の人には見えなくても、色々なことを経て、何が起こるかが私には読める時がある。今回のプロセスでは、色々な気づきがあって、毎回好奇心をそそられた。本当に色々なことを学んだんです。特に学んだのは、私のスタミナ(笑)。そして、自分が不安や心配事に打ち勝つ力を持っていることもそう。自分が作りたいものや誠実さがぶれなければ、私にはそれができるんだということがわかった」

ーー先ほど話されたように、今回のアルバムはさまざまなミュージシャンとのコラボレーションによって制作された作品でもあります。たとえばリズム・セクションを司ったトム・スキナーやトム・ハーバートに求めたこと、逆にかれらが今作にもたらしてくれたことは何でしたか。
ベス「トム・スキナーとは、もう16年の付き合い。2005年には一緒にツアーをしたりもしたし、彼とはずっとコラボしたいと思っていて。実は、今回の前に他のレコードでそれを試みたことがあったんだけど、あの時は、時期も作品もコラボにとって最適ではなかった。でも、今回はピアノがメインだったし、半透明な独特の雰囲気があったから、彼に参加してもらうなら今だ!と思って、彼にトラックを5つ送ったんです。ビートやループでなくていいから、彼には何かパーカッションを加えて欲しくて。私がそれをぶつ切りにして、その上からプレイできる何かを作って欲しかった。それを伝えたら、彼が素晴らしいパーカッションのパートを送ってくれて、私がそれを使って曲を作った。例えば“Unwritten”はその一つで、トムのパーカッションがトラックの基盤になった曲だと言えるかな。そして、その後、私が彼と私と3人でライブでレコーディングができるベースプレイヤーを探していたら、トム・スキナーがトム・ハーバートを紹介してくれた。その後3人で集まって、“Unwritten”をレコーディングしたんだけど、ハーバートのあのベースはワンテイクだったんです」
――へえ。
ベス「あれを聴いた時は、今までこんな美しいものは聴いたことがないってくらい美しいと思った。それくらい衝撃を受けたんです。で、その後またロックダウンがあって、それが開けてから数日間また一緒にレコーディングができるか彼らに尋ねたらOKがでて。だからまた3人で彼らがよく使ってるフィッシュ・ファクトリーっていうスタジオに入って、そのスタジオのエンジニアと一緒にレコーディングしました。その時に私は作っていた曲全てをプレイしたんだけど、最高でも一曲3テイクくらいまでしか録らなかった。本当に直感的で、サラッとしていて、素晴らしかった。みんなのおかげでベストなものをとらえることができたと思う。トム・スキナーが、よく“the first thought is the best thought”(=最初の思いつきが最高の思いつきだ)って言っているだけにね(笑)。トムたちだけじゃなく、今回参加してくれた皆に参加してもらうことになったのは、いい意味ですべて偶然だった。そして、皆と一緒に自然の流れで素晴らしいサウンドが出来上がった。最高で美しい偶然が重なって、アルバムの曲が出来上がっていったんです」
――そのトム・スキナーがメンバーを務めるサンズ・オブ・ケメットや、トム・ハーバートが一員のポーラー・ベア、そして今作でサックスを吹いているアラバスター・デプルームなど、現在のイギリスのジャズ・シーンを牽引するプレイヤーが参加しているのも本作のトピックのひとつです。最近、イギリスのジャズ・シーンはかなり盛り上がっていますよね。
ベス「本当にそう! 今年は特にクレイジーだったと思う。私は、自分自身がジャズ・シーンに属していないこともあって、あのシーンがあそこまで盛り上がっているなんて全然知らなかった(笑)」
――あなたから見て、今のイギリスのジャズ・シーンにはどんなところに刺激や面白さを感じますか。どんなインスピレーションをもらっていますか。
ベス「私にはわからない(笑)。トムたちにも、モダン・ジャズ・シーンのエナジーをもたらしてほしくて参加してもらったわけではないから(笑)。ジャズ・シーンにかかわらず、今のイギリスはあらゆるシーンからすごく刺激的なアーティストが出て来ていると思う。今は、イギリスの音楽にとってすごく重要な時期なんじゃないかな。それが何なのかを言葉で説明することは出来ないんだけど、彼らが放つエナジーにはすごく引き寄せられる。今回のレコードでも、皆がそれをもたらしてくれたと思う。それを聴いて、私自身すごく魅了されたし。皆に参加を依頼した時は、本当に直感的で、何をもたらしてくれるのかなんて意識してなかった(笑)。でも、結果本当に良い選択をしたなと自分でも嬉しく思っています」
――“Fractals”という楽曲もありますが、今回の『Weather Alive』にはそうしたミニマルな美しさや静けさが感じられて、心を静めたり瞑想を誘うような音のテクスチャー、音の響き(アンビエンス)が印象的です。個人的にはブライアン・イーノやファラオ・サンダーズの作品も連想したのですが、こうしたムードやニュアンスを捉えた作品になったのはどうしてでしょうか。
ベス「今、私は人生の中で瞑想的でゆっくり時間を過ごせる状態にいるんです。たくさん歩いて時間を過ごすのが好きだし、ピアノを弾いていると時間と時間の間に存在しているような気持ちになれる。今回のアルバムは、これまでに起こったことや過去へのリアクションではなく、瞑想的な空間に存在している今の私が作った作品。自分の人生の中に平和を求め、それを探している私の状態が表現されている。音楽を作っている時は本当に平和な時間を感じることができるし、私がなぜミュージシャンになったのかという本質を感じることができる。自分自身が誰なのかを知ることができるというか。それがサウンドに反映されているんだと思う」
――今作には、多彩な楽器の音色と共に、例えばあなたが咳を払う音やピアノスツールのきしむ音なども収められていて、そうした臨場感の演出は、この音楽が普段のあなたの日常や生活と地続きにあるような感覚を抱かせます。今作は、そうした今のあなたが立っている、目にしているラウンドスケープのサウンドトラックなのではないか、と感じたのですが、いかがでしょうか。
ベス「私は本当によく自然の中を歩くんです。今回のアルバムの曲を書いていた時は特にそうだった。何時間も何時間も歩いたな。ノーフォークからロンドンに引っ越してきた時も、森林の近くに住む場所を探して。田舎の出身だから私は自然が大好きだし、森の中に座っていると、本当にたくさんのものを吸収する。その環境は影響しているかもしれない。咳やピアノスツールのきしむ音に関しては、レコード制作の最後の方で、もうこれ以上は作れないと思った瞬間があって……身体的にも、精神的にも、もう無理!と思って、クレイグ・シルヴェイにミックスを任せた。そしたら、彼は咳の音もピアノスツールのきしむ音も、どんな音も一切消さなかったんです(笑)。髪の毛一本分さえ何も変えず、全ての音を残した。彼は、その全ての音をとても気に入ったらしくて。私が彼に渡した、“リアルさ”がすごく良いと思ったみたい。最初にミックスを聴いたときは、『ちょっと待って、あなたの仕事はサウンドをきれいに、クリアにすることじゃないの?』って思ったし、聴き難かった(笑)。でも、彼はむしろそういう音のボリュームを上げて、その存在感を強くした。彼は、それが美しいと思って、もっと強調したいと思ったらしい(笑)。子供が走り回る音も、犬の鳴き声も(笑)、そのリアルな日常感が魅力的だと感じたみたい」
――発声や呼吸の取り方も含めたヴォーカルのアプローチ、また、その録音やミックスに関して、これまでの作品と違って意識したことなどはありましたか。
ベス「その違いは、私ではなくてリスナーが感じることだと思う。自然と出来上がったものにすべてを合わせたんです。何か一つをもっと磨いてしまうと、その他すべてを磨かないといけなくなってしまう状態だったから。糸を一本引っ張り出したくて引っ張ってしまったら、そこに10本の糸が付いてきてしまうような感じだった。だから、何も触らないようにして。そこには奇妙なパズルが完成していて、そのピースを一つでも変えようとするとすべてが崩れ、組み立て直さないといけなかった。私は、それはしたくなかった。いつ手を加えるのをやめるかは、私が今回学んだことでもあった。ストップするのって、すごく大変なことなんです」
――今作は、ジャズやアンビエント、フォーク、クラシックなど様々な音楽がクロスオーヴァーしたサウンドだと言えますが、参加したミュージシャンのなかでシンサイザーを弾いているダスティン・オハロラン.の名前に目が留まりました。近年では映画音楽においても世界的な地位を確立しているコンポーザーですが、彼とはどのように出会ったのでしょうか。
ベス「ダスティンは、私の前回のレコードでプレイしてくれた。私の友人のルーシー・ブライトを通して知り合って、レコードに参加してくれないかと頼んだらOKしてくれて。私は彼の音楽が大好きだし、本当に美しいと思う。だから今回も彼にお願いすることにしたんです。彼が快くオファーを受けてくれたのは、すごく光栄だった」
――あなたと共同でエンジニアを務めたダニ・ベネット・スプラグは、今作の他にもブラック・ミディやアイドルズの最新作を手がけている若手の女性プロデューサーですが、彼女を起用した理由は?
ベス「彼女はクレイグのアシスタントだから」
――“Lonely”では、「falling」と「lonely」という言葉が響き合う瞬間が印象的で、「Will you be the ash of a well-tended fire/Will you be the ambush of my desire?」という問いかけも深い印象を残します。この曲へのアプローチについて教えてください。
ベス「ある意味、この曲はアルバムのサウンドの青写真と言える作品。他のどの曲もこれに続いて、この曲のような感情の深さを持つようになったから。この曲は、愛の探求の曲。けれども、愛を見つけるためには、孤独な時間が必要だということを歌っている。そして最終的に、孤独を受け入れる。深い愛、ずっと続く愛を知り、得るためには、孤独を知らなければいけない。そして、孤独を受け入れ容認しなければならない。パンデミックは全く関係なく、これはずっと私が感じてきたことです」
――“Friday Night ”は、あなたが10代の頃の親友について歌った曲だと聞きました。歌詞からは、痛みや悲しみに寄り添い、癒すこと、セルフケアについて描いた歌という印象を受けましたが、なぜ彼女について書こうと思ったのですか。
ベス「私が彼女について書いたわけではなくて。曲を書いて歌っている時に、彼女のことを考えるようになった。彼女に向けて歌っているような気持ちになったというか、そんな感じ。この曲もラブソングで、“Lonely”と同じように孤独についてでもあるし、回顧録でもあり、受け入れることについての曲。彼女との繋がりにインスパイアされて出来上がった曲だと思うし、彼女のことが思い出される。ちょっと複雑なんだけど、これがラブソングであることは確かかな」
――アルバム全体を通じた歌詞に関しては、主要となるインスピレーションは何だったと思いますか。
ベス「無意識だったと思う。私は、その無意識を掘り下げ続けたんです。無意識の中から言葉がまず出てきて、その、一見意味をなさない言葉の中に意味を見出そうとした。それを問うというよりは、その言葉との自分の関連性を見つけていき、それを歌詞として広げていった感じ。出てきたものを後から見て、その意味に気づき、発見していった。私の場合、無意識に出てくるものから意味を見出すのに時間がかかるんです」
――このアルバムの中でのあなたは、記憶の中の過去を訪れ、あるいは不確かな未来に思いを馳せ、喜びの時も幻滅させられる時もすべてを慈しむように佇まれている様子が印象的です。それは、この6年の間にあなたが過ごされてきた時間の濃密さをうかがわせるものでもありますが、今回のアルバムの制作はご自身にとってどんな経験だったと振り返ることができますか。
ベス「すごく深い経験でした。受け入れることに至るまでの瞑想、長い旅のような経験。そして、アーティストとしての原点を改めて見つめ直し、感じることができた。なぜ私は音楽を作るのか、なぜ音楽を作ることが好きなのかを改めて感じることができた経験だった。それは、私にとってすごく大きな意味がある。作品を作り始めた時、まだまだその意味を完全には理解できていなかったと思う。でも、ある時にこのアルバム制作のプロセスを振り返りながら、それが理解できるようになってきて。作っている間はずっと混乱もしていたし、手に負えなかった(笑)でも、それが形になっていくにつれ、自分にとってとても大切なものに進化していったんです」
――アルバム・タイトルの「Weather Alive」は曲名から取られたものですが、このフレーズをタイトルに選んだのはどうしてですか。
ベス「レーベルのティムが、『Weather Alive』にしたら?ってずっと言ってきたから(笑)。私は『本当にそれでいいと思う?』って確認したんだけど、『思う!』っていうから、じゃあそうしようかなと思ってそれにした(笑)。私って、名前を決めるのが本当に苦手だから(笑)」

text Junnosuke Amai(TW)

BETH ORTON(ベス・オートン)
『WEATHER ALIVE(ウェザー・アライヴ)』
Now On Sale
(ビッグ・ナッシング/ウルトラ・ヴァイヴ)
収録曲目:
1. Weather Alive
2. Friday Night
3. Fractals
4. Haunted Satellite
5. Forever Young
6. Lonely
7. Arms Around a Memory
8. Unwritten
Beth Orton
イギリスで最もユニークで魅力的なミュージシャンの一人。The Chemical Brothers、Andrew Weatherall、Red Snapper、William Orbitとの共演を通し、Ortonのサウンドは、フォークトロニカ/トリップ・ホップのパイオニアとして、約30年にわたり変貌をとげてきた。これまでに発表した6枚のアルバムの中で、Ortonはカテゴリー分けを断固として拒否。静寂に包まれたフォーク調のストーリーテリングから、暗く陰鬱で難解な実験主義までを織り交ぜた作品を発表している。このような様々な音の探求を通し、Ortonは幻想的なソングライターであり続け、スタジオの外では、Patti Smith、Nick Cave、Sinead O’Connor、Flaming Lips、Beckといったアーティストとステージやマイクを共にしている。ブリット・アワードを受賞し、マーキュリー・プライズに二度ノミネートされる等、Ortonはあらゆる賞賛を浴びながらも、次に進むために常にあまり人が通らない道を選び続け、予測不能な興味深いバック・カタログを作り上げている。
More info: http://bignothing.net/bethorton.html