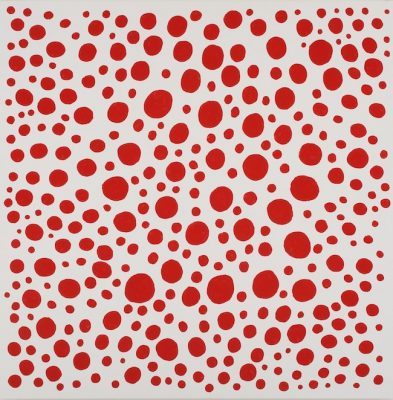ハードエッジで伸縮の効いたギター・ロック・サウンドと、無機質でつぶやくような歌い回しが特徴的なヴォーカル。そのコントラストやコンビネーションが持ち味のドライ・クリーニングは、世代こそ少し上だが、ブラック・ミディやスクイッドと並んで近年のイギリスを代表する新進気鋭のロック・バンドの一角に挙げられる。そんなかれらのニュー・アルバム『Stumpwork』は、音楽面の「探求」を推し進めつつ、ユーモアとシリアスな警句が散りばめられたユニークで刺激的な作品だ。ジェンダーとアンビエント、サイケデリックと生春巻き、エンポリオ・アルマーニとダンス・ビート、インプロヴィゼーションとペットの亀……その落差や緩急、ハーモニーが生み出すダイナミズムこそ、ドライ・クリーニングの真骨頂と言えるだろう。
「自分を取り巻く世界に興味を抱き続けよう/できれば子供の頃の好奇心を持ち続けよう」。アルバムの最後の曲“Icebergs”でそう語りかけるヴォーカリストのフローレンス・ショウ。待望の初来日公演を控えた前日、メンバー4人に話を聞いた。
――ドライ・クリーニングの曲は歌詞に食べ物がよく出てきますよね。パンケーキ、ソーセージ、ミックスサラダ、寿司、チョコレートムース、ポテトチップス……。
ニック「このバンドは食べ物を中心に回っているんだ(笑)」
フローレンス「インタヴューで聞かれるまで、そのことに気がつかなかった。みんなそのことを話題にするんだけど、私にとってはまったくの驚きで。歌詞の中に食べ物に言及することがこんなに多いなんて(笑)。食べ物のことはよく考えるよね。お腹が空くととても不機嫌になるし、毎日同じ時間に食事をとらないとストレスを感じる。食事を抜くと他のことを考えるのが難しくなる。体質みたいなもので、食べ物のことで頭がいっぱいなのかな(笑)。私は面白い食べ物が好き。イギリスで売られている『ビリー・ベア・ハム』という、熊の顔の形に潰されたハムがあって。素材は肉らしいんだけど(笑)、何でできているのかわからないような、そういうのが面白くて好きです」
ルイス「この取材に向かう途中も食べ物の話をしてたしね」
トム「僕らがバンドを始めた頃は、音楽を演奏するよりも食べ物の方が大事だった。このバンドは元々、社交的なものとして始まったんだ。よくたむろして、音楽を作って、食べ物を食べていたね」
――今回の新しいアーティスト写真の中にも、4人で食事をしている写真がありますね。食事中の会話から音楽のアイデアが生まれることもありますか。
ニック「音楽のことを忘れるには一番いい時間だと思う」
トム「食事には、共同体や儀式のような側面がある。そしてアイデアとは、無意識のうちに出てくるものなんだ。それはとても大事なことで、一緒にいて、なんとなく書いたりしているうちに頭の中でいろんなことが起こってくる。何かを書いたり、ジャムをしたりすると、それが頭の奥で浸透していき、別の何かが生まれたりする。だからそこで座って何を考えているかといえば、曲を書くことではなく、『このターキーサンドイッチはなかなかいいね』といったくらいのことなんだよ(笑)」
フローレンス「あのプレスショットは、“ドライ・クリーニングは食べ物が大好き”というテーマで撮られた写真みたいで面白いよね(笑)。ちょっとジョークみたいだけど、でも実際、食べることが好きなのは私たち自身だから」
――ただドライ・クリーニングの曲では、“食べる”描写はあまりないですよね。出てくる食材や料理は、美味しそうでもなければ、不味そうというわけでもない。即物的というか、静物画のような対象との距離感がドライ・クリーニングの音楽のクールな佇まいを象徴しているというか。
フローレンス「私は常に、他人が自分たちの音楽をどう捉えているのか知りたいと思っている。私自身、曲を書く際にそれがどのような役割を担っているのかについて自覚がないから。あくまで無意識のうちにやっていることなので、他人の意見を聞くのは楽しい。この前も誰かが言っていたんだけど、『食べ物のことを女性の声で話しているのが面白い』って。今までそう思ったことはなかったけど、でもここには明らかに、ある種の政治的な側面があるような気がする。よくはわからないんだけど……ただ私自身ほとんど意見を持っていないので、人々がこの作品をどう解釈して、そこから何を得るのかに興味がある」
――ちなみに、食べること、もしくは料理とのアナロジーでドライ・クリーニングの音楽を語ることってできたりしますか。
フローレンス「どうだろう? 私が料理をするときは、冷蔵庫にあるものを使って作るのが一番好き。レシピは嫌い。あれこれ指示されているような気がして(笑)」

――今回のニュー・アルバム『Stumpwork』は、デビュー作の『New Long Leg』に続いてジョン・パリッシュをプロデューサーに迎えて制作されています。ただ前作と比べて、スタジオでの「実験」に多くの時間が費やされたと聞きましたが。
ニック「面白いことに、僕たちはスタジオでの作業を表現するのに『実験』という言葉をよく使うんだ。ただ、言葉本来の意味での『実験(Experimenting)』とは違うと思う。僕たちがしたことは、どちらかというと、『探求(exploration)』に近いと思うんだ」
トム「かなり主観的な言葉だよね。誰かにとって実験的なことが、僕らにとっては必ずしも実験的であるとは限らない。今回、僕たちがサウンドでやった『実験』は、たとえば異なるコードを使ってオルガンやラップスティールやいろんな楽器を追加していくようなことだった。さまざまなエフェクトをかけたり、ペダルを変えたりしていろいろ試してみたんだ」
ニック「それは今回、(ロックダウンの影響で)時間的な余裕があったからこそ可能だった側面もある。そこにはある種の精神的な効果もあって、ロックフィールドにあるスタジオに行き、ジョンと一緒に仕事をするのは僕らにとってとても心地の良いことだったんだ。その根底には信頼という要素もあり、気心の知れたエンジニアやプロデューサーと一緒に仕事をできたのが大きかった。隔離された環境の中で、同じ部屋で過ごし、同じスタジオで作業し、同じものを食べるという。前回は2週間でアルバムを作らなければならなかったけど、今回は1カ月もかけることができた。その過程では困難なこともたくさんあったけど、でも一緒にいることで、その不安を頭の隅に追いやることができる。そうした恩恵が今回のアルバムでは大きかったと思う」
ルイス「メンタル的な部分だけでなくフィジカル的なことを言うと、今回は“遊び部屋”を用意したんだ。そこにはキーボード、パーカッション、サックスなどたくさんの楽器がいたるところにあり、ライヴを録音する一角とおもちゃ部屋みたいな部屋が混在しているような感じで。そこにいつでも好きな時に出入りして、遊んでいるような感覚で曲作りをすることができたんだ。あと天候の違いもあったと思う。最初のレコーディングの時は天気が良くて、外で卓球をしている時間が長かった。今回は少し寒くて雨が降っていたので、室内で過ごすことが多かったね」
――サウンド面で、今回のアルバムに持ち込みたかった新たなテイストや具体的なアイデア、表現したかったフィーリングみたいなものは何でしたか。
トム「今回は“スペース”が強調されていると思う。どうすればより多くのスペースを作ることができるのか、そこに関心があった。それと反対に、より短く、簡潔にわかりやすくすることも意識していた。だから、短くてシングル向きのものと、長めで広がりのあるものがある。その両極端の要素を押し出し、ドライ・クリーニングの世界をもう少しダイナミックなものにしようという狙いがあったね」
フローレンス「考えてみると、私たちがしている『実験』とは、リコーダーを使ったり、誰かにホーンを吹いてもらったりとか、とてもささやかなものだった。これが違うバンドだったら、16人にホルンを吹いてもらうみたいな感じだったかも。でも、そこはバンドの気質とも関係があると思う。私たちはマキシマリストではないから、きわめて思慮深く、ちょっとした付け加えをしたんだ」
――その「実験」ないし「探究」という部分において、今回のアルバムの中で最も手応えを感じた曲を挙げるとするなら何ですか。
フローレンス「たくさんあるけど、“Conservative Hell”とか?」
トム「いい例だね。あれは逆に、制作時間が足りなかったこその産物でもあって。最初にレコーディングした曲はかなりうまくいったので、ジョンが『2曲目をやろう』って言ったんだ。ジョンはニックに気持ち強めにバスドラムを叩くように指示して、ルイスと僕にはランチの前に何かやっておくようにと言った。そうしたシチュエーションはよくあることで、僕らはそこでいろんなことをやっていたんだ。ペダルを踏んだり、何かを試したりしていただけなんだけど、実は頭の中ではランチのことを考えていたんだ(笑)。だから僕らがリハーサルルームを出た時に、周りの人たちがそれをいいって思ったのは驚きだった。人は時に、物事をすぐに判断してしまい、その結果、興味を失ってしまうことがある。判断が鈍ると、逆に面白いものができるのかもしれないね」
フローレンス「実際にしなかったけれども、やろうとしたことのひとつに、児童合唱団を入れるというアイデアがあって。次のアルバムでは子供たちの合唱が聴けるかも(笑)」
――その“Conservative Hell”は、冒頭の「Good Wedding/Bad Wedding」という歌詞が印象的で、以前にメーガン妃を題材にして書かれた “Magic of Meghan”という曲を連想しました。“Conservative Hell”は前作に収録された“Unsmart Lady”同様に、社会に置かれた女性の立場や、女性に対する固定的な役割分担の意識について歌った曲でもあると思いますが、この曲が書かれた背景について教えてください。
フローレンス「前々からこういう歌詞が書きたくてノートにメモしていて。正直なところ、それはイギリスで起きた“何か恐ろしいこと”がきっかけになっているんだと思う。というのも、イギリスではもう10年以上、保守政権が続いている。かれらは毎週のように新しい酷いことをやっていて、それが頭にあった。この “保守的な地獄”について書きたいと思ったんです。本当はもっと気の利いたことを書きたいとも考えていたんだけど、結局例の書き溜めたノートに戻ってきて――タブロイド紙の見出しのような感じでアレだけど。それとイギリスだけではなく、今や世界中が“保守的な地獄”に陥っている状況について考えていた。ちょうどフランスの選挙でマリーヌ・ルペンが当選しそうになった頃で、それで思いついたんです。世界的に右傾化が進む状況について、ヨーロッパをはじめ世界中で右翼的な政権がどんどん誕生していることを訴えるようなものが書きたかった」
――ええ。
フローレンス「でも同時に、人生とはそれでも続いていくもの。結局のところ、私たちの日常は変わらない。恐ろしい政治的状況の中で、買い物をしたり、人の結婚式に出たりしなければいけない。そこに選択の余地はない。それであの曲では警察権力に触れ、『If you think this car’s dirty you should try a night with the driver(この車が汚いと思うなら、あの運転手と一晩一緒に過ごしてみなよ)』と書いたんです。そのフレーズはロックフィールドで料理人をしている人の車に貼ってあったバンパーステッカーを見て思いついたもの。私はこの国の責任者にショックを受けている。政府の中の人たちはいわばドライバーであり、責任者。かれらは本当にタチが悪い……そんなことを考えるうちに、バンパーステッカーのイメージと結びついて。そうやっていろいろ集めて一つにして曲ができた」

――今フローレンスが話してくれたような話題や問題意識について、メンバー内で話すような機会はありますか。食事の時は音楽のことは考えないということでしたが。
フローレンス「どうしてもそうなってしまうよね。今、国内では多くの新しい、そして恐ろしい動きがある。特に、ボートで海峡を渡ってくる人々については、まさにそうした状況の一つと言える。まるで絶え間なく繰り広げられる災害のようなもので。ケント州にあるマンストンという収容施設で起きた事件も本当にひどいものだった」
トム「誰かがそこに車で乗り付けて、ガソリン爆弾を投げつけて自殺したんだ。メディアと政府が反移民的な行動を許しているために、人々が移民を攻撃しているという現象が起きている。彼らは『亡命者』ではなく『移民』という言葉を使っていて、これは法的なトリックに過ぎないんだ。民主主義のために亡命を申請することは許されているけど、それを申請するために海峡を渡ってイギリスに行く合法的な方法はないんだよ」
フローレンス「英国の多くの人々は、海峡を渡って亡命を申請することは違法だと信じ込まされている。でも、そんなことはなくて、完全に合法的な行為。話がすっかり歪曲されてしまっている」
トム「それと、ウクライナや香港から助けを求めてくる人々もいて、亡命希望者の数が増えているという状況がある。けれど一方で、シリアの人々には同じことをしようとしない。シリアで起きたのと同じことがウクライナでも起きているのに、この2つの紛争に対する対応はまったく異なる。この国では実に不快なことが起こっているんだ。メディアの情報を鵜呑みにしていると、本当にひどいことになるよ」
フローレンス「とてもあからさまで、無視したいと思ってもできない。日々、制御不能な大きな出来事が起きている。そう、だから話さないわけにはいかない」
――そうした話を受けて聴くと“Liberty Log”も印象的です。「巨大な腐ったサッカーボール」「中華春巻を食べてジワジワと死ぬ危険を冒そう」という歌詞とか、時節柄どこか意味深に感じられて。
フローレンス「“Liberty Logs”の歌詞は『春巻き』が由来。ロックダウン中はレストランに行けないまま、9週目に入っていた。すでに頭がおかしくなっていたんだけど、新たなレベルの狂気に陥っていて。『生春巻きが食べたいなあ』と思いながら(笑)。当時はワクチン接種前の時代で、COVID‑19で亡くなる人が続出し、誰もその仕組みやリスクを理解していなかった。テイクアウトは安全かどうかという議論が盛んに行われ、BBCのニュースやウェブサイトでも取り上げられていた。テイクアウトは可能か不可能か、『商品が届いたら箱を掃除する必要があるかどうか』とか、延々と続く感じ。私自身、テイクアウトができるのかできないのか長い時間考え、怖さはあったけど、とにかく危険を冒してでもテイクアウトしたいって思ったのを覚えてる。生春巻きを食べたい気持ちがCOVID‑19に感染する恐怖を上回った(大笑い)」
――なるほど(笑)。
ニック「2年前の冬に鉄道のアーチの下でリハーサルしたときの録音が携帯電話に入っていて。ヴィクトリア時代に鉄道が建設された時の高架で、そのアーチの下のスペースがロンドンのあちらこちらで再利用されていてね。で、友人のひとりがそこを所有していて、パンデミックの時にそこでリハーサルをした。上を通る電車がうるさくて、凍えるほど寒かったけど、曲作りの期間中にちょくちょく出入りしていたんだ。トムが4トラックで素晴らしいギターループを作ってくれて、そこにいろんな音をフェードインさせて背景のレイヤーや全体の雰囲気を構築していった。その素材を“Liberty Log”のレコーディングでは使っている。元々はジャムのようなもので、3つのセクションに分かれていて長さも決まっていなかったので不確定な要素が多く、レコーディングにはかなり不安があった。でも、この曲はいろんな意味で即興的で、ワンテイクで作ったので、それが形となりレコードで聴けてとても嬉しいよ。リハーサルの時間があまりなかったのでまだライヴで演奏したことがなく、今回のツアーには間に合わなかったんだけど、来年のツアーではやれたらいいなと思っている。みんな大好きな曲だし、僕も大好きな曲のひとつなんだ」

photography Marisa Suda(https://www.instagram.com/marisatakesokphotos/)
text Junnosuke Amai(TW)

Stumpwork by Dry Cleaning Album Cover 2022
Photography: Annie Collinge
Creative Direction: Rottingdean Bazaar
Dry Cleaning
『Stumpwork』
(4AD / Beat Records)
Now on sale
国内盤CD
(解説・歌詞対訳付/ボーナス・トラック追加収録/先着特典タオル)¥2,200+税
BEATINK.COM:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=12859
TRACKLISTING
01.Anna Calls From The Arctic
02.Kwenchy Kups
03.Gary Ashby
04.Driver’s Story
05.Hot Penny Day
06.Stumpwork
07.No Decent Shoes For Rain
08.Don’t Press Me
09.Conservative Hell
10.Liberty Log
11.Icebergs
12.Sombre Two *Bonus Track for Japan
13.Swampy *Bonus Track for Japan