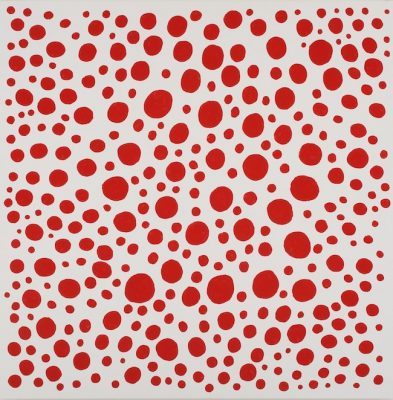世界の映画祭から注目を集めた新鋭・空音央監督の長編劇映画デビュー作『HAPPYEND』が10月4日公開される。物語の舞台は決して遠くはないXX年後の未来であり、我々の生活と地続きなリアリティのある世界。高校卒業を控えた大親友の2人が、自分自身と向き合うことで生じた関係性の変化をエモーショナルに描いた青春映画となっている。主役のユウタとコウを務めたのは、ともに俳優デビューとなる栗原颯人と日高由起刀。監督の人柄や役を演じての気づきなど、作品を通して得た学びを伺った。
役だったのか、自分だったのか、感情が入り混じっていた
──栗原さん、日高さんともに今回オーディションで主演に抜擢されました。オーディション時のエピソードから伺いたいです。
栗原颯人「ユウタとコウの台本を事前にいただき、それを演じるオーディションでした。演技をした後に監督と、演じたキャラクターについてどう思ったかを話す、という形で進めていました」
日高由起刀「演技のことよりも、監督は役者たちと話す時間を大切にされている印象でした。監督と何人かのスタッフの方たちには、育ってきた環境、バックグラウンドなど、いろいろ自分について聞いていただきました」
──それぞれの役について、どのような役だと理解しましたか。ご自身と共通点などありましたか?
栗原颯人「ユウタはすごい僕に似ていました。それは母子家庭という環境の部分だったり、音楽が好きで、いつも明るくて、楽しいことだけやっていたいという性格の部分も。僕のことを知っているんじゃないかと思いました」
──渡辺真起子さんがお母さん役でしたね。
栗原颯人「真起子さんは本当にすごかったです。台本には僕が実際に母親と体験した思い出に近いものが描かれていました。だから余計に、真起子さんを見ながら本当に自分の母親を見ている感覚になりました。自分も演じていて、今ユウタとしてそう思ったのか、栗原颯人として思ったのか、感情が入り混じっていたと思います」

勉強しておいてではなく、一緒に勉強していこう
──日高さんはいかがでしたか?
日高由起刀「コウは在日コリアンの役です。実は自分も祖母が台湾と韓国にルーツがある人なので、自分自身のルーツも考えながら、本作の撮影に向けて勉強していきました」
──これまでご自身のアイデンティティと社会に対する違和感を感じる瞬間はあったのでしょうか。
日高由起刀「祖母は僕が生まれる前に亡くなっていることもあり、祖母のルーツを知ったのは数年前でした。自分自身のルーツに向き合う経験もこれまでなかったですし、それこそ歴史などもあまり知らずに生活していました。そんな中、今回監督は『勉強しておいて』ということではなく『一緒に勉強していこう』という形で話をしてくださって。たとえば関東大震災後の朝鮮人虐殺の事実だったり、それらを取り上げたドキュメンタリーなどを見せていただきました。僕とフミ役の祷キララさんは特に、役を演じる上で知っておく方がいいねということで、監督とともに学ばせていただきました」

音央さんの頭の中にいる人物を2人に分けているイメージ
──本作はいろんな国にルーツのある俳優がたくさん起用されています。SNSでは排外主義的な意見を見かけてしまう社会において、高校生たちが楽しそうに交友関係を築いている様子に希望を感じました。
栗原颯人「身近にバイレイシャルの友達もいるので、僕自身としてもそれは普通のことだと思っています」
日高由起刀「僕もです。高校の交換留学で海外の友達もたくさんできましたし、今は日本でも外国人や海外にルーツを持つ人と友人になる機会も多いので。ただ、差別に対して具体的に抵抗するような行動をとってきたことはこれまでありませんでした。そのため、映画に描かれるような差別の事実については撮影を通して改めて考えさせられました」
──空音央監督はどんな方でしたか?
栗原颯人「すごく優しくて温かい方でした。パーソナルな部分にも優しく触れてくれるというか、いろんな方に対して理解がある。僕はそこまで分かったようなことを言えないですけど、いろんな人の内面に優しく寄り添ってくれる方だと思いました。さきほど話した渡辺真起子さんとのシーンでは、実はカットがかかった瞬間に泣いてしまったんです。実際の記憶がフラッシュバックしてしまって。そのあと、音央さんが『ごめんね』という感じで優しく抱きしめてくれて。そういう包みこんでくれる優しさを感じました」
日高由起刀「悩みなどいろんな気持ちを共有してくれる方でした。特に僕が一番印象的だったのはワークショップ。ハグの仕方について考え実践する内容でした。体と心とが密着するハグとはどういうものなのか、挨拶で相手がこういうハグをしてきたらどう思うか、自分の気持ちを相手に伝えるとはどういうことか。気持ちの共有について学びました。こんなにオープンな人に出会ったことがなかったので、そこがすごく印象的でした」
栗原颯人「僕はペアで行ったパーソナルスペースのワークショップが印象に残っています。とりあえず自分がウッと不快に感じるところまで近づいてみる。肩が触れるぐらいまでいったら、今度は顔を近づけて、頬をくっつけて……。本当に斬新でした」
──監督からそれぞれの役柄について何かアドバイスはありましたか?
日高由起刀「ユウタとコウは監督自身だとおっしゃっていました。遊ぶときはユウタで、考えるときはコウ。音央さんの頭の中にいる人物を僕ら2人に分けているイメージだそうです。だから自分の中の葛藤なども描いているんだなと思いました」
栗原颯人「だからこそ、監督を理解しようと努めました」


お互いリスペクトがあれば、意見が食い違っても戻ってこれる
──2人はいつから仲良くなったのでしょう?
日高由起刀「それこそ作品を制作するに当たって、主要キャストの5人の仲が深まるということはとても重要なことでした。それも『ただ仲良くなっておいて』ではなく、そのための機会をちゃんと設けていただいていて。僕らがどういう風にしたら仲良くなるか、本当に細かく環境づくりを考えてくれていました。撮影現場に入る日にはもうすごい仲良くなってる状態でした。それはスタッフの方々も同様です。全員が全員ちゃんと話したことがあるし、一人ひとりがしっかりと印象に残っている現場でした」
──そんな2人に、物語の中で亀裂が入ります。人間関係を再構築するのは難しかったのでは?
日高由起刀「内容的にお互いすれ違うけど、それぞれ成長はしている段階なんですよね。特に高校生の役ということもあり、お互いプライドがあったりして、なかなか相手を認められない部分がある。それでも終盤になるにつれて徐々に変化が起こります。相手の小さな変化に気づいていく、それを認めていくということが大事なんだと思いました」
栗原颯人「そうですね。長年仲が良かったという関係性でスタートしていることもあり、お互いリスペクトがあれば、意見が食い違っても戻ってこれるんじゃないかなと感じました」

どどんなに小さいことでも何かを訴えるという行為は世の中を変える
──決して遠くないXX年後の未来だという設定が効いた作品でした。作品には社会秩序への不満や憤りが描かれていますが、正直、描かれている差別的な空気、権力の暴走などはすでに現代の日本と通ずる部分があると思います。国家レベルのあやしい政策なども描かれる一方で、ユウタとコウが通う高校ではAI監視システムが導入。学校という身近なところでも安全のため、防犯のためという口ぶりで、人権を無視するようなシステムが忍び寄ってくる恐怖を感じました。
栗原颯人「怖いですよね」
日高由起刀「未来的だなとも感じましたけど、よく考えてみたら今の世の中が示す現実と変わっていないというか、本当に表現の違いなだけであって、みんなが常に誰かに監視されている現実は同じだと思うんです。それを映像で表していくことによって、作品を観た人たちが何か気づくものがあるのかなと思います」
栗原颯人「生徒を監視するシステムが出てきますが、それが減点法での評価しかされないという点も今っぽいなと思いました。粗探しをするネガティブな社会に直結すると感じます」
──コウの「デモって本当に社会を変えられるんですか?」という疑問をときほぐしてくれる作品であったところもよかったです。
日高由起刀「あのセリフは高校生の幼さゆえの疑問であり、信頼できる相手に向けて発する言葉でした。でも、どんなに小さいことでも何かを訴えるという行為は絶対、世の中を変えると思っています。僕の周りの親しい友達でも、納得がいかない現実や社会に向けて抗議してる人はいるし、海外で育った友達はうちの国はデモがすごく多かったよという風に話をしてくれます」
栗原颯人「現代社会だと他者からの見られ方を意識しなければいけないとも言われますが、僕も由起刀と同じで、どんなに小さなことであってもその人にとっては切実なことであり、声を上げることは大切だと思います。本作はいろんな意見を持つ人がぶつかることもあるけど、ちゃんとそこに対話が生まれているんですよね。そういうことも大事なんだろうなと思います」

──本当にお2人はいい監督といい現場に出会えてたんだということが伝わってきました。この現場で何を得られましたか?
栗原颯人「初演技ということもあり、お芝居のことについてもっと勉強したいと思えた現場でした。感情の動かし方など学ぶことは多かったです。ただ、作品を観終わったあとは、この映画が伝えたい社会のあり方に対する疑問などを自分も考えていかなくてはいけないと再確認させられたし、俳優として政治についても知っておかなければいけないという気づきを得られたことも大きかったです」
日高由起刀「演技面では、音央さんのワークショップで学ぶことも多く、自分がどういう風に演じたらこの映画は良くなるのかということも考えることができました。みんなと相談し合うことで、成長できた現場だったと思います。そして本作が描く各々のアイデンティティの違いについても考えることができました。周りの人間とのすれ違いには、何かしら自分の選択が関わっている。どれを選んでもうまくいかないこともありますが、その一つひとつを大切にしなくてはいけないという学びも今後の人生に生かしたいです」
photography Satomi Yamauchi(https://www.instagram.com/satomi_yamauchi/)
text Daisuke Watanuki(https://www.instagram.com/watanukinow/)
『HAPPYEND』
10月4日(金)、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開
https://www.bitters.co.jp/HAPPYEND/
監督・脚本:空音央
栗原颯人 日高由起刀
林裕太 シナ・ペン ARAZI 祷キララ
中島歩 矢作マサル PUSHIM 渡辺真起子/佐野史郎
撮影:ビル・キルスタイン 美術:安宅紀史
プロデューサー:アルバート・トーレン、増渕愛子、エリック・ニアリ、アレックス・ロー、アンソニー・チェン
製作・制作: ZAKKUBALAN、シネリック・クリエイティブ、Cinema Inutile
配給:ビターズ・エンド
日本・アメリカ/2024/カラー/DCP/113分/5.1ch/1.85:1
© 2024 Music Research Club LLC