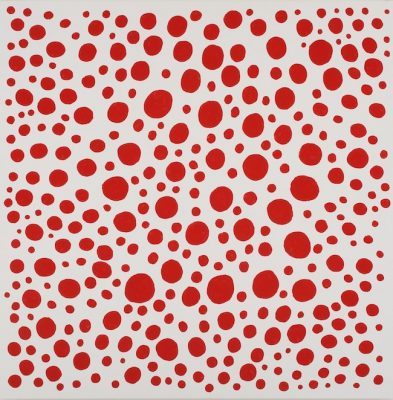石原海による長編映画『重力の光 -祈りの記録編』が、6月5日に開催されるイベント「SAVAGE GALS」にて1日だけの限定上映(https://www.contacttokyo.com/schedule/savage-gals/)。資生堂ギャラリー『第15回 shiseido art egg』で発表された『重力の光』(2021年/30分)、そしてそれを長編映画化した『重力の光 -祈りの記録編』は、元生活困窮者の人々、極道としての過去や虐待の記憶を持つ人、生きる意味に悩む人、北九州で30年以上困窮支援を行うNPO法人抱樸で働く人、東八幡キリスト教会で働く人など9名が出演。東八幡キリスト教会に集うそれらの人々が、イエス・キリストや十二使徒、大天使などに扮した新約聖書の演劇と、その練習風景や日常、インタビューなどを交差させた挑戦的な映画となっている。映像作家・石原海に本作の制作に向かうきっかけや人々との交流、作品をつくる姿勢についてなどを聞いた。。
『重力の光』:https://motion-gallery.net/projects/jyuuryoku_hikari
東八幡キリスト教会:https://higashiyahata.info
認定NPO法人 抱撲: https://www.houboku.net
――元々困窮者支援やそのドキュメンタリーを撮りたいという気持ちがあった上で東八幡キリスト教会に行くことになったのでしょうか。それとも教会でみなさんと出会ってから撮りたいと思うようになった?
石原「教会に行くことになったのはたまたまです。5年前に友人に連れられて行ったのが最初ですが、その時はNPO法人抱撲のことも活動も知らなくて、行ってから衝撃を受けました。中でもずっと記憶に残っていたのが、抱撲の人や教会の人たちみんなでお花見をしてる時に、『やっぱ愛だよね』って一番大きな声で叫べた人が勝ちという大声大会のこと。ああ、いつかまたここに戻ってきてこの人たちの映画を撮りたいなと思っていました。
その時に奥田伴子と奥田知志(NPO法人抱撲理事長/東八幡キリスト教会牧師)に『北九州に住んじゃえば?』って言われたんですが、当時教会の上で書いてた助成金の申請が通ったので、イギリスで2年半映像を学ぶことになって。日本に戻ってきても最初はまだイギリスに戻ろうと思っていたので、家を借りることもなく友達の家を転々としてたんです。でも『北九州に住んじゃえば?』って言われてたことがずっと残ってて、その言葉を真に受けて本当に北九州に住みはじめて。そこから東八幡キリスト教会や抱撲の活動を撮り始めました」
――北九州での様々な出来事や言葉が海さんの中に深く残ったのはなぜだったんでしょう?
石原「傷ついてる人や大変な育ちをしていた人たち、人生でいろんなしんどいことがあった人たちが傷を隠さず過ごしてるから。普通は悲しいことやしんどいことがあっても人には言わないじゃないですか。それをみんながオープンに、傷ついてることに対して傷ついてる、しんどいことにしんどいって安心して言えるコミュニティのようなものとして教会や抱撲が機能しているんです。アタシもめちゃめちゃ傷ついてたり悲しいことがあって、今もそれを引きずってるんだけど、人に悲しいと伝えていいんだと初めて知りました。
この間、すごく嬉しいことがあって。小倉昭和館で『重力の光』を上映した時に、私が短いスカートを履いてたんです。そしたらお客さんが200人くらいいる中で、伴子が『海ちゃん、パンツ見えそうだから足!』って言ったんですよ。その時に『恥ずかしいな、うざいな』って思ったんです(笑)。なかなか他人に対してウザいなって思わないじゃないですか。その自分の感情というか、ああアタシたちはそういう距離感になってきているんだ、伴子の前では子どもになれてるんだなって実感しました」

――そうしたパーソナル面での変化もあったんですね。
石原「はい。北九州では作品に対する姿勢も変わっていきました。今まで作品をつくる時は100年先まで残したいと思ってたんですけど、北九州に行ってみんなと出会ってから、そういうのはどうでもよくなった。自分の作品を残すことより、目の前の人との関わりの方が大切だと思うようになったんです。アタシは意外と完璧主義で、綺麗に撮りたいという気持ちも強かったのが、北九州での撮影は綺麗さよりも目の前の人との関係性を撮ることの方を大切にしたいという撮り方になったんですよね。もっと自我が強かったのが、目の前にいる人との関係性、そして自分がそこで生きてることの方が大切だと思うようになった。作品をつくって遠くに投げることもできるかもしれないけど、今は目の前のことをやるんだと思うようになった。
特に今回撮らせてもらってる人たちは普段は表に出ないような人たちもいます。その人たちを撮らせてもらってる時に、ドキュメンタリーであれドラマであれ、映像を撮らせてもらうということはすごく暴力的だと実感しました。映像を撮ることは、相手を傷つける可能性があり、相手の人生を背負うということだなと改めて思った。その暴力性を自覚してでも撮らなきゃいけないものが絶対にあるからアタシは作品をつくってるんですけど、相手を傷つけないということはないと思っています。だから自分の後ろにいろんな人の人生が乗っかってるという重い気持ちになるし、アタシはそれを一生抱えて生きる。今はよくても、その人が10年後に嫌だと思うかもしれないし、20年後に嫌だと思うかもしれない。もし嫌だという人が現れてしまった時に、心の底からなぜこれを撮らなくてはいけなかったか、撮らせてもらったことでどうなかったということを全部説明できるくらい愛してる人たちのことを撮ろうとより一層思うようになりました。それが目の前にいる人たちとの関係性を大切にするという作品づくりへの姿勢にも繋がっていると思います」
――確かに今作では半生を語ってもらうという部分でもその暴力性は増すと思います。9人の出演者たちとは映像を撮る前から信頼関係が築けていた?
石原「撮る前から仲良かった人もいれば、映像きっかけで仲良くなった人もいて。ユダ役の森さんは、信仰告白という、なぜ自分がクリスチャンになろうと思ったかを礼拝で話しているのを聞き、出演してほしいなと思ってそこから仲良くなりました」
――作品中でみなさんが半生をしっかりと語られていることにも驚きました。そうした自分を語るという経験を教会や抱撲での活動で獲得しているんでしょうか。
石原「自分を語ることに慣れているわけではないと思いますが、信仰告白を経てクリスチャンになっているから、自分の中で半生への理解が高まっている人たちが集まっている感じはしました。
本当に悲しみの最中にいる人は自分が悲しいとわかってないと思うんです。わけがわかってないというか。その渦みたいなものから離れて自分を見つめた時に、あの時はああいう状態だったんだとようやくわかってくる。ある意味では、今回の人たちはその最中から抜け出して、俯瞰して自分の身に起きたことについて考えることができる人たちなんだと思います。人間だからもちろん未だにめちゃくちゃになることもあると思うけど」

――個人的に福祉を学んでいるのですが、本当に最中の人は、なかなか助けてと言えないですよね。日本は特に言えるような教育も環境もないことが多いと感じます。自分が今大変な状況だと開示することが難しい。
石原「助けてっていうの、大変ですよね。そう言われても、相手が絶対に迷惑がるだろうと思っちゃう」
――抱撲の活動ではまさに福祉で必要とされるリカバリーやストレングスモデルといったものが実践されていて凄いと思いました。教会でも、人は生まれながらにして罪人であるという視点から違いを当たり前として受け入れている。
石原「自分自身でいうと、キリスト教思想と出会う以前から自分が罪人であるという気持ちがあったんです。人のことを傷つけながら生きているという気がしていたし、実際そうだったから、ずっと自分は罪人だと思いながら生きてきて。北九州で教会に通うようになって、私と同じことをイエスが言っていたことを知りました。自分の話をしてるって思ったんですよね。それで自分がキリスト教の思想にハマっていったこともあって、今作のテーマをキリスト教にしようと思いました。元々大好きなシモーヌ・ヴェイユという哲学者が、『重力と恩寵』という作品の中でキリスト教は奴隷の宗教だと言ってるんです。ヴェイユは工場で働いていて、身体も精神も病んでボロボロになってポルトガルに療養に行ったら、そこで漁師の妻たちがとても悲しい歌声で賛美歌を歌っていた。それを聴いた時にキリスト教は奴隷の宗教だと確信して、ヴェイユ自身も自分も奴隷の一人であると思ったと書いていて。キリスト教は傷ついた人のための宗教であると。幸せな人はイエス・キリストを必要としないんじゃないかと思うんですよね。なんらかの痛みを抱えた人が、キリストがいないと1週間生きていけないようなところがあるのかなって」
―― 一方でキリスト教は、解釈の違いという部分もありますが、家父長制を拡大させていたり、堕胎を認めないなどの問題も多く内包しています。
石原「そうなんですよね。本当にたくさん問題はあると思います。フーコーなどいろんなヨーロッパの知識人たちが軒並み反キリスト教で、私もキリスト教に問題がないとはまったく思えないけど、アタシが言うところのキリスト教というのは東八幡キリスト教会でのキリスト教思想。だからもちろん同性愛も肯定的なものとして捉えているし、戦争にも反対してる。クリスチャンになるために洗礼も受けたいんですけど、組織としてのキリスト教には自分の意見と全く真逆の教会もあるから、組織の枠内に入るのはまだ少し難しいなと感じています」

――なるほど。抱撲の話に戻りますが、支援するシステムや組織を知らない人も多い中、抱撲はどのように周知をさせているんでしょうか。
石原「街でパトロールして、道端に寝てる人にお弁当を配り、こんなことをやってますって一人一人に声をかけてるんですよ。毎週金曜日に夜の小倉の街を歩いて、それを34年も続けてきていて。行き場がない人たちは街にいるしかないから、そういうところで人から人に伝わって知られていってるのかなと思います。長く活動をしているので地域の人たちからの認知度もありますし、抱樸の活動を介して家に住めるようになった人は3700人以上もいます。草の根の活動ですね」
――そのパトロールのシーンもありましたね。そうしたいろんなシーンの中から、最終的に今回の選択に至った基準は?
石原「今回出てくれた人たちの人生に集中したいというのが一番の基準でした。例えば選ばなかったもので、炊き出しの後で街の人たちに声をかける時に、天使役の下別府さんが車の中で死んでるホームレスの方を見つけるという出来事がありました。実際に死人を見ているし、自分もかつてホームレスだったわけだから、みんな動揺していて。それを入れることでインパクトは出るかもしれないけど、それは抱撲としての出来事であって、彼らの人生ではないという判断で入れませんでした。ドラマティックなことを強調するのではなく、あくまで撮影させてもらった人たちの人生を記録することが大切でした。言葉が難しいんですが、人を感動させたり、いいものを撮ってる、いいことをしてる人たちを撮ってるという風には見せたくなかった。だから復活劇とのミックスもしていて。そもそもは抱撲としてのホームレス支援などの活動を撮っていたんですけど、いいことをしてる人や大変な人たちを普通にドキュメントするだけだったら私がやらなくてもいい。ドキュメンタリーとは離れた形を模索している中で、東八幡キリスト教会に通うようになってから、じゃあここにいる人たちと演劇をしよう、という設定を考えました。
重要だったのは、あくまでも自分が出会って、人生が変わった場所にいる人たちの、世には出されていない人生を記録するということ。そこがたまたま教会で、知志がいるから、ホームレス支援や困窮者支援、困窮状態になっている人たちが付随してきた。もちろん福祉への関心もあるし、目の前の人をどうやって助けることができるだろうとか、助けるまでにどうやって一緒に生きていけるのだろうというのは考えていて、その中で作品づくりでは限界があるとも感じています。でも私は作品をつくるしかない。自分がやるべき仕事は作品をつくることだというのも、北九州でいろんな状態にいる人たちと出会って思ったこと。人生で何かに取り組む時にそこに集中することは大切だから、全部の作品づくりをやめる覚悟がないと抱撲で働きますなんてこともできない。だからアタシは作家として作品をつくっていくということしかできないんだという絶望もありました」

――その作家としての向き合い方然り、冒頭の説明からの長回しや、モノクロとカラーの使い方、音の入れ方も含めて、どうやって観衆に作品を見続けさせるかというテクニック的な部分も見事でした。
石原「もちろん映画が好きでつくってるから、映像の快楽に吸い寄せられるようなところがあって。かんなが天使の格好をしてタバコを吸ってるシーンとか、あれはかんながタバコを吸いたいって吸ってるんだけど、撮ってみたら言葉がいらないものになってるんですよね。あの人生を送ってきた人が天使の格好でタバコを吸っているーーそれだけでとても意味があることで、カメラの前でああいうことをしてくれているということ自体に意味がある。ドキュメンタリーだけど、そういう映像の快楽みたいなものを入れることで、ただ記録の提示じゃなく映画として成立させるということはめちゃくちゃ考えたところです。
同時に、さっき言ったように綺麗な映像を撮るよりも映ってる対象の気持ちや動きを捉えることの方が重要なんだということも踏まえていました。それがやっぱり物語の力だから。綺麗にということを意識しすぎるとそれはある種広告のようになっていくから、映像の快楽は重要視しつつも綺麗な映像を撮ろうとは思わないというバランスでした」
――最後になりますが、改めてクラウドファンディングの目標達成おめでとうございます。
石原「ありがとうございます。シェアしてくれたみんなのおかげです。ビックリしたし、感動しました。作品づくりって祭りのようだなと思うんです。祭りがないときは一人で生活をこなして働いて生きていくけど、つくるとなったらみんながバーッと集まってある種の共同体みたいな祭りの状態で過ごして、撮影が終わったら散って、また一人で編集したり。上映になったらまた集まって、上映が終わったら散っていって、ずっと祭りをやり続けている気がしていて。クラウドファンディングには400人くらいが協力してくれたんですが、こんなにもたくさんの人が見守ってくれているんだということが目に見えて感動しました。
作品をつくることはすごく大変で、全然お金にもならないし、アタシも毎回息切れして、もう無理、これ以上つくれないという気持ちになる。でも、大きなものや力が強いものに勝てるものって純粋なものしかないから、自分だけの人に伝える場を持ってつくり続けるしかない。小さくても弱くても人が見なくてもいいから、純粋に丁寧にやっていくしかないと思っています。そして、作品制作以外の抵抗の仕方として、コミュニティをつくることや、対話ができる場所をつくること、知ることなどもあって。今回の制作やたくさんの人が応援してくれたことから、コミュニティというものの大切さを感じたし、自分の名前を冠にしないような様々な女性たちのコレクティヴのようなものもやりたいなと考えるようになりました」
photography haru.
text Ryoko Kuwahara
石原海
1993年東京都生まれ、北九州在住。愛、ジェンダー、個人史と社会を主なテーマに、フィクションとドキュメンタリーを交差しながら作品制作を行う。2019年、東京藝術大学の卒業制作『忘却の先駆者』がロッテルダム国際映画祭に二作同時選出、またBBCテレビ放映作品『狂気の管理人』を監督した。21年に第15回 shiseido art eggに入選し、個展「重力の光」(資生堂ギャラリー)を開催。そして今年、初の長編映画『ガーデンアパート』がテアトル新宿を皮切りに全国劇場公開される。
NPO法人抱樸
https://www.houboku.net/about/
東八幡キリスト教会
https://higashiyahata.info/
SAVAGE GALS
curated by NeoL Magazine
https://www.contacttokyo.com/schedule/savage-gals/
2022.6.5(Sun)
16:00-22:00
@ contact tokyo
ADV : ¥2,000 DOOR : ¥2,500
U23 : ¥1,500
16:00-17:00 EARLY BIRD DISCOUNT : ¥1,500
TICKET :
https://eplus.jp/sf/detail/3628390001-P0030001P021001?P1=1221
https://contacttokyo.zaiko.io/item/348268
石原海監督『重力の光 -祈りの記録編』(2022年/72分)
1回目 16:30-
2回目 18:00-
3回目 19:30-
[STUDIO X]
CINEMA:
石原 海『重力の光』
UMI ISHIHARA”Gravity and Radiance : The full testament”
[CONTACT]
LIVE :
Maika Loubté
DJ :
LISACHRIS
Loci + sudden star
MAYUDEPTH
SAMO
LASER:
MES
[FOYER]
DJ:
GANCO
miute
nasthung
scrab
Yu Ishizuka
VIBES:
Daisuke Watanuki(zine)
DENSE(vintage clothes)
Erika (2weeks tatoo)
good junk store Brother(hot dog)
HIGH(er) Magazine(zine)
KINU(all rounder)
Kotetsu Nakazato(zine)
MA1LL (under consideration)
Tae(AT HEAVEN ceramics)
yuna(nail)
(A-Z)