
ジム・ジャームッシュらと並んで、USインディーズ映画のアイコンとして愛されてきたアレクサンダー・ロックウェル監督。ベルリン国際映画祭でジェネレーション部門の最優秀作品賞を受賞した待望の新作映画『スウィート・シング』が、10月29日に公開。クエンティン・タランティーノらと共同監督した『フォー・ルームス』(1995)以来、25年ぶりに日本での劇場公開が決定した待望の新作は、監督の実の娘(ラナ・撮影時15歳)と息子(ニコ・同11歳)が主演を務める、親密で映画愛に満ちた作品だ。スーパー16ミリで撮影した質感のあるモノクロ映像で描かれるのは、頼る大人がいない過酷な環境で生きる姉のビリーと弟のニコの物語。ある日、マリクという名の少年と出会った姉弟は、彼と一緒に逃走と冒険の旅に出る…。アルコール依存症の父親アダム役を演じたのは、カルト的な人気を誇る監督の名作『イン・ザ・スープ』(1992)にも出演した名優ウィル・パットン。監督の実の妻で俳優のカリン・パーソンズが、離れて暮らす母親イヴ役で出演を果たした。今回は映画の日本公開を前に、監督と主人公ビリー役のラナ・ロックウェルへのリモートインタビューが実現。すっかりパパの顔をのぞかせた監督と18歳になったラナが、映画の舞台裏や作品への想いをニューヨークの自宅からたっぷりと語ってくれた。(→ in English)
――映画の日本公開おめでとうございます! とても美しくて、同時に心を揺さぶられる作品で、子どもだった頃の純粋な喜びを思い出すことができました。この映画を作ろうと思ったきっかけを教えてください。
アレクサンダー・ロックウェル監督「ラナが7、8歳で弟のニコが4、5歳の頃、僕は純粋な映画製作に立ち返りたくなって、『Little Feet』(2013/日本未公開)という映画を制作しました。子どもたちが生まれたとき、自分の周りにある大切なものを映画にすることが、とてもイメージしやすくなったんです。当時の僕はハリウッドに嫌気が差していて、ハリウッド的な映画の作り方にはあまり興味がありませんでした。ある日、子どもたちが遊んでいるのを見ていたら、ゲームをしながらささやいているのが聴こえてきたんです。彼らの想像力はとても生き生きとしていて、自分たちでいろんなことを想像しては、何もないところからゲームを生み出して遊んでいたんです。本当に良い子たちで、良い人たちで、興味深い存在で。そこで僕は子どもたちとロサンゼルスで『Little Feet』を作ったのですが、それはまるで若さの泉を発見したかのような経験でした。なぜか突然、映画を作ることが再び好きになれたのです。独創的な体験で、自分の好きなように作ることができました」
――本作『スウィート・シング』は、どのようにして生まれたのですか?
アレクサンダー・ロックウェル監督「それからしばらくして、(別の映画を作ることについて)ラナと話していたのですが、僕は少し心配だったんです。というのも、幼い頃の彼女はとても自然体でしたから。ラナは弟ととても良い関係にあるし、カメラの前でも非常にカリスマ性があります。でも彼女にとって、『スウィート・シング』に出ることは大きな責任でした。前作とは次元が違って、ただ荒んだ環境で遊んでいればいいだけではなく、荒んだ大人の世界と対峙しなければならないからです。ごまかしのないものを書くべきことはわかっていたのですが、同時にラナはプロの役者ではないので、どうなるかわからなくて心配で…。大きなリスクでしたが、実際にやってみると、彼女は僕を驚かせてくれました。作品のインスピレーション源は、ラナであり、ニコであり、君と同じように、子どもたちの持つ魔法のような感覚を取り戻したいという僕の気持ちでもあります。そして、子どもたちはどんなに残酷な日々からも喜びや詩を見つけ出すことができるという事実も、この映画のインスピレーションとなりました」


――ラナは最初にお父さんから出演オファーを受けたとき、どう思いましたか?
ラナ・ロックウェル「最初に声をかけられたのは、父が実際に動き始める数ヶ月前のことでした。脚本を渡されて、『他にビリー役を演じてほしい人が思いつかないんだ。これを読んでみて、どう思うか教えてほしい』と言われたんです。それ以前に、私にはあまり演技の経験がありませんでした。幼い頃に『Little Feet』に出ただけで、当時は“演じている”という自覚があまりなかったですし、あとはニューヨーク大学の学生の短編に出演したくらいだったので。でも、特に怖いとは思いませんでした。すごく楽しそうだなと思ったし、演技にも興味があったし、たくさんの人と一緒に何かを作るのも好きなんです」
――劇中のビリーとニコの父親はアルコール依存症で、子どもたちは自分たちだけでなく、本来なら保護者であるべき父親の面倒まで見ています。日本でもヤングケアラーの問題は深刻化しているのですが、監督はなぜこの物語を伝えようと思ったのですか?
アレクサンダー・ロックウェル監督「僕自身、父がアルコール依存症だったこともあり、決して楽な子ども時代ではありませんでした。アルコール依存症の親を愛していると、複雑な気持ちになるものなんです。愛しているから守りたいと思うし、不思議なことに、子どもにとって親はいつまでもヒーローなんですよね。でも、彼らは常に子どもたちを失望させ、恥ずかしい思いをさせてしまう。ニコにとってラナがいるように、僕にも姉がいるのですが、彼女たちはある意味、母親のような存在で、僕は姉たちのおかげで困難を乗り越えることができました。アルコール依存症の機能不全な家族との辛い時期を生き延びる上で、姉たちや友人たちとの間にある友情の絆が大きな支えとなったんです」
――そうだったんですね。
アレクサンダー・ロックウェル監督「だから、もし読者の中にこのような問題を抱えている人がいたら、決して信念を失わないで、と伝えたいです。だって、君は正しいのだから。病気を患っている人を愛することはできるけど、本人が自分の体を大事にするべきだし、君は君自身のことを大切にするべきです。僕はアルコール依存症ではないし、ラナにとって良い父親だと思うのですが、彼女は信じられないほど思いやりのある心の持ち主で、想像力を働かせて、父親役のウィル・パットンのことを愛してくれました。演じているラナを見ていると、まるで幼い頃の自分を見ているようでした。彼女は思いやりと愛と誠実さに溢れていて、何の問題もなく演じることができたんです。あのような家庭で育ったわけではないのに、他人への共感力が強いんですよね。父親としてはわからないものなので、何だか不思議でした。でも、僕はどこかでラナのそういう部分を理解していたんだと思います。ニコについても同様で、彼が姉を尊敬していることもわかっていたので。2人のそんなところを信頼していたし、それは僕にとって、本作の一番の魅力なんです」
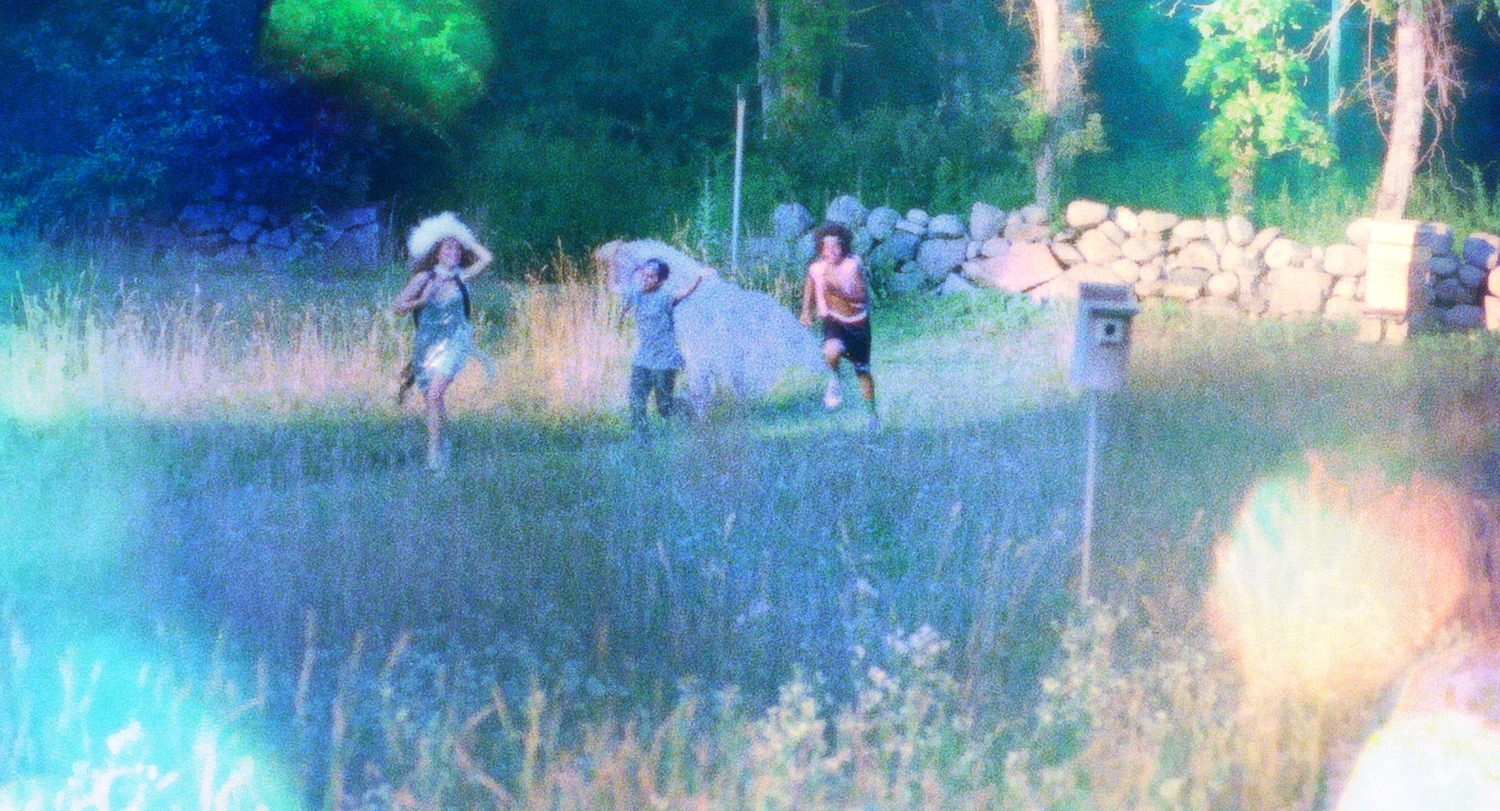

――ビリーは難しい役ですが、どのように役作りをしましたか?
ラナ・ロックウェル「私が演技を通して学んだことの一つは、他の人の気持ちに耳を傾けることです。ビリーはとても観察力が鋭くて、あまり反発しない人。そして、人生において、大人にならざるを得なかった人でもあります。そこで私は、『自分だったらどうするだろう?』と考えました。人生の中で、自分がどのようにして大人になってきたかを考えたんです。もちろん、ビリーほど極端な状況では全くなかったのですが、そういった状況を完全に包み込むことで、ビリーを正当に表現しようと心がけました」
アレクサンダー・ロックウェル監督「彼女はビリーのことを、友だちを必要としている人だと感じていたんです。まるで、誰かがビリーの面倒を見る必要があったかのように。ラナは『ビリーのためにやらなくちゃ』と言っていたよね。母親がいなくて弟の面倒を見なければならない、ビリーのような女の子を助けたいという気持ちが伝わってきて、とても感動的だった。だから、ラナは本当にビリーという女の子の手を取って、彼女を支えたんです。非常に興味深いアプローチだと思いました」
――家族と一緒の現場はいかがでしたか?
ラナ・ロックウェル「正直に言って、家族との現場は最高なんです。もちろん、一緒に住んでいるから大変なこともあります。撮影中に何かあったら、家に持ち帰ってしまうし(笑)。でも、私は父や母や弟と本当に強い絆で結ばれているので、現場では安心して過ごせました」
アレクサンダー・ロックウェル監督「それに、ラナは母親よりも親子共演を楽にこなしていました。母親の方が緊張していたんです。でも、ママとの一番激しいシーンでも、君は平気だったよね。ワンテイク撮る度に、ラナは『全然OK』って感じだったけど、カリンの方は『どうしよう! どうしよう!』って(笑)。ラナは『私を叱っても大丈夫だよ。ただフリをしているだけでしょ?』と言って、母親の緊張をほぐしていました」


――姉弟のシーンも本当に愛おしかったです。ニコは幼いのにカリスマ性がありますね。2人は実生活でも仲が良いのですか?
ラナ・ロックウェル「そうですね。姉弟ゲンカをすることもあるけれど、ニコは現場では素晴らしかったです。とても自然体で、ありえないくらい! 彼は何も考えずにできてしまうんです。ワンテイク撮るだけで最高なんですよ。ニコとは実生活でもとても仲が良いので、それは映画にも反映されていると思います」
――ニコは演じることが好きなんですか?
アレクサンダー・ロックウェル監督「だったらいいんだけど、ニコはバスケットボールに夢中なんです」
ラナ・ロックウェル「現場では良い時間を過ごせたと思うし、楽しんでいたと思います。終わった後は、『OK、あとはどうでもいいよ』って感じだったけど(笑)」
――子どもたちの父親役にウィル・パットンを選んだ理由は?
アレクサンダー・ロックウェル監督「ウィルは『イン・ザ・スープ』でクレイジーなスキッピー役を演じてくれたのですが、一緒に仕事していてとても楽しかったんです。『イン・ザ・スープ』を本当に気に入ってくれて、常にお互いをフォローしていたので、『そうだ、ウィルに脚本を送ってみよう』と思いました。というのも、僕は本作を無一文で作ったので、たとえお金がもらえなくても献身的に参加してくれて、リスクを恐れない役者が必要だったんです。ウィルは様々な仕事をしていて、大きな作品にも小さな作品にも出演しています。常に自分がやりたいことに従っているんです。本作にも参加してくれて、現場ではとても物静かで誠実でした。そして、ラナとニコを本当によく助けてくれたんです。2人とも彼のことが大好きになりました。彼らのシーンはどれも自然体で、3人の間には本物の愛情があるんです」


――マリク役のジャバリ・ワトキンスも素晴らしかったですが、演技は初挑戦だったそうですね。
アレクサンダー・ロックウェル監督「ジャバリのことはニューヨークのスケートパークで見つけたのですが、とにかくワイルドでエネルギーに満ち溢れていました。まるで炎を見ているみたいで。生命力のようなエネルギーの持ち主だから、この映画に出てほしいと思いました。でも、彼はセリフが覚えられなくて大変でした。演技の経験はなかったのですが、ラナが本当によく面倒を見てくれたんです。ジャバリを座らせて、時にはセリフを教えてあげて。2人は兄妹のように仲良くなりました」
――演技経験がないのに映画出演をオファーされて、彼はどのような反応をしていましたか?
アレクサンダー・ロックウェル監督「彼は複雑な人ではないんです」
ラナ・ロックウェル「そうだね。『うん、いいよ』って感じだった(笑)」
アレクサンダー・ロックウェル監督「ところが撮影が始まる1、2週間前に、突然ジャバリから電話がかかってきたんです。『ヤバい、映画は無理だ』って。『何だって!?』と言ったら、『脚が折れちゃった』と。スケボー中に骨折したと言うんです!」
ラナ・ロックウェル「ジャバリはいつもスケボーしているから、骨折しちゃったんです。クランクインの直前に!(笑)」
アレクサンダー・ロックウェル監督「ありがたいことに、若いから治りが早かったんだけどね。でも、『頼むよ!』という気分でした。彼はこの作品をとても気に入ってくれました。完成した映画を見せたら、奇跡だと思ったそうです。どのように映画が形作られるか理解していなかったんですよね。彼はとても誇りに思ってくれました。出演してもらって本当によかったと思っています」


――ヴァン・モリソンの曲「Sweet Thing」を映画のタイトルにした理由は? よく使用許可が下りましたね!
アレクサンダー・ロックウェル監督「不可能に近かったよ(笑)。僕は頭の中であの曲を聴きながら脚本を書いたのですが、曲の使用許可を得ようとまでは考えていなかったんです。その後、ラナがあの曲を覚えて、劇中でも歌ってくれて。僕は“I will never grow so old again(もう2度と大人になんてならない)”という歌詞が気に入って、映画のタイトルを『スウィート・シング』にしようと決めました。とても美しいフレーズだし、この作品の核心を語っているので。編集が終わった後、曲の使用許可について調べ始めたのですが、どこに問い合わせても無理だと言われた上、大手のレコード会社からは高額の使用料を提示されました。そして最終的に、スイスのとある人物を通してヴァン・モリソンのマネージャーとつながったんです。ラナの歌った音源を本人に送ってもらったのですが、どうやら、それを聴いて承諾してくれたみたいで、その翌日には使用許可が下りました。だから、僕の周りではヴァン・モリソンの悪口は禁止なんです(笑)」
――本作は監督のポケットマネーとクラウドファンディングで集めた資金で制作したそうですね。現在、独立系のフィルムメーカーが資金調達するのは難しいことなのでしょうか?
アレクサンダー・ロックウェル監督「今はインディペンデント映画にとって、とても大変な時代です。アメリカ映画は、かつてはヨーロッパや日本から支援を受けていました。『イン・ザ・スープ』は、日本からも一部の支援を受けて製作したんですよ。どういうわけか完全には理解していないのですが、今のアメリカではすべてがハリウッドにコントロールされています。インディペンデント映画でさえハリウッドにコントロールされているのです。僕はジム・ジャームッシュやスパイク・リーたちとやっていた時代が好きで、みんなニューヨークから発信していました。そんな彼らも、今ではもっと規模の大きな作品を手がけています。でも、僕はハリウッドの大作はやらないし、ハリウッドのお金で映画は撮りたくないので、別の方法を模索する必要があるんです。それに僕はいつだって、映画を作るのはお金ではなくて人だと思っています。ジョン・カサヴェテスが『今週末はうちに来いよ』と言って、みんなで映画を撮ったようにね。今回は配管トラブルで自宅の地下室が浸水したので、手元にいくらかお金がありました。修理のための保険金が下りたので、妻に『地下室の修理は後に回して、このお金を映画に使ってもいいかな?』と聞いたんです(笑)。妻はOKしてくれました。それがカリンなんです。彼女は素晴らしい人なんだ」
ラナ・ロックウェル「実話です(笑)」
アレクサンダー・ロックウェル監督「そこで僕は修理費を映画につぎ込み、学生たち(※監督はニューヨーク大学大学院ティッシュ芸術学部映画学科の監督コース長を務めている)と、ウィルとカリンと子どもたちと一緒に撮影しました。そして、仕上げの段階になってから、クラウドファンディングで音楽やポスプロのための資金を集めたんです。本作はクラウドファンディングなしでは完成できませんでした。確かハル・ハートリー監督も、この手法で映画を撮っているんじゃなかったかな」


――ついに『スウィート・シング』が日本公開されますが、今のご気分は?
アレクサンダー・ロックウェル監督「みんなで日本に行きたかったね。皆さんと一緒に日本に居られないことが本当に残念です。日本の観客に会って、本作で描いたアメリカの一面を共有したかったな。前にも話したことがあるんだけど、日本の映画監督で『万引き家族』を撮った…彼の名前はどう発音するんだっけ?」
――是枝裕和監督です。
アレクサンダー・ロックウェル監督「僕は彼を兄弟のように感じていて、とても尊敬しています。会ったことはないんだけど、ぜひ会ってみたいんです。彼による、子どもたちや問題を抱えた家族の描き方といったら…彼はインスピレーションなんだ。僕らは同じ言語で話せるような気がするんだよね。だから、この映画を楽しんでくれる観客も、きっと日本にはいると思うんです」
――最後に日本の映画ファンにメッセージをお願いします。
アレクサンダー・ロックウェル監督「日本で皆さんとお会いしたかったです。この映画を観るときは、ラナとニコと僕が皆さんと手をつないでいると思ってください。これは僕たちから皆さんへの手紙なのですから」
ラナ・ロックウェル「私たちの心は、皆さん一人一人と共にあります!」
text nao machida
『スウィート・シング』
10月29日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷、新宿シネマカリテ、アップリンク吉祥寺他全国順次公開
http://moviola.jp/sweetthing/
原題:Sweet Thing|2020年|アメリカ映画|91分|DCP|モノクロ+パートカラー
監督・脚本 : アレクサンダー・ロックウェル
出演:ラナ・ロックウェル、ニコ・ロックウェル、ウィル・パットン、カリン・パーソンズ
日本語字幕:高内朝子 配給:ムヴィオラ
©️2019 BLACK HORSE PRODUCTIONS. ALL RIGHTS RESERVED
text by nao machida
「病気を患っている人を愛することはできるけど、本人が自分の体を大事にするべきだし、君は君自身のことを大切にするべき」アレクサンダー・ロックウェル監督&ラナ・ロックウェル 『スウィート・シング』 インタビュー/Interview with Alexandre and Lana Rockwell about “Sweet Thing”
1 2




























