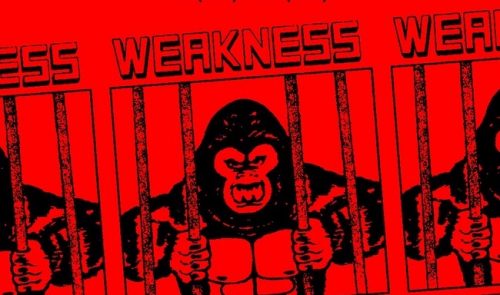『舟を編む』『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』で知られる石井裕也監督がオール韓国ロケで挑んだ最新作『アジアの天使』が7月2日(金)より公開。痛みや葛藤を抱えた二つの家族が交わり、言葉や国境を超えた人と人としての関係を築くこと、そして予想だにしない天使との邂逅で、各々が“自分”を見つけていく様を描く。作家、青木剛を演じたのは石井監督に絶大な信頼をうける池松壮亮。彼が本作で見た“天使”とはなんだったのかーー池松に聞いた。
――予想の斜め上で驚きましたし、希望を感じる映画でした。初号をご覧になった時、どういう印象を受けましたか。
池松「僕は自分が関わった作品こそ厳しく観ているようなところがあるのですが、想像していたよりもはるかに良いものが完成しました。いろんなことを経てずっと見守ってきた作品ですが(*2017年に企画が立ち上がるも撮影延期)、その中で想定していたよりもかなり良かった。やっていることや目指してることがものすごく前に出たような気がしました。これは2020年の2月から3月にかけて撮っていて、コロナと追っかけっこはしたものの、ここまで世界がひっくり返る前の段階で撮影を終えていたんです。そこから石井さんを始めとした仕上げチームはコロナで韓国での編集ができなかった。たくさんの困難を経たことで、経た答えや人に対する眼差しなどが上がりに入っていて、凄いところに到達していました。この映画がそもそもやろうとしていたことが、ある意味コロナや困難を経験したことでさらにパワーアップして、浮き彫りになったような感じがしました」
――石井監督作品にはずっと分断に対する危機感のようなものが描かれていて、本作でもそれは大きなテーマですが、おっしゃるように全く違う次元に到達していると感じました。
池松「そうですね。元々は日本と韓国との関係にフォーカスしつつ、その奥にある人対人の分断をテーマにした映画になると思っていたんです。撮影時はちょうど国同士の関係が悪化していて、本編にも使われていましたが、“戦後最悪”というような記事が日々出ていて、不買運動などもすごかった。それが世界中にコロナが拡がったことで、1対1の関係ではないもっと大きなものにみんなが直面せざるを得なくなった。決して喜ぶべきことではないけれど、この状況になって本作の意味がより大きくなるのではないかと思います」

――まさに本作でも描かれている痛みの共有ですね。この作品に出てくる人たちは何かしらの分断やバイアスを乗り越えて、自分の目で見て感じ体験していくことでアイデンティティを再確立していきます。その中でも中心的役割を担う剛という役柄を演じるにあたって、土台としたようなご自分の体験や感情はありますか。
池松「今回の役で一つ言えるとすれば、20代最後の撮影だったことはとても大きかったです。3、4年前から、時代の変わり目であったり、それに伴うネガティヴな感情、各地で破壊が起こっているという感覚があって。それは夜明け前でもあり、どこかで破壊が終わって再生が来るはずだとも思っていました。その夜明け前の最後に何ができるかということを考えた時に、キャラクターというフィルターを借りて、生きてきた29年の間に自分に溜まった膿をちゃんと役に持ち込んで、再生すること。そして自分1人で再生するのではなく、人と再生すること。国も関係なく、言葉も関係なく、ただ人と人として再生すること、そういうことはできるんじゃないかと思っていましたね」
――言語が違う人々との対峙はもちろん大きな軸ですが、同時に剛にとっては息子である学(佐藤 凌)との関係の再生も大きな軸です。石井監督は「剛は自分のアバター」とおっしゃっていましたが、学も監督の一種アバターだと思いました。
池松「仰る通りです。学がいることで、大人は無垢なるものに常に真っすぐ見つめられている感覚が生まれます。価値や言葉、概念に縛られて彷徨う大人たちをただ見つめている。ある種、学は一番の天使なんですよね。ああいう目が大人たちの何かに制御をかける。そこから愛や概念の超越を目指していく。そして石井さんにとって今作は初めての海外制作で、ある意味自分の一番ピュアな部分、最も信じてきたもの、その原点にかえることを強いられた、もしくは自分に強いたと思います。その原点こそが学という息子であったとも思います。いろんな要素を持った、面白い設定ですよね」

――兄の透を演じたオダギリジョーさんも石井監督作品には大きな存在であり、主演ドラマには天使も登場しています(石井監督演出のTVドラマ「おかしの家」)。お二人の共演は、それぞれが監督作品で持つ意味や役割の交差でもあるのかなと思いました。透との関係性に関してはどう捉えられましたか。
池松「キャラクターを2つに分けることで対比が生まれ、映画の幅が広がり、意見の幅が広がったと思います。剛としては、あの兄貴がいることでああいう弟になってしまうところと、救われる部分と、いろんなことを表現できたらなあと思ってやっていました。いつも喧嘩したり、文句や冗談を言い合ってる兄弟なんですけど、ちゃんと大切なところは繋がっているんですよね。あの兄をオダギリさんがやってくれたことで、上部だけではない説得力が出た。あんなに愛情深い人はいないんですよ。常々共演するたびにすごいなと思っているんですが、本当に素晴らしい俳優さんで、目には常に情深さとパンクな精神を孕んでいて、それでいてものすごく深い品性とユーモアがある。今回はこの映画にとっての緩みと温かみを請け負ってくださったので、オダギリさんのある部分の良さがふんだんに詰まっていると思います。そしてオダギリさんも韓国が大好きなので、撮影自体をすごく楽しんでいたように思います」
――オダギリさんに限らず、韓国の俳優陣やスタッフ陣との制作は全体的にとても楽しいものだったとお聞きしています。
池松「そこに関しては心から感謝しています。監督が石井さんで、僕がいて、オダギリさんがいて、あと2、3人の日本人がいて、それ以外は全て韓国の方というクルーだったんですね。もちろん助け合ってはいるんですけど、制作共同体で言うと、物事を決めていく立場に日本人がいたので、国と国のことを考えると、ひょっとしたら受け入れてもらえないかもしれないし、反発を食らうかもしれないと覚悟していたんです。でもみんな映画に対してものすごくピュアな方々で、価値観や文化の違いを感じることはあっても、そうした意味での反発などは全くなく受け入れてもらえたんですね。そのことが何よりこの映画を経た財産ですし、こんな状況じゃなかったら本当はすぐにでも会いに行きたい。本当にかけがえのない仲間たちに出会いました」

――タイトルにもなっている“天使”ですが、天使はいろんなメタファーとなっています。私は資本主義からの脱却だったり、思い込みなど様々なものからの解放という風に感じたのですが、池松さんはあの天使をどのようにご覧になりましたか。
池松「自由に観ていただきたいので、解釈を限定するつもりではなく個人の見解として話すと、おっしゃっていただいた通り、自由、解放のメタファーだと思います。人間は信じ込めるからここまで繁栄してきたわけで、その信じるという能力は素晴らしいことだと思うんですが、間違ったことを信じる力も強い。その歪みが、いま世界が混沌としている理由の一つだと思うんですね。僕が普段使っている言葉も、国境も、誰かが決めたもの。そして神も人間が作ったもの。誰が天使は子どもで外見が美しいものだと決めたのか。あるいは美しいという価値観は誰が決めるのかーーそういう“いつからか真実を見失った者たちが意味や価値を超える”ことのメタファー。石井映画にはこれで6回目の出演ですが、ここまでそこにフィーチャーしたものは初めてだと思います。人間は、共に信じてくれる人がいればどんなものだって神様にできるはずだと、おそらくそういうことをやろうとしたのではないでしょうか。世界を見渡すと、思想や宗教、人種や違いという隔たりによってこれまでたくさんの尊い命が失われてきました。違いを超えて手を組むこと、愛をもって誰かが誰かの救済に向かうこと、そこに天使は舞い降りる。そういうことを見てもらえるのではないかと期待しています」
photography Yudai Kusano
hair & make-up Fujiu Jimi
text & edit Ryoko Kuwahara
『アジアの天使』
http://asia-tenshi.jp
7月2日(金)テアトル新宿ほか全国公開
出演:池松壮亮、チェ・ヒソ、オダギリジョー、キム・ミンジェ キム・イェウン 佐藤凌
脚本・監督:石井裕也
エグゼクティブプロデューサー:飯田雅裕 プロデューサー:永井拓郎、パク・ジョンボム、オ・ジユン
撮影監督:キム・ジョンソン 音楽:パク・イニョン
配給・宣伝:クロックワークス
(c) 2021 The Asian Angel Film Partners
<ストーリー>
8歳のひとり息子の学(佐藤凌)を持つ小説家の青木剛(池松壮亮)は、病気で妻を亡くし、疎遠になっていた兄(オダギリジョー)が住むソウルへ渡った。ほとんど韓国語も話せない中、自由奔放な兄の言うがまま怪しい化粧品の輸入販売を手伝う羽目に。
元・人気アイドルのソル(チェ・ヒソ)は、自分の歌いたい歌を歌えずに悩んでいたが、亡くなった父母の代わりに、兄・ジョンウ(キム・ミンジェ)と喘息持ちの妹・ポム(キム・イェウン)を養うため、細々と芸能活動を続けていた。
しかし、その時彼らはまだ知らない。
事業に失敗した青木と兄、学たちと、資本主義社会に弾かれたソルと兄、妹たち ──
どん底に落ちた日本と韓国の2つの家族が共に運命を歩む時、ある“奇跡”を目の当たりにすることを・・・。