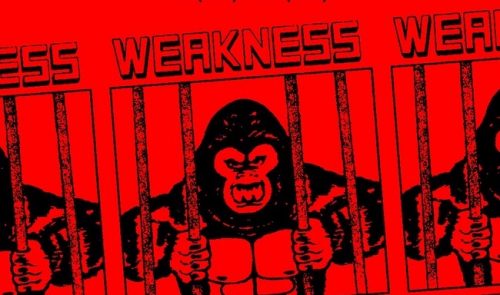この年末、34年もの年月を隔てて製作された二作品がほぼ同時期に劇場公開を迎える。ひとつは1986年に林海象監督が初めてメガホンを取り、佐野史郎が私立探偵役で映画初主演に挑んだ伝説のモノクロ・サイレント作『夢みるように眠りたい』(デジタルリマスター版)。もうひとつは、原発から漏れ出す冷却水を止めるべく、作業員たちが命がけでボルトを締めに向かう最新作『BOLT』。両作に触れることは、二人の映画人生の出発点と現在地を目撃することでもある。夢を必死に追いかけ、制作を続けたその軌跡。そして現代を生きる若者たちへ伝えたい言葉とは。デビュー以来、型にはまらない表現の可能性を追究し、互いを知り尽くしたコラボレーションで人々を魅了し続けるお二人に話を訊いた。
--今回、34年ぶりに公開となる『夢みるように眠りたい』(86)は、林さんにとっての初監督作であり、佐野さんにとっての初主演作です。その後、最新作『BOLT』に至るまで、幾つもの映画作品でご一緒されてきたお二人ですが、いちばん最初の出会いのことは覚えていらっしゃいますか?
佐野史郎「本当に最初に会ったのはいつだったんだろう……?」
林海象「たぶん、あがた森魚さんに連れてってもらった遠藤賢司さんのライヴに、佐野さんがギターで出ていて」
佐野「あ、eggman(渋谷にある老舗ライヴハウス)か。それが最初かな。遠藤賢司さんのバックを僕と嶋田久作が務めていたんですね。あの頃、嶋田たちとバンドを始めた頃で、あがたさんや遠藤さんの周囲にみんなが集まってきて、何か面白いものが生まれそうな可能性に満ちた時代でした。最初は、あがたさんから『映画を撮るんで手伝ってくれないか』って話だったんですけど、その企画が結局なくなって、並行して進行していた『夢みるように眠りたい』の林監督が僕に声をかけてくれたんです」
林「最初にお会いした時には佐野さんのことを俳優さんだとは全然知らなかったんです。で、交流を重ねてお芝居などを見る中で、ものすごく”昭和の顔”の人だ、と思って。それは僕がずっと探していた主役の顔にぴったりだったんですね」
--サイレントで、モノクロで、初監督作。今の映画界を考えると、なかなか実現の難しそうな企画ですが、当時の林監督にはそれができた。そこにはどんな秘訣が?
林「秘訣なんて何一つないですよ。あれができたのはやっぱり、集まってくれた人々が素晴らしかったから。そして、僕は今でもそうなんですけど、映画の作り方として絶対に『形から入らない』。潤沢な資金を用意してくれるプロデューサーなどはいなかったけれど、その分、変な方向へコントロールする人たちもいなかった。それが恐らく、今でも残る映画になった理由だと思いますね」
--佐野さんのどういう才能や特質がこの映画にハマったのでしょうか?
林「この映画は無声映画なので、役者にとってほとんど演技する間がないんです。ワンシーンが短くて、細かい描写の繋がりでできていますから。佐野さんがそういったサイレント映画の構造についてよく理解してくれる人でしたから助かりました。つまり、意味を理解せずに、演技をするっていうことですよね。ちょっとわかんないけど、とりあえずやってみようっていう。逐一『これ、どういう意味なの?』とかって聞かれたら、たぶん、答えられないし、できなかったですよね」
佐野「出会いのタイミングが良くてね。監督は監督でこの映画をどうしても撮らなきゃという切実さがあったのと同時に、僕は僕で直前まで状況劇場にいて、唐十郎さんから『お前みたいな芝居してたら、映像の演技なんかできないぞ』と言われて。これが本当に大きい一言だったんですね。それがきっかけで退団して、並木座(銀座にあった名画座)に通って、じゃあ、映像の演技ってどういうもんだろうって、清水宏や小津安二郎、成瀬巳喜男などの作品を観まくって研究してたんです」
--なるほど。
佐野「そのタイミングで『夢みるように眠りたい』の台本を渡された。林監督が求めていた“何もしない演技”をサイレント時代の作品を見て勉強しつつ、優れた演出家や監督が必ず口にする『何もしないで、ただそこにいればいい』という意味を僕なりに探る毎日だったんです」

--佐野さんから見て当時の林監督はどんな存在でしたか。
佐野「何よりもまず(江戸川)乱歩が好きとか、好きなものが僕と似てるので、とても嬉しかったですね。お互いにまだ何も知らないことだらけでしたけど。でも、同じ世界が好きだっていうことだけははっきりしていて、近かった。そこがやっぱり大きかったですね」
--35年ものあいだ、ずっと友情が続く理由はなんでしょうか。
佐野「それは監督が声かけてくれるから(笑)」
林「楽だからですね。趣味が合うのと同じで。まあ、プライベートでも会いますけど、なんか無理に仲良くしようとしてないんですよね。映画においてはいつも頼りになりますし、本当にありがたい友達ですよね」
--『夢みる』の後しばらくすると、バブル崩壊を迎えます。しかしお二人の勢いは失速するどころか、佐野さんは「冬彦さん」(1992年TBS系列ドラマ「ずっとあなたが好きだった」で佐野が演じた役所)ブームで日本全国の知るところとなり、林監督は「濱マイク」シリーズ(1994年より公開された探偵映画/ドラマシリーズ)という金字塔を打ち立てます。経済的な逆境にもかかわらず、これほど突き抜けられたのはなぜなんでしょう。
林「それは若い頃にもっと苦しい時代を味わっていたからですよ。もっと下のどん底から這い上がって来ましたから。バブルが崩壊すると、何かを作るのにちょっと時間がかかったりもしたのかなあ。でも全然辛いとは思わないですね。むしろ僕らはバブルってのにかなり巻き込まれた方なんで、その世代としてある意味、ラッキーというところはありました。だって僕、『帝都物語』(88)の脚本を29歳の頃に書いてるんですよね。今そんなこと絶対ないでしょ。『ZIPANG』(90)を撮ったのも30歳くらい」
--佐野さんはご自身の80年代の終わりから90年代にかけての流れをどうご覧になられますか?
佐野「『夢みる』があったからこそ、それを観た黒木和雄監督の『TOMORROW 明日』(88)に呼んでもらえたし、ウルトラシリーズの大ファンとしては『帝都物語』で実相寺昭雄監督とご一緒させていただけたのが光栄でした。そのあとも大御所の大作に立て続けに出演させて頂けて。日独合作の超大作とかね。そういう様々な映画経験は、バブル期じゃないとできなかったと思いますよ」
林「僕らはラッキーだったよね」
佐野「恩恵はものすごく受けてます。『ぼくらの七日間戦争』(88)のヒットの影響もありましたし。あの意地悪な教師役のおかげで、それからTVドラマの方からもお声がけいただくようになったんです。その頃の一作一作がその後の『冬彦さん』へと繋がるきっかけを作っていったと思います。自分としては世間の反応にかなり面くらいましたけどね」

--現在の新型コロナによる経済的な影響は、バブル崩壊やリーマンショックなどの時代に喩えられたりしています。映画界にも影響が及ぶこの状況をどう見つめていらっしゃいますか。
林「確かに興行を打つのにね、不利ですよね。気軽に外出できないっていう状況がね。そこは懸念すべき点ではありますけど、結局、物作りっていうのは若い人が中心なんですよね。だから今の状況だけを見て判断しない方がいい。不自由さを自分の中で規定してしまうのは変だと思います。だからコロナの先を考えた方がいいんじゃないですかね。こういう悪い時だからこそ、いいところばっかり見た方がいいですよ。
仮に、今の状況と昔で似たところがあるとしたら、それはやっぱり『若い人になかなかチャンスが巡ってこないこと』だね。でもこの壁は、いついかなる時代でも、若い人間が自ら突破するしかないんですよ。自信と力を持って」
--まさに若い世代の人たちが本当に欲してる言葉だと思います。
林「信じるっていうか、やるしかないですよね。誰も信じてくれないんだから、せめて自分たちくらいは自分たちのことを信じてね。で、友達同士で、気が弱くなったら、俺たち間違ってねえよなって。とりあえず何の効果もないことを言い合って、それでちょっといい気持ちになって。そんな風景は昔と全く変わらないんだと思いますよ」
佐野「みんないろいろ必死に探ってたんだよね」
林「自分のことで精一杯で、人に構ってる暇なんてなかった」
佐野「今年は緊急事態宣言で家から出ちゃいけない、現場も全部止まってるという時に、何をしたかっていうと、東宝の特撮や円谷プロの作品を一作目から見直してたんです。時間がある時に一番やりたいことをやってみようと。ああ、やっぱり俺はこれがいちばん好きなんだってつくづく思い知らされましたよ」
林「そうだね。このコロナ禍で自分が本当に好きなものとか、何をやりたいのかってことがはっきりしたように思います。あとは……我々もちょっとばかし余裕が出てきたから、若者を応援した方がいいよね。僕ら、いつも言われてたじゃん。木村威夫(日本映画界を支えた美術監督。2010年没)先生に。『きっといいことありますよ!』って。あの言葉にはずいぶん救われました」
佐野「木村先生もそうだし、若松孝二監督も、石井輝男監督もみんな信じられないくらいバイタリティに溢れ、お元気な方ばかりだった。僕らは本当にお世話になったよね」
--さて、『夢みる』と同時に、最新作『BOLT』も公開を迎えます。作業員が若者に対して「俺たちの責任だ。俺たちに(責任を)取らしてくれよ」って口にするシーンがありますが、ここには林監督や佐野さんが若者の世代に対して寄せる思いが込められているように感じました。
林「やっぱりあの原発問題って、我々50代以上はみんな加害者なんですよね。たとえ何も知らなかったとしても、何もしなかった以上は、当事者意識をきちんと持っておいた方がいいと僕は思ってます。そして僕らの世代のうちに止めた方がいい。負の遺産を若い世代に残さない方がいい。これだけははっきりしています」
--原発を描いた『Fukushima50』から一転して、佐野さんは一作業員の役を演じていらっしゃいます。
佐野「『Fukushima50』では首相役でしたけど、ああいう立場に立たされたら人は誰でもああなっちゃうんじゃないかなってのは思いましたよ。もちろん個人の性格の問題はあるでしょうけど、でもあそこに立たされたときに、何を選択するかっていうのは、今は僕らはその後を知ってるからいろいろ言えるけれど、少なくとも自分は、こうなってもおかしくないなって思いながら演じてましたね」
林「問題は、一つの鍋の蓋が開いてて、それを閉めないうちに次の蓋を開けようとしてることなんですよね。この状況をなんとかしなければいけない。そう考えると、『BOLT』で命がけで現場へ向かう一人一人が、僕ら自身なのかものかもしれません。この映画は別に反原発や脱原発でもないフィクションですけど、現状として放射能が止まってないというのは事実なので、その問題を受け止めつつ、様々なことに思いを広げて頂きたいですね」
--防護服や巨大セットも印象に残りました。
林「現代美術家のヤノベケンジさんが手掛けたものです。高松市美術館に創り上げた巨大セットはもちろん、そのほかの細かいものも全てヤノベさんがデザインしてくれました。言うなれば『エイリアン』のH・R・ギーガーとリドリー・スコットみたいな関係ですよね。芸術家とこれほど強力なタッグを組んで映画を作ることって珍しいんじゃないですか」
--確かに。
林「その点、アート映画とも言えるのかもしれません。とにかく80分ジャストなので、手軽に見れますし、見て頂けたら確実に面白いと感じてもらえるはず。『夢みる』と併せて観るともっともっと満足できる。そう多くの人に伝えたいです」
佐野「『夢みる』と『BOLT』、同じ監督のデビュー作と最新作が同時に公開されるなんて滅多にないこと。昭和の建造物と現代アートが重要な点も重なります。両作品とも僕の中では、大好きな特撮映画にもつながる”幻想怪奇映画”というべきもの。ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいですね」
『BOLT』
2020年12月11日(金)よりテアトル新宿ほか全国順次公開
http://g-film.net/bolt/
2015年から2017年にかけて製作された『BOLT』『LIFE』『GOOD YEAR』の3つのエピソードで構成された人間ドラマ。ある日、日本のある場所で大地震が発生。その振動で原子力発電所のボルトが緩み、圧力制御タンクの配管から冷却水が漏れ始めた。高放 射能冷却水を止めるため、男は仲間とともにボルトを締めに向かう。この未曾有の大惨事を引き金に、男の人生は大きく翻弄されていくーーー。監督は、『夢みるように眠りたい』『我が人生最悪の時』『弥勒MIROKU』などを手がけてきたほか、プロデューサーと しても活躍する林海象。主演は、林海象と何度もタッグを組んできた盟友、永瀬正敏。そのほか、佐野史郎、金山一彦、後藤ひろひと、大西信満、堀内正美、月船さららが脇を固めるほか、佐藤浩市が声の出演を果たした。現代美術家、ヤノベケンジが香川・ 高松市美術館に創り上げた巨大セットや防護服などの近未来的なデザインも圧巻。
脚本・監督:林 海象
出演:永瀬正敏 /佐野史郎/後藤ひろひと/金山一彦/吉村界人/佐々木詩音/大西信満/堀内正美/月船さらら
BOLT|2019年|80分|脚本・監督:林海象
制作:東北芸術工科大学
製作・著作:レスパスビジョン / ドリームキッド / 海象プロダクション
『夢みるように眠りたい』
2020年12月19日(土)よりユーロスペースほか全国順次公開
http://g-film.net/dream/
大正7年。初めての女優主演映画といわれる帰山教正監督「生の輝き」の以前に、実は月島桜が主演した「永遠の謎」という映画があった。しかし、この「永遠の謎」は、警視庁の映画検閲によって妨害され、ラストシーンが遂に撮影されないまま、その名を映画史から消されてしまった……。 昭和のはじめ、東京。私立探偵・魚塚甚(佐野史郎)の元に、月島桜と名のる老婆(深水藤子)から、誘拐された娘・桔梗(佳村萠)を探して欲しいとの依頼がくる。調査を続けるうちに、魚塚は、この事件全体がまるでドラマのように出来すぎていることに気がついていく……。
製作・監督・脚本:林海象 撮影:長田勇市 製作:一瀬隆重 美術:木村威夫 音楽:熊谷陽子 / 浦山秀彦 / 佳村萠 / あがた森魚 照明:長田達也
出演 : 佳村萠 / 佐野史郎 / 大竹浩二 / 大泉滉 / あがた森魚 / 小篠一成 / 中本龍夫 / 中本恒夫 / 十貫寺梅軒 / 遠藤賢司 / 草島競子 / 松田春翠 / 吉田義夫 / 深水藤子
2020年デジタルリマスター(初版1986年)|84分
脚本・監督:林海象
製作:映像探偵社|宣伝・配給:ドリームキッド / ガチンコ・フィルム
photography Yudai Kusano
text Atsunobu Ushizu
edit Ryoko Kuwahara