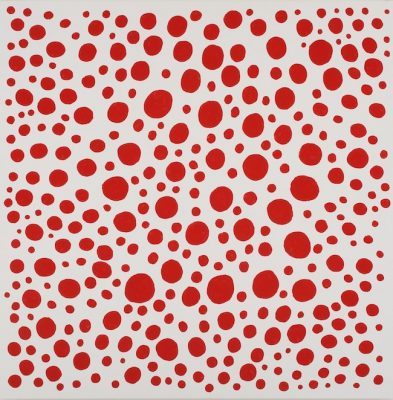阿波屋のことを考えるとあまりにも強い思い出がありすぎるため、どこから始めたらいいのかわからなくなってしまう。阿波屋とは、町屋駅から徒歩10分ほどの三角地帯に立った飲み屋(厳密にはおにぎり屋らしい)のことである。座席5席のめちゃくちゃ狭い、人数が多い時は隣の空き地に適当に座って飲める、夜23時頃から明け方にかけて開く看板も値段もない深夜食堂で、荒川区に住んでいた2年間のなかでアタシにとって最も大きな存在であった。
阿波屋との出会いは大学3年生の頃で、その時アタシはまだ目黒区に住んでいた。藝大の同期であるいまは北千住で髭という古着屋を営んでいるしゅんちゃんに連れて行ってもらったのが初めてだった。(髭、暖簾がかかった面白いところなのでぜひ寄ってみてね。)北千住にある飲み屋街を抜けたキャンパスの授業後に、または授業に行くつもりが道端でしゅんちゃんと出会ってしまい授業をサボって酒をひたすら飲み続けた調子のいい夜の最後に辿り着く、深夜に開く狭くて汚い場所が阿波屋だった。目黒に住んでいたから遠さゆえに数回しか行ったことがなかったけれど、その後縁があって荒川区に引っ越すことになったとき(都内のクラブにすぐ行ける距離の、住み慣れた目黒を離れるのは抵抗があったけれど)なによりも頭の片隅には阿波屋のことがあった気がする。これでアタシはいつでも阿波屋に行けるんだなって。そして、クラブに行く回数よりも阿波屋に行く回数が増えたあの荒川区の2年間の記憶を思い出そうとすると、すべての記憶がまるで阿波屋を中心に取り巻いているかのような気にさえなってしまう。
阿波屋には少ない時で10日に1回、多い時で週に2回は行っていた。阿波屋に行く日のパターンはだいたい2つあって、深夜1時頃前に終わるバイト帰りにそのまま終電に飛び乗って町屋駅で降りて歩いていくパターン。または、出かけていて直接家に帰る代わりに、当時一緒に住んでいた元恋人との待ち合わせ場所としてもよく使っていて、どちらかがひとりで先にここに来て静かに飲みながら相手を待ったりした。阿波屋からの帰り道、二人で酔っ払いすぎてここには書けないほどの壮絶な喧嘩を繰り広げたり、または二人乗りしたチャリから転げ落ちて、誰もいない夜明け前の都営荒川線沿いの舗道でゲラゲラ笑ったまま道路に寝っころがってにんにく臭い口でキスをした。あとは文字通り、深夜食堂として使うパターン。家から一歩も出ずに締め切り間近の映像の編集や執筆をしていて深夜にさしかかった頃、今日はとりあえずここまでにして、まだ食べていない夜ご飯でも食べて一杯飲むかなと、束の間の休息として阿波屋に向かったりした。
阿波屋の良さを説明しようとしてもなかなかうまく言葉にできない。さらりと生活に溶け込んでくるのに、毎回行くたびに静かな奇跡と出会う、そんな場所だった。一度そこを訪れただけで特別な場所だってことがわかる、そして行けば行くほど、どんどん愛が増えるような。あえて言葉にするならばまるでスルメイカ、かっこつけて言えば、なんていうか、汚れきった天国のような場所だった。汚くて、孤独で、酒と美味しいものが好きな真夜中に生きる人たちが集いあう、美しくて寂しい場所だった。この場所では、誰がなにをしているとか金を持ってるとかそうゆう社会的なことはまったく関係なくて、身なりが汚かろうが、魂さえ綺麗だったら、なんなら魂が疲れて果て汚れきっていたとしても、そこにいることがなぜだか認められるような、そんな無名の天国が阿波屋だった。

阿波屋の前のガードレール、天気がマイルドな日は夜風をあびながら外で飲んだ
おじちゃんはいつも無口で、話しかけると滑舌の悪いまま、ああ、とか、そうだねえ、とか、そんなんじゃねえよ、とか適当な感じで返事をしてきて、あとは淡々と、客に出すのと同じくらいめちゃくちゃ濃い、ほぼ原液に近い宝焼酎の水割りをカウンターの中で飲んでいた。阿波屋に行くときは(何があってもこの場所に行き続けたいから粗相のないようにしなきゃ&酒がとにかく信じられないくらい濃いからいつもと同じ飲み方をしてはいけないというこの二つの理由により)少しだけピリっと背筋がはる緊張感があり、あんまり極端に酔ったことはなかったけれど、とはいえ数回ほど、記憶をなくしそうになるくらい泥酔したことがあった。泥酔した数日後に、おじちゃんこの間はごめんね、と申し訳なさそうにしょぼしょぼと店に入ると、そんなことなんてあったっけ忘れちゃったよととぼけたまま、相変わらず何も言わずに信じがたいほど濃すぎる蕎麦茶割りを出してきて、これと言った会話をするでもなく、帰りがけにおい元気だせよと、ビニール袋に入った大量の漬物をくれたりした。
元々はおにぎり屋で、学校や会社に行く人にむけて朝方おにぎりを売っていたのが阿波屋の原型らしい。そして、なんだかんだで時間がずれ込んで(そんなことあるか?)深夜にオープンする、深夜食堂になったということだった。この文章で散々、阿波屋は孤独な魂を癒してくれる〜とか汚れきった天国〜とか意味のわからないことを延々と書いてきたが、まあ実際は、それよりも何よりも、おにぎり屋という触れ込み通り、阿波屋のおじちゃんが作る食べ物がめちゃくちゃ美味しかったのだ。今日はなに作れる?と聞くと、適当なものを合わせてささっと作ってくれる食べ物が感動的だった。とくに分厚いぶりんぶりんの豚肉で作ってくれる炒めものが最高で、美味しい豚肉のなんかちょうだい、っておじちゃんにいつも聞いて、色々なものを出してくれた。あとはなぜだか刺身がとにかく美味しくて、こんな場末なのになんでこんなに新鮮で美味しい刺身が出せるんだろうと不思議に思って聞いてみたら、仕事が終わった明け方にそのまま魚を仕入れに行ってると言っていて納得だった。その日の朝におじちゃんが仕入れた新鮮な中トロマグロ刺しを、多すぎるすりおろしにんにくの入った醤油にぶっ込んで食べる、何度やっても毎回これには痺れた。あとは、生ハムがカリカリになった不思議な食感の生ハム目玉焼き、たまに仕入れてくる大好きなタコブツ、油がぎんぎんに滴るニラ玉、炊き立てのごはんで作ってくれる筋子おにぎり、そしてなんと言っても、店を開けてから作りはじめる、モツとかよくわからないものが詰め込まれたカレースープは、明け方まで居座り続けるほど煮込まれる極上のカレースープだった。

というわけで、阿波屋=天国という言葉を使ったのは、もしかしたらあらゆる食べ物の美味しさゆえかもしれない。一生、ふとした瞬間に阿波屋のおじちゃんが作ってくれたあらゆる食べ物が頭の中を駆け巡ることだろう。この謎に美味しすぎる真夜中の食べ物、またはパンチの効いた濃すぎる宝焼酎の蕎麦茶割り、そして場所そのもの、疲れ果てた魂の集う無名の優しい深夜食堂が、とにかく好きだった。好きだったと過去形なのは、残念なことに阿波屋はもう存在していないからだ。ちょうどアタシがロンドンに引っ越す前くらいから、だんだんと阿波屋は営業する日が少なくなってきていた。最後のほうは阿波屋チャレンジと呼んでいたくらい、とりあえず店まで様子を見に行ったり深夜2時頃まで近くの居酒屋で待ってみたりした。珍しく空いていた日はあまりにも嬉しくてつい飲みすぎてしまった。そして、だんだんと開くことのなくなった阿波屋は、気づいたらまったく開くことがなくなってしまい、おじちゃんの体調があまりよくないから阿波屋は閉まった、とロンドンに引っ越してすぐ、そんなことを風の噂で聞いた。当たり前だけれども、あらゆる場所や人は永遠ではない。それはもうどうにも仕方ないことである。阿波屋のことを考えるたびに、あんな不思議な場所が実在していたのだろうか?とすら思ってしまう。だからこそ自分が大切に思う場所には、そこが存在しているうちに、何度も何度も、しつこく足を運ばなければいけないのだ。人生の中で、そんな場所に出会うことはなかなかないのだから。ロックダウンで好きな店になかなか足を運べないなか、なんだか阿波屋のことを書き、そして愛しの酒場/食堂のことを考えるとついセンチメンタルな気持ちになってしまう。たくさん食べてたくさん飲んで、お金の許す限り、これからも大好きな店にお金を落としていきたいです。そのためにアタシはがんばって働くのだ。そしてこれからの人生、また奇跡のような深夜食堂に、そう遠くはないうどこかで出会えますように。
最後に、阿波屋の汚すぎるぼっとんトイレに掲げられた格言で終わりにします。「惚れた涙とトイレの水は一度流せばよし」!
UMMMI.
映像作家/アーティスト
http://www.ummmi.net/
Instagram : @_____81