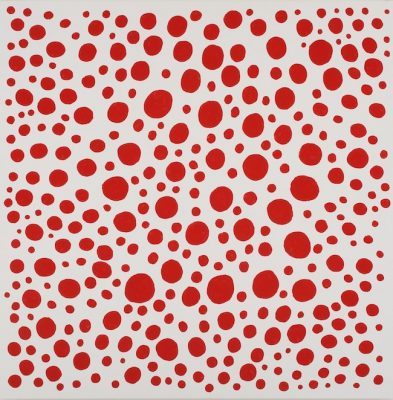食堂とは実に興味深い場所で、「食べる」という生命、生活に直結した行動を見知らぬたくさんの人々と共有する。個々で食事を楽しみたい時は放って置いてもくれるし、もちろん店主や隣に座った人と話しながら出来立ての食事を楽しんでもいい。美味しい食事を目の前にすると、まるで実家に帰ってきたような素の自分でいられる、この感覚は食堂ならではである。日本に限らず世界中で、食堂が舞台になっている作品がたくさんあるのは、ずっと変わらず人々の交流の場になっているからだろう。肩書きやイメージなどの外殻を全て抜き捨て、気取らずに行けるこの場所を大切にしたい。
江戸前期までは、階級関係なく食事は家でとるのが当たり前で、一汁一菜を基本とした質素なものであった。町人文化が華開いた江戸時代に、外食文化が発展し、「食堂」の原型ができあがったとされている。
1590年に徳川家康が江戸入りをし、1635年に参勤交代制度が始まったことで、江戸は全国最大の消費の中心地となる。また、江戸市中の3分の2を焼き尽くした明暦の大火の復旧のため集まった大工、左官、鳶など職人さんたちのような、”独り身”を相手に煮売、今で言う総菜屋が増え、火事の延焼を防ぐために設置された火除け地を呼ばれる空き地にたくさんの屋台が並び、たちまちそこは庶民の溜まり場になっていった。
江戸時代には庶民が住む長屋には本格的な台所がまだなかった。そのため天秤棒で野菜や魚、豆腐などの食材を担いで行商する「棒手振り」や「振売り」、そのまま食べれる料理を売っていた「屋台」が発達していった。江戸の4大名物食「蕎麦」「寿司」「天ぷら」「うなぎの蒲焼き」も屋台が始まりと言われている。江戸時代初期から、そういった立ち食いの「屋台」や、惣菜を店先で売る「煮売り」が数多く出てきたが、店内で飲食させる「居見世」と呼ばれるいわゆる「飯屋」「居酒屋」が発展してくるのは江戸中期に入ってから。
17世紀中旬にどんぶり飯(一膳飯)に簡単な惣菜をつけて提供される「飯屋」が登場、浅草の浅草寺境内の「茶屋」で茶飯や豆腐汁、煮しめ、煮豆などをセットにして「奈良茶飯」として販売されたのが最初と言われている。「一膳飯屋」は「煮売り屋」が発展した店で、米飯と一緒に簡単な惣菜、汁物を一緒に出したり、鍋物、酒類、菓子も提供した。

いまでいう「食堂」が生まれたのは大正時代と言われており、「白めし」を提供するが主な業だと考えるとわかりやすい。座敷ではなくテーブルで食事をするという明治以降のスタイルがまず前提としてあり、明治時代中期から、大正にかけて昔ながらの一膳飯屋、大衆化する西洋料理店、カフェーなどが入り乱れ、大正時代の食糧難の時に「公益食堂」誕生というのが大まかな流れとなっている。
1800年中期、幕末に差し掛かると、豊臣秀吉のキリスト教弾圧から始まった長い鎖国時代が黒船の来航を皮切りに終わり告げ、徳川家の勢力が衰え、大政奉還、そして明治維新へとつながっていく。今まで制限されていた海外の食文化が一気に広がりを見せ、カフェや洋食屋が発展していくのが明治、大正時代である。
明治30年代、ロマン主義派の詩人・小説家として知られる島崎藤村が7年間住んだ長野に足繁く通ったとされる揚羽屋という一膳飯屋がある。一言では語れないほどスキャンダラスな人生を送ってきた島崎が「千曲川のスケッチ」(大正元年刊行)にもその一膳飯屋と島崎との交流が描かれており、定食屋は作品として残したくなるほどの様々な出来事が起こる場所でもあったのだろう。
明治44年には銀座に「カフェプランタン」が誕生し、カフェブームが起こる。外食の分野で「西洋料理店の大衆化」がすすみ、浅草などの盛り場を中心に、名前に「バー」「カフェ」がつく大衆的な洋食屋が次々と生まれた。この「カフェ」から「食堂」や「洋食屋」あるいは「喫茶店」へ転向した店が多かったよう。

社交の場、情報交換の場として17世紀頃のイギリスでコーヒーハウスが流行り始めたように、日本でも、大正5年開業の一膳飯屋「へちま」が大杉栄、辻潤らアナーキストたちの溜まり場となっていたという記録がある。画家、アナーキストとして知られている望月桂が現在の御茶ノ水、明治大学のあるあたりに開業した「へちま」は、理想を追いかける若者たちの英気を養う場所となっていたが、多くは貧乏学生でツケを踏み倒されることが多くて経営はうまくいかず、結局は店をたたむことになった。
大正7年、第一次世界大戦直後の物価騰貴や米騒動を直接の動機として、庶民の食生活難を排除し、社会不安を緩和するために「公益食堂」は誕生。大正12年9月1日に起こった関東大震災もあって、ますます「公益食堂」の必要性が強まったことで、大正13年九段食堂、そして昭和7年4月開設の深川食堂まで、都内16か所にできた。
大正末から昭和の初めには、貧乏な都市生活者が膨張し、昭和2年には、「大衆」が流行語になった。昭和13年に東京府料理飲食業組合大衆食堂部がきるまでのあいだに「大衆食堂」という単語ができたと思われるが、実際に「大衆食堂」が盛り上がったのは、戦後昭和30年代以降である。
昭和12年から始まった日中戦争が本格化し、節約ムードの中、食堂の米飯使用禁止となる。真珠湾攻撃の年の昭和16年4月1日、ついに六大都市で米は配給通帳制になり、5月東京府料理飲食業組合大衆食堂部は外食券食堂部になり、「外食券食堂」が広まる。

第二次世界大戦の最中、絶対的な食糧難だったこの時代、国は国民に食糧と交換できる「米穀配給通帳」を発行し、これがないと食料を手に入れることができないよう、食糧統制を行った。外食券も同じく、当時の食糧難に端を発する。昭和16年春から、この配給制度と同時に「外食券制」という制度が敷かれ、家で食事をしない人を対象に外食券として発行した。闇市という言葉が出てきたのもこの頃で、市民は自分で穀物や野菜を栽培したり、動物や魚を獲ったり、そして闇市で仕入れたり。配給に頼らない食糧確保の手段を、皆こっそりと心得ていた。
戦後になると外食券が高値で取引されたり、闇市では外食券がなくても雑炊を供する「雑炊食堂」ができたり、徐々に物資供給が安定するようになったりと、外食券の必要が徐々になくなったことで、昭和26年に外食券制度が廃止に。この時の外食券食堂が、都に指定されて「民生食堂」となる。昭和30年に、米飯販売の統制がなくなると本格的な「民生食堂」の時代となった。
昭和39年(1964年)東京オリンピックによって東京が大きく変貌を遂げ、大衆食堂の環境もかわったし、大衆の意識もかわった。だが、戦後に成長した大衆食堂は、東京オリンピック後の都市の変化には乗らなかった。大衆が新しい暮らしを求め生活スタイルをどんどん変えていったけれども、大衆食堂はそれを追わなかった。家族の「なりわい」であり、そして地域に密着したものだったから、新しいスタイルには合わせなかった。その結果、昭和30年代の「たたずまい」をとどめている「大衆食堂」がこうして現在に残されたのだろう。

そして平成のトピックとしては、「子ども食堂」。これは、地域の大人が子どもに無料や安価で食事を提供する、民間発の取り組みである。貧困家庭や孤食の子どもに食事を提供し、安心して過ごせる場所として始まった。そうした活動は古くからあるが、「子ども食堂」という名前が使われ始めたのは2012年。最近は、地域のすべての子どもや親、地域の大人など、対象を限定しない食堂が増えている。食堂という形を取らず、子どもが放課後に自宅以外で過ごす居場所の中で食事を出しているところもある。子ども食堂という名前がつくほどフィーチャーされ始めたのは、格差の拡大のせいではないだろうか。
「食堂」は、時代によって変化しながら、現在まで続いてきたことがわかる。決して贅沢品ではなく、日常で食べていたものが、その時にできる方法で提供される。そしていつの時代も人々の交流の場となっていた。今も昔も変わらず、私たちの生活に寄り添ってくれる。
illustration:TWEAK @tweak_76
text/edit:Shoko Mimbuta