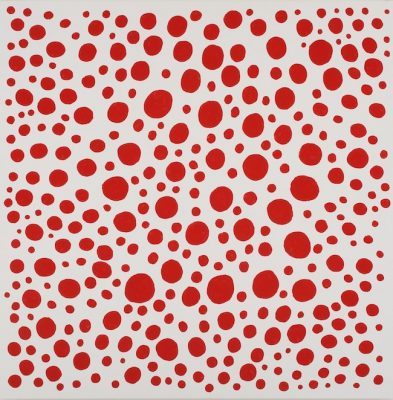2017年11月、東京都庭園美術館を舞台にして開催されたwrittenafterwards 2018SSのショーは「After Wars」というテーマのもと、戦争という歴史に向き合うと同時に、いまの不穏な空気や危機感を鮮やかに切り取った衝撃的な内容だった。社会情勢や政治と隔たったファッション表現が多い日本において、真正面から自身の現状認識を発信した山縣良和の背中を押したのは何か。考えること、創造することの重要性とはーー。
ーー今回のショーは、個人的に感じていた現状の気持ち悪さに対しても考えさせられるものがありましたし、壮大なテーマでありながらファッションとしても美しく着られるものであるという見事な落とし込み方にも本当に感動しました。前シーズンの “flower”からの流れや、どういったところからスタートしてあの形になったのか聞かせてください。
山縣「そもそもは日本の戦前、戦中、戦後と向き合ってやってみようと思ったところが始まりで、一年半くらい前から激動の時代を生きる人々をテーマにした、“flowers”というコレクションのタイトルで服作りをしていました。“flowers”のイメージソースのひとつはオバマ前大統領が広島訪問した時の献花なのですが、広島に来られるまで70年以上かかったんですよね。そこに考えさせられるものがあって、ファッションという媒体でそういうことに触れてみようと思ったんです。“flowers”では戦後にそこまでフォーカスしていなかったんですが、最終的には戦後をテーマにショーをやってみようという気持ちはあったので、そこにどう着地していくかを考え続けた1年間でした。最終的にブランド名のwrittenafterwardsとかけて”After Wars”というタイトルにしたのですが、戦後の表現は非常に難しい。アートフィールドの中でもそこは一番難易度の高いところですし、下手したら上っ面になりかねない。そこが自分の中の大きなハードルでした。でもいまやるべきテーマだと思ったんです。時代がぐるっと回って、いま不穏な空気があるじゃないですか。多分、僕もそれを感じていて、なんか怪しいなと。どんどん戦争のことは忘れ去られていくし、僕らも直接は知らない。そんななか、EU離脱、トランプ大統領、北朝鮮、日本もそうだし、いろんなところで世界が独裁色的になっている。この空気は、ちょっとまずいんじゃないかと。そういう時代感もこのテーマに向き合うきっかけになっていると思います」





——具体的なリサーチなどのプロセスはどのように進めていかれたのでしょうか。
山縣「僕の作り方というのはなんとなくテーマを決めて、色々情報を集めながら最終的な構成を考えていくもので、映画などを作る感覚に近いんです。“flowers”は、僕のルーツにも関係しているんですが、そもそも僕のルーツは鳥取と長崎なんです。父親から『長崎で祖母は原爆を見た記憶があるらしい』と聞いて、自分と戦争や原爆というものが全く遠い存在ではなかったのだなと。そこからリサーチするなかで石内都さんの本「ヒロシマ」を見ましたが、僕にはこのストレートな表現は出来ないなと思って、戦後の僕らの世代にとっての象徴的なヴィジュアルを何か作れないかと考えました。そこで、濱田祐史さんがやっているC/M/Y(シアン/マゼンタ/イエロー)という作品があって、写真を水に入れると一枚一枚水に溶解していくというものなんですが、それで何か出来ないかと思って作ったのがこのヴィジュアルです(*1)。これはポラロイド社のある機種でプリントアウトさせて出来上がったものなんですが、ちょっと玩具っぽいし、フェイクっぽくもありますよね。水に溶解、メルトさせていくなかでイメージがグジャグジャになるという行程もいま現在を表しているのかなと。福島原発事故によって“メルトダウン”といった言葉も身近になっていますが、とても深刻な出来事であるはずなのにいまの東京の日常ではどこか現実感がないといったような感覚も含まれていたり。おどろおどろしさもあればポップさも嘘っぽさもあって、いまの僕らの世界ってそういうものなんじゃないかと」
ーーそうしてイメージの原型を掴まれた後、実際に長崎に足を運ばれたそうですね。
山縣「はい。久しぶりに去年の春に祖母に会いに長崎に行き、色々と見て来ました。爆撃地も再訪したのですが、高校生が千羽鶴が添えてある慰霊碑の前で黙祷している風景を目にしました。直接戦争を知らない僕らが語るうえで、むしろ戦後のこういった風景の方がリアリティがある。この戦後の光景をそのままファッションショーで再現をして、戦争から今へ続く地続きのものを表現しようと。それが“After Wars”の原型となりました。カラフルな千羽鶴のルックや献花という、様々な色のある光景です。具体的な色のインスピレーションとしては、長崎に行った時に長崎県立美術館で行われていたマリー・ローランサンの展覧会からです。パステル調の作品が印象的な女性アーティストで、戦争に人生を大きく左右された象徴的なアーティストです。実は彼女から大きく影響を受けたのが絵本作家のいわさきちひろさんなんです。いわさきちひろさんの絵は幼少期から実家の玄関に飾ってあり、毎日その絵を眺めいた、ぼくにとって特別な作家です。そうやって色々と歴史や記憶を辿りながらイメージを作っていきました」


——ショーでは、マイクを持ったジャーナリストたちに囲まれた女性という1ルック目から度肝を抜かれました。
山縣「ある日、報道ステーションを観ていたら、稲田朋美元防衛大臣が映っていて、周りにマイクを持った大勢の記者たちに囲まれていて、『稲田さんはもの凄いものを纏っているな』と思ったんです。それがちょうど今回の庭園美術館での『装飾は流転する(*2)』の展示のお話をいただいていたタイミングで、新しい装飾に対してアプローチするというのがひとつのお題でもあったので、『この記者たちを装飾として捉えてみるのはどうだろう』と思いついたんです。なので、登場の時の音楽も報道ステーションの曲を使用しました。”集団性の装い”というものは今回の僕の重要なお題のひとつです。学生服も元々は軍服がルーツであったり、日本人独特の集団性というものによって悲惨な戦争も生まれているし、面白いカルチャーも生まれている。そこに向き合ってみようと。日本人の集団性の文化のルーツとして日本の山があると思ったので、山をそのままルックとして表現しました。そして脱ぎ捨てられた着物の山のルックも作りました。日本人は着物を脱ぎ捨てて、洋服へと移行した歴史を持っていますし、それに加えて関東大震災や東京大空襲で着物を来ていた方が、洋服を着ている人に比べて逃げ遅れて亡くなってしまったという話があるので、燃えて焼け焦げた着物で表現しました」
ーー谷川俊太郎さんの詩も鮮烈でした。
山縣「『十二の問いかけ』(*3)は、谷川俊太郎さんに僕が考えていること、今までやってきたこと、これから表現したいものを見ていただき、詩を書いていただいたものです。谷川さんは、『鉄腕アトム』のあの有名な、戦後を代表するテーマソングの歌詞を書かれた方なんです。アトム、ウランの原子力を平和利用する形で物語が描かれた漫画です。しかし僕達の時代は福島原発事故を経験しました。70年前の“戦後”と現在の“戦後”は環境も価値観も大きく変化しました。谷川さんの詩には根源的な様々な問いと共に、平和へのメッセージも『十二の問いかけ』には織り込まれています。美術館の入り口には広島に捧げらてた献花をモチーフにした衣装を配置し、最後に“あとがき”として谷川さんの詩で締めくくらせていただきました。
今回のファッションショーで表現したかったのは平和へのメッセージはもちろん前提としてありますが、特定の政治的な思想の表現というわけではなく、どちらかといえば歴史と現状を客観視した表現です。その客観的に見えたものを背伸びせず、ストレートにただ表現することに気をつけました」
——現状を客観視することは内面で済むことではあるけれど、外に出してそこにリアクションが返ってくるわけですよね。山縣さんはリアクションを求めていたのでしょうか。それとも昇華させるために行ったんでしょうか。
山縣「何かしらを感じてもらいたいというのはあります。ファッションは色々な側面があるのですが、ファッションだから表現できることもあるし、伝わることもある。あとは、身近にあるものだけど、集団性の危うさが戦争に繋がっていったように、ファッションにも実はそういった表裏があるということも表現したかった。日本でもドイツでもファシズムによるファッションの利用というものはあって、ヒトラーは元々アートを学んでいて、デザインの力を知っていた人なので、デザインによって人を惹きつける力というものを作りましたよね。日本も着物にプロパガンダ的なメッセージを織り込んだり。集団性の表現の面白さは日本の文化の中の根底にあるのですが、一歩間違うと危険な表現にもなりえる」
ーー戦後というのは今もそうですし、集団性も当たり前のように日常にある。あのショーを遠いように感じた方もいらしたかもしれないけど、おっしゃるようにとても身近なテーマであって。
山縣「そうですね。だからこそ、日常に正直にならないと無理なテーマだったなと思います。そしてレイヤーがひとつでも欠けていたら、曇ってしまって何も見えない。そういう切迫感もありました」
——山縣さんはここのがっこうも運営されていますが、そういう思考的な部分も教えているんですか?
山縣「自然とそうなりがちではありますが、特定の思想を賛美したり、一方的な何かを伝えるということはできる限り避けるべきだと思っています。伝えるべきは、歴史の複雑性であって、色々な価値観があるんだよといった世界観ですね。一般のファッション教育の現場では思考ではなく、もっと洋裁の専門的なテクニックを教える。なぜその技術を学ぶ環境が生まれたのかという背景や結びつきを考えるきっかけががあまりないので、その部分を補完できたらと思っています」
——社会との関連性を考えることは自分の身を助けることになる気がします。
山縣「サバイヴの仕方がわかりますよね」




——社会との関連もそうですが、山縣さんが掲げているテーマにはいつも平和への願いがある気がしていて。2013SSの七服神も2015 AWの「Heal the Worlds」も、そういうことですよね。
山縣「社会に関連づけして考えるのは、親の影響もあると思います。祖父は教師、親はリベラルで、仕事から帰ってくるとよく現状の政治に納得いかないとブツブツ言っていたのを思い出します(笑)。話しかけてくるわけでもないし、強要するわけでもない。あまり直接話した記憶はないけれど、なんだかんだ影響は受けているのかもしれません。今話していて、いきなり自分がここでファッションをやるなんて家系的には脈絡がないと思っていたんですが、クリエイティヴの世界もインディペンデントであることや既存のシステムへの疑問、自由な表現という風に見えたからだったのかもしれないと思いました。学校をやっているというのも、祖父の存在があったりと、結局のところルーツと繋がっているなと思いますね」
——小さい頃から社会を俯瞰的に見ていた節はありましたか?
山縣「社会、歴史が好きでしたし、インスピレーションを受けていました。例えば大学1年生のときに9.11が起きたんですけれど、当時僕はロンドンにいて。アメリカ大使館にバリケードが立っていて、その場所で写真を撮って作品にしたり。あとになって社会に対しての考察というのはセントラルマーチンズの伝統芸能のようなもので、セックス・ピストルズのファーストギグがセントラルマーチンズで行われていたり、そういう影響もあってジョン・ガリアーノが入学したという歴史があります」
——ルーツというのはクリエイティヴにどうしても影響してきますよね。
山縣「コンプレックスや嫌だなと思うことから逃げようとしているということは、結局そこになにか感情を置いて来ているんですよね。離れれば離れるほど、なぜ離れる力が生まれて来たかというところに帰っていきます」


——なるほど。”考える力”はどうしたら身につくと思いますか?
山縣「僕は考えざるをえなかったんだと思います。コンプレックスの塊で、自分自身が嫌だったし周りにもバカにされていた。でもそれに対して諦めなかったというか、自分で自分に駄目なレッテルを貼りたくなかったんですよね。人にバカにされないところはなんだろうともがいていたし、それを見つけたいなと強く思っていました。それでロンドンに行ったりして、そしたらさらに自分自身について考えざるをえない環境がそこに待っていて。他の国の人から見たら『なんでお前はこういうものを作るんだ?』となるので、『なんでだろう?』と考えざるをえないんです。自分のルーツがあからさまに出てくる環境でした」
——周りに言われても自分にレッテルを貼らないというのは随分大きいことだったと思うんですが、それはどうやってできたんでしょう?
山縣「『貼るべきではない』といった思想があったのかもしれませんね。親の思想の影響もあったのかな。子供時代からうっすらと、差別は駄目だとか人の権利は大切にという思想はあったんです。だから自分で自分のことを差別するべきじゃないと思っていて。自分までが自分のことを最悪と言ったり、レッテル貼るなんて、それをやったらおしまいじゃないですか。歴史を見ても差別やレッテルを貼ってもろくなことになっていない。そのうえに僕は、先生がいわゆる道徳的な話をすると『僕が先生だったらどんな話をするだろう?』と考えるのが子供時代からの癖でしたから」

——最後に、今後の展開を教えてください。
山縣「今回のショーと展覧会は全力で向き合ったので、良くも悪くもこれが今の自分の実力だと素直に捉えることができ、今後の課題にも多く向き合うきっかけとなりました。僕の課題というのは、ファッションの表現を拡大し過ぎていて、繊細な表現ができていないところだと思うんです。この10年で、あれもこれもファッションなんじゃないかとグイグイ拡げていったのですが、拡げれば拡げるだけチームとしても強くしなければいけないし、僕の経験値も上げなければ収集がつかない。だからこそ、もっと核の部分を強くしていかなければならないと思っています」
——では、今後はもっと削ぎ落とした表現の追求をする可能性が高い。
山縣「はい。そういった時期もあっていいと思うし、今はかなり削ぎ落としていきたいという気持ちです。これまではヘルメットをかぶって、防護服を着てハンダゴテなんかで工作していたり、普通のファッションの制作現場じゃありえないようなことを沢山やっていて(笑)。僕はそういうのも好きですけれど、次のステップに挑戦していきたいです。そうしたらこれまでやってきたことも見え方が変わってくるかなとも思うんです。そういう意味で、もっとクラシックなことをやっていきたいですね」

(*1)

(*2)装飾は流転する 「今」と向き合う7つの方法
(*3)
「十二の問いかけ」 谷川俊太郎
どうしてコトバが欲しいのだろう?
柔らかな布の手触りだけで十分なのに
どうして服を着るのだろう?
誰もがvaginaやpenisを持っているのに
どうして色を塗るのだろう?
花々と小鳥に任せておけばいいのに
どうして形を創るのだろう?
自然は形の宝庫なのに
どうして文字を書くのだろう?
声がこんなに暖かいのに
どうして箱が要るのだろう?
見えないものは入れられないのに
どうしてなんでも飾るのだろう?
はじめはみんな生のままなのに
どうして平和が戦争を生むのだろう?
戦争は平和を生みはしないのに
どうして入道雲が湧くのだろう?
凍える冬の心の底から
どうして道しるべがあるのだろう?
迷わずに行くのは退屈なのに
どうして名前をつけるのだろう?
これそれどれあれ 大きな違いなどないのに
どうしてどうしてと問うのだろう?
世界は答えであふれているのに
山縣良和(writtenafterwards)
2005年セントラルセントマーチンズ美術学校卒業。在学中にジョン・ガリアーノのデザインアシスタントを務める。2007年writtenafterwards設立。2008年9月より東京コレクション参加。2009年オランダアーネムモードビエンナーレにてオープニングファッションショーを行う。2015年、LVMHプライズに日本人として初めてノミネート。またファッション表現の実験、学びの場として「ここのがっこう」を主宰。
http://www.writtenafterwards.com
http://www.coconogacco.com