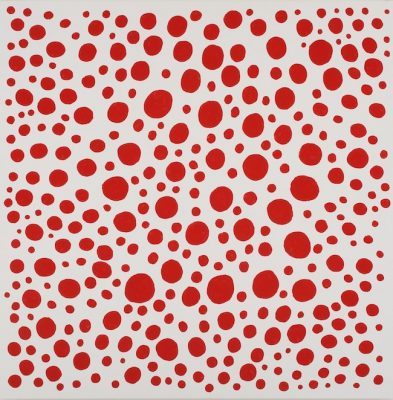韓国文学を読むとき、私はいつも数少ない自分の韓国体験を思い出す。
中学生の頃、授業の一環として海外研修旅行なるものがあった。なぜか半日間ロッテワールドから出ることを禁じられた私と級友は途中で飽き、ゲートで再入場のスタンプを押してもらい脱走した。とはいえビビってしまってそう遠くまでは行けない。結局、遊園地と隣接している蚕室駅ショッピングセンターで10,000ウォン(約1,000円)のセーターを買った。お店のおばさんは明らかに保護者のいない子供を訝しみながらも優しく対応してくれた。
高校生の頃、イギリス留学中の友人と長電話していると突然知らない男性が電話口に出て言った。「こいつは俺の彼女なんだ。あまり長い時間邪魔しないでくれる?」。彼は韓国から同じく留学に来ているクラスメイトだという。友人は彼氏が怒ってるから行くわ、と電話を切った。
大学時代、アルバイト先に韓国の男の子と交際している女の子がいた。勤務中にもしばしば電話がかかってきて、女の子は「うちの彼、嫉妬深いんです」と言って笑っていた。
大人になって、フランスに短期滞在する機会があり、私は語学学校に通った。クラスには韓国人の若い夫婦がいた。二人は料理人を目指す夫の修行のため、1歳になる娘とともに渡仏してきたらしい。娘はよく熱を出し、看病のために妻は頻繁に学校を休んだ。ある授業で、条件法を学ぶためのロールプレイングが行われた。私は占い師のキャラクターを演じ、妻はその顧客を演じた。
「先生、私の夫はキュイジニエとして出世するでしょうか。夫がお金持ちだったら、娘に良い教育を受けさせることができるんですが」。私は水晶玉に手を翳すふりをしながら答える。
「ええ、きっとポール・ボキューズよりも有名になりますよ。しかも、もしあなたが今から勉強すれば、あなたは夫よりも有名なパティシエールになるでしょう」
彼女は手を叩いて爆笑していた。内気な夫もはにかんで笑っていたし、クラスの全員がウケていた。その週末から小さな娘はまた風邪を引き、私が帰国する日まで若い母親は学校に来なかった。
・
これらは全て「個」の話だ。このたった4つの体験をもとに「韓国の男性は恋人を束縛する」とか、「韓国の女性は夫の収入をあてにしている」などと言うことは決してできない。できないが、同時に「個」だからといって全く取るに足らないケース・スタディだと切り捨ててしまうことだって、誰にもできないのではないか。
『82年生まれ、キム・ジヨン』(チョ・ナムジュ著)のAmazonレビューには、「単なる個の問題を一般化している」という批判が投稿された。一般とは何だろう。広く全体に共通して認められ、行き渡っていること。偶然起こったたったひとつの問題を、社会全体に共通する問題として語るなということだろうか。しかし、社会とは人間の集まりだ。人間とは個の集まりだ。2016年の「江南通り魔事件」の被害者となったのは「ひとりの」女性である。いつだって一般の問題は、個人の目の前で顕現する。
この「個」に寄り添う姿勢を、最近の韓国文学の中に見かけることが多いと私は感じている。『82年生まれ、キム・ジヨン』のタイトルロールであるキム・ジヨンは、物語の中では「例の」精神科医にしか見つけてもらえなかったが、彼女の存在は100万人の読者が知っている。知って「そうだったんだ、世の中にはこんなことがあるんだ」と衝撃を受けたり、「これは私の物語だ」と噛みしめたりすることで、私たちは100万の胸の中にいるジヨンを慰めることができる。
『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』(イ・ミンギョン著)では、「あなた」という個人が直面するであろう、日常の「個人的な」できごとへの対策が綴られる。そういえば、私が『日本のヤバい女の子』を書いた時、刊行イベントで「確かに色々な女の子たちの存在に勇気付けられたのですが、明日、会社で嫌なことがあったらどうしたらいいでしょうか」と聞いて下さった方がいた。今生きている一つずつの人生の、今直面している一つずつの問題にしか、救いは体現できないのだ。
『すべての、白いものたちの』(ハン・ガン著)や『悲しくてかっこいい人』(イ・ラン著)では、ごく個人的な体験をベースに、日々の心の動きや、大きな絶望や、愛おしい人生のディティールが書きとめられる。フィジカルなものを除けば、これこそが救いだと私は思う。この個人的な心の折り合いを、誰に向かって言うでもなく呟くこと。呟いたときに、誰もそれを否定しないこと。個人の力では立ち向かえない大きなものを前に、水際で繋がりあい、眺めあい、そっと寄り添いあい、何とか折り合いをつけていく。「すべての、白いものたち」をずっと胸に留め、「悲しくてかっこいい人」になり、「黙らない」ことは全て、キム・ジヨン氏を救うことになる。
・
では、個人の力では立ち向かえない大きなものとは何だろう。
韓国フェミニズムを社会構造抜きに語ることはできない。例えば、必ず儒教の一部がごく深い地中に染み渡り、新しく生える木々に水分を与えている。例えば、ミソジニーが現れるとき、兵役の話題が持ち出されないことはほとんどない。構造がベルトコンベアを動かし、毎日の「個」の現象を供給している。構造がAにBを守る代わりに、Bを好きにしていいという。Bは好きにされる道理はないし、守ってもらうという構造は自分が作ったものではないという。Aは知らないうちに決められた義務は守らなければならないのに、何も好きにできないことに憤慨し、損していると感じる。構造は何ひとつ損しない。
話は変わるが、2019年2月、日本の自衛官募集のポスターにメディアミックス作品『ストライクウィッチーズ』(島田フミカネおよびProjekt Kagonish原作・角川書店企画) のキャラクターが使われ、批判された騒動は記憶に新しいだろう。
3月のある日、私がなんとなくテレビをつけると、民間放送のバラエティ番組でその騒動について言及しているところだった。フリップボードでざっくりと経緯を説明した後、数人のお笑い芸人の男性が、女性アナウンサーに問いかける。
「○○ちゃんはどう思う?このポスター、反対派?賛成派?」
「うーん…私がこういう格好をしろって言われたらイヤですけど、彼女たちが好きでしているならいいと思います」
答えた瞬間、スタジオは笑いに包まれた。
「誰がアンタにこんな格好しろ言うてん」
「誰も言うてへん、言うてへん」
「せんでええ、せんでええ」
「てか漫画のキャラの気持ち、慮りすぎちゃう?」
録画していたわけではない。メモしか残っていないので、細かな言葉遣いは違っているかもしれない。ただ、この笑いに対する静かなる抵抗が「水際で繋がりあい、眺めあい、そっと寄り添いあい、何とか折り合いをつけていくこと」ではないかと、私は勝手に考えている。
直接「こんな格好をしろ」と言われなくても、私たち、「こんな格好をする可能性がある性」として見られていたんだよね。「お前はこんな格好をする可能性がある性だが、お前の造形はこんな格好をするには耐えない」とジャッジされることがありえたんだよね。たった今この瞬間には誰も笑っていなくても、私たち、微かだということになっている違和感を共有することができるよね。
この日本の女性アナウンサーが韓国文学の中に登場したとすれば、こんな風に受け入れてもらうことができたかもしれない。「今はそれは関係ないでしょ」と切り捨てられなかったかもしれない。「で、どうしてほしいの?」と問い詰められなかったかもしれない。ああ、そうだったんだね、そんなことがあったんだ。私はね…。
「私はね」で始まる話というものは単なる個人の見解であり、全く一般的な話ではないのだろう。それなら、私はもっとたくさんの「個」の話を聞きたい。無限に聞きたい。無限に集まった個人的な話こそが社会だ。彼女たちのごくパーソナルな物語を聞かせてもらい、ときどきは聞いてもらい、寄り添いあいたい。そうして少し心強くなりたい。大いなる構造が変わるその日まで、さしあたり生き延び続けていかなくてはならないのだから。
illustration & text Arisa Harada

はらだ有彩
『日本のヤバい女の子』
(柏書房)
購入はこちら
はらだ有彩 / Arisa Harada
テキストレーター(テキスト/テキスタイル/イラストレーション)。2014年から、テキストとイラストレーションをテキスタイルにして身につけるブランド《mon.you.moyo》を開始。これまでに、ウェブマガジン「アパートメント」「リノスタ」「She is」などにエッセイを寄稿。著書に『日本のヤバい女の子』(柏書房)がある。
http://arisaharada.com
https://twitter.com/hurry1116
https://www.instagram.com/arisa_harada/