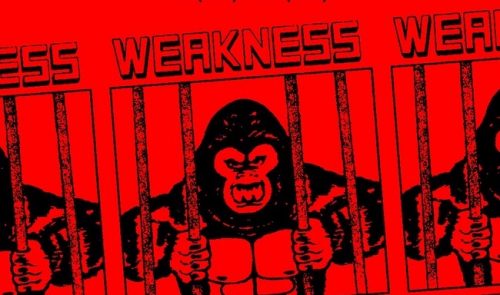オトナになるという境界線は、公的には”20歳(もうすぐ18歳に引き下げ)“となっているけれど、もちろんその年齢になったからといって突然に精神が成熟するというわけではない。なんなら、20歳を超えてもまだオトナになりきれていな人はたくさんいるようだ。じゃあ一体”オトナ”ってなんなのか。確固とした定義は難しいけれど、自分だけの換えのきかない毎日をしっかりと歩むことの延長線上に、自分なりの答えが見つかるかもしれない。
進路が少しずつ重きを増してきて、身体も気持ちも毎日少しずつ変化する14歳の頃、いま楽しく仕事したり生活している先輩たちはどんなことを考えて、どんなことをしていたんだろう。そんなファイルを作りたいと始まった「14歳」特集に、写真家の嶌村吉祥丸が登場。静かながらも凛とした佇まいや視野の広さや深さを感じさせる作品たちで誰にも似ない存在感を放つ彼は、どんな十代を過ごしたのか。
――吉祥丸さんはいつも仙人のように飄々としているイメージがあるんですけど、幼少期から14歳くらいまでどういう過ごし方をしてきたのかとても興味があります。
嶌村「幼稚園から小学校まで少林寺拳法をやっていました。サッカーも同時進行でやっていて。14歳はサッカー、塾、勉強に打ち込む毎日でしたね。いわゆる受験用の塾プラス英会話塾にも行っていて。当時も今も勉強は好きなんです。人間と関わる上でそれぞれのバックグラウンドを共有するための教養や知識みたいなものは重要なので、それを得られる勉強は大事だと思っていて。たとえ数学や物理という生活に必要のなさそうな分野でも、もしかして知っていたら人との共通項になるかもしれないじゃないですか。だから、そのころ勉強漬けでも意外と苦には思っていなかったです」
――勉強に対してのそのようなポジティヴなイメージを持てたきっかけは?
嶌村「父が“何のために勉強をするのか”ということをちゃんと僕に伝えてくれていたからだと思います。それに対して自分の中で納得がいっていたし、受験勉強もある種意味がないこととわかりながらも、それも含めて全てひっくるめた経験に意味があると捉えられていたんです。もちろん全てについて完全に納得いっていたわけではなかったですけどね」
――お父様からのお話は吉祥丸さんの視点を形成するにおいてすごく重要な部分だと思うので、もう少し詳しく聞かせてください。
嶌村「例えば”平均寿命に対していま自分がどこに立っているか””いまは〇〇区の学校では勉強何番だけどこれは世界基準で言えばどこにいるのか”など、そういうことを考えた方がいいと言われてグラフを描かされたりしていました。父は僕が小さかった頃には、紛争地域に行って地雷除去の活動をしたり色々な幅を見ていた人だから、そういう自分が見てきた幅を伝えてくれたのだと思います。母はNPOで子どもの抱えるあらゆる問題やDV問題に携わっていて、やはりちゃんと話をしてくれる人でした。二人ともいわゆる会社員ではなかったんです。14歳って学校と家庭が世界のほとんどですから、そこで幅を与えてもらえる家庭にいたという環境は大きいですよね。当時は嫌だなと思ったアドバイスも今思えば役に立っていますし」

――はやくに幅を知れたというのは良いですね。ちなみに当時はどんなことを考えて生活していましたか?
嶌村「わりと何も考えていなかった気がします。その都度目の前のことに集中して、という感じでしたから。何をしていたか記憶にない……」
――それくらい忙しい日々だったんですね。部活と勉強のバランスはどのように?
嶌村「部活が終わったら塾に行ってというルーティンにしてコントロールしていました。部活を引退してからは受験に向けて追い込みましたね。サッカーをやっていた時の集中力や体力を当時は勉強に、今は写真に変換させています。エネルギーの出し方や運動能力や脳の基礎体力は変換の仕方を変えるだけで色々なことに役立つと思います」
――当時は何になりたかったですか?
嶌村「半分疑問に思いながらサッカー選手になりたかった。でもいわゆる夢というものを確信をもって言えなかったから、なんとなく大学に行くんだろうなと思っていて。大学生は考える時間であり、今はその大学に入るための環境整備の時間だなと。そのためにも変なところでつまずかないように、どれだけいい環境に身をおけるかということを考えていました」
――そこまで俯瞰して考えられていたのは凄いですね。
嶌村「ひとりっ子だったからひとりで考えることが多くて。小学校低学年の頃のある日、通学路で”ソフトクリームが食べたい”と思ったことがあったんです。で、それと同時に”あのときソフトクリームが食べたいと思った”ということをこの先何年経っても思いだすだろうということを予感していると思った。今後この考えを何重にもレイヤーしていくだろうと。それで実際、思いだすたびに今何回目なんだろう、ということは自分はずっと同じ存在なのだろうとずっと考えていて……”〇〇だろう”のレイヤーが一個になっているなという考えですね。それを覚えています。幼い頃ってそういうこと考えていたはずなのに、自分の中でぐるぐるするだけで外に向かって吐き出すということをしないから忘れてしまうんでしょうね」

――確かにその頃考えていたことは哲学のような深さがあったかもしれないけど、忘れてしまいがちですね。写真家を志されたのはいつからですか?
嶌村「ここ最近ですね。ちょうど大学1年の終わりに祖父の家でカメラを見つけて撮り始めたんです。大学2年でポートランドに留学して、写真を撮っていく中での人とコミュニケーションが生まれることがおもしろくて。ここまでピンときたものは初めてでした。サッカーは友達がやっていたからから始めたものだったし、自分でやれるところまではやった。写真は自分が選んだものとしてちゃんと好きと思えるし、始めた当時に古着やファッションにもハマったので文脈がうまく繋がったんです。最初は写真を撮ることがお金に変わるなんてことは夢にも思っていなくて。撮っているだけで楽しいし、カメラを持っているだけでおもしろい人に出会えるということが自分にとってプラスだったのでそれだけで十分でした。徐々に仕事としてやれるようになったのですが、その前には写真を撮りまくると自分に課した1000本ノックみたいな時期がありました。大学に行きながら3カ月で100本程度撮影していて、そのおかげで撮影の基礎体力がついたと思います」
――写真家になりたい人は多いと思いますが、どこが”なれる”、”なれない”のポイントだと思いますか?
嶌村「みんな、写真家じゃないですか(笑)」
――写真で生活ができるというい意味での、です。
嶌村「僕は自分自身を写真家だと思っていませんが、第三者に対しての見せ方ですかね。日々の言動やプロジェクトが他人からどう見られているかという、ある種のブランディングもあると思います」
――色々なバランスを客観的にとるのはなかなか難しいと思いますが、効果的なブランディングはどのようにして作られるのでしょうか。
嶌村「僕の場合は、バランスを考えたうえでそのバランスを壊そうとしました。例えばファッションフォトグラファーを指す言葉として”ここの雑誌で撮っている人”や”誰々さんを撮っている人”で語られることは多いのですが、僕はそういうものを壊したくてティーン誌から文芸誌から、もちろんファッション、雑誌だけではなくあらゆるジャンルにおいて活動をしていました。流行りもジャンルも作りたくありませんでした。ある特定のところばかりにいると自分を消費することになるので、あえてイメージをばらけさせることが自分のイメージの回収に繋がると思って」
――そのロジックを実行できる人は稀だと思います。
嶌村「比較的短い期間の間でお仕事をいただける写真家になったのは、たぶん僕よりも写真が上手い人がいる中で、僕と過ごしている時間を相手にとって価値のあるものだったと思っていただけるように心がけていたからかもしれません。向こうの求めているものを踏まえた上で新たに提案することもやる。それが大前提として、プラスアルファ”吉祥丸といる時間は良いものだった”とできれば現場全員に思っていただけるようにする。もちろん、スタッフだけではなく例えばカフェを撮影場所に選んだとしたらカフェの店員さんにもそう思ってもらえるようにしたい。この間、僕が撮るときは被写体との間にやんわりと精神と時の部屋のような空間が生まれると言われて。自分では気づかなかったのですがおもしろいなと思いました」
――たしかに、嶌村さんの撮影は優しいシールドが生まれますよね。静かだけど強い。そこにも少林寺の影響を考えてしまう(笑)。
嶌村「(笑)。少林寺憲法は原始仏教に基づいた思想に近く、脱いだ履物はそろえる、礼儀を正して心を正す、といった当たり前のことを大事にしましょうという考え方を持っています。小学生までなので本格的な組手もやっていませんが、精神と身体を自覚することができたのはよかったかもしれません。今もフィジカルも鍛えたいし、それは大切だと思っています。僕は本をあまり読んでこなかったのですが、良い音楽を聴いたり、コンテンポラリーダンスを見て受ける衝撃がシンプルに自分にとっては自然で有機的だったりするんです。本を読んで新たに発見するというよりはフィジカルで自然と身につけていた思想を改めてやっぱりそうだよなと確認するようなことが多いですね」
――そういう身につけ方だったんですね。てっきりたくさん本を読んでいると思ってました。
嶌村「実はあまり(笑)。昨日ちょうど友人と”2019年は本を読もう”と話したんですけれど、哲学書はたまに読んでいて、今はちょうど『神・死・時間』(エマニュエル・レヴィナス著)という本を買ったばかりです」
――最後に、14歳の人たちに知っていてほしいことがあれば教えてください。
嶌村「うーん、何だろうな。さみしい目線かもしれませんが、意外と誰もあなたのことを気にしていないよって伝えたいですね。逆に言えば何をしてもいい。14歳の時は限られたコミュニティのなかで守りに入って空気を読まなければならない風潮が強いと思うのですが、良い意味で誰も気にしていないんだから自由でいてほしいですね。でも、自由は責任が伴うことです。これは知り合いの受け売りですが、責任って英語でresponsibilityと書くじゃないですか。これは本来の自分自身に対してresponse(反応、応答)できていますか?ということだと思うんです。自分の真理に対して正直にいられるかということが自由と同時に付きまとう、ということを考えつつ、目の前のことを楽しむことも忘れずに。生きている心地や実感を持ってほしいです。例えばSNSのなかで自分の虚像を持っていてもそれは自分の一部ではありつつもそればかりで生きている心地がするかといえば、違うと思います。フィジカルなものでもなんでも熱中するものに真摯に向き合って、もっと生きている心地を感じてほしいです」
photography Kisshomaru Shimamura
text & edit Ryoko Kuwahara
嶌村吉祥丸
東京生まれ。ファッション誌、広告、カタログ、アーティスト写真など幅広く活動。主な個展に”Unusual Usual”(Portland, 2014)、”Inside Out”(Warsaw, 2016)、”about:blank”(Tokyo, 2018)など。 www.kisshomaru.com