猪野秀史による5年ぶりのアルバム『SONG ALBUM』。その名の通り、全曲を通して猪野がヴォーカルをとった今作は、ミニマルな音と“ことば”が奇妙にも美しく絡み合い、際立たせ合い不思議な中毒性を持つ。日々の生活を訥々と描きながら、“響き”となったときには自由に飛躍する、その卓越した歌詞を紡ぎ出したのは、猪野本人と彼が敬愛してやまない東京を代表するミュージシャンである小西康陽。コラボレーションの経緯から、それぞれの制作への向き合い方などを、二人のゆかりの場であるtenementで語らってもらった。
――この『SONG ALBUM』を聴いていたら、いきなり1曲目“スカイツリー”から歌がガツンと入ってきて、それがタイトル通りで凄く良いなと思いましたし、クレジットを見ないで聴いていて1曲目の歌詞が小西さんっぽいなと思っていたら本当にそうだったので驚きました。お二人で曲を作ろうとなったのはどういう経緯があったんですか?
INO「この曲ともう1曲、“東京上空3000フィート”は小西さんに書いていただきました。もともと小西さんの独自な世界観と歌詞が好きで、僕がやっているレーベル“innocent record”の名付け親でもあります。かれこれ15年くらいのお付き合いになるんですが、たまたま小西さんと夜中にお茶をしているときに『歌のアルバムを作っているんです』という話になって、自分で歌詞を書くのは初めてだったので色々と相談させていただいてた中で、『小西さんに歌詞を書いてもらえたら嬉しいです』とお話したら『喜んで』という流れで。それがきっかけですよね」
小西「そうですね」
――曲タイトルの“スカイツリー”はどちらのアイデアなんですか。INOさんは「僕は東京タワー派なのにスカイツリーを選ぶなんて!」とおっしゃっていましたが、どうしていきなりスカイツリーを持ってきたのでしょう?
小西「僕も東京タワー派だったんですけど、何年か前にレコーディングをしていて、スタジオのある駅からJRに乗って錦糸町で降りたんです。その時の、錦糸町の駅前から見えた夕方のスカイツリーがとても綺麗で。一発で惚れましたね。あの姿でファンになる人は多いんじゃないかな。そこで、『スカイツリーっていいもんだな』と思ったんですけど、またある時に神保町で映画を観て喫茶店に行こうと駿河台の交差点から小川町の方向に向いたときにスカイツリーが見えたんです。『神保町からもスカイツリーが見えるのか』という驚きがあって、そのことがずっと忘れられずにいて。今回INOさんから歌詞のお話をいただいた時に突然そのことが思い出されて、題材にしました」

――小西さんといえば、気持ちを直接は書かないけれど歩いて見える東京の風景を通して叙事的に気持ちが漂う歌詞という印象があります。以前はその舞台が東京タワーということが多かったけれど、今回でスカイツリーになったんですね。INOさんが今回歌もののアルバムにしようと決めたのはどんな思いからなんですか?
INO「デビューアルバムを出す前、20代の頃に60年代の音楽を偏愛したロックバンドを組んで鍵盤を弾きながらヴォーカルをやってました。最初に出したソロアルバムがたまたまインストだったので世間からはインストの人って認識をされてますが、自分はそう思っていなかったので10年ほど悶々としてましたね(笑)。ライヴではヴォーカル曲をやってましたが、作品として歌ものを作ってみたいという思いもあり、今回は満を持して自分のルーツに立ち返った作品が完成して本当に良かったです」
――確かに“cry me a river”や“プカプカ”など以前にもINOさんがリードヴォーカルを取っている曲を聴いて、INOさんの声が年を追うごとに前に出てきている印象はありました。小西さんはPizzicatoOneでの秀逸な配置しかり、キャスティングやヴォーカリストの選び方には凄く気をつかわれていると思いますが、ご自分で “歌ってみたい”という気持ちが盛り上がってきたことはなかったんですか?
小西「なかったですね。僕は歌を歌わないだけでなく、楽器も弾かないんです。ピアノも作曲するときだけ。僕の中で演奏したりパフォーマンスすることは音楽の第一ではない。僕にとって音楽で一番大切なことは“聴くこと”です。次は“作ること”。そう考えると、歌うことや演奏することはどんどん後ろの方へいってしまう。ただ、いままさに自分が歌ったレコードを作って聴いてみたいと思っています。ライヴがしたいわけではなく、ライヴ盤の自分の声というものが聴いてみたいんですね。まあ、思っているだけですけれど(笑)。そういえば、二週間ほど前に代官山でライヴをやったときには自分で歌ったのですが、INOさんにピアノを弾いてもらったんです」
INO「小西さんの“地球最後の日”という大名曲があって、当日、思い切り間違えたり、いろんな意味でノックアウトされてしまったんですよね(笑)」
小西「いや、間違え方が大胆でアッパレでしたよ! それは稲垣吾郎さんと草彅剛さんのために書いた曲で、映画『クソ野郎と美しき世界』のエンディングテーマだったんです」
INO「転調を繰り返す難しい曲ですね、ああいう転調のさせ方はどこから来ているんですか?」
小西「あれは簡単でしたよ。要するに文章の段落を区切るような感じで、ここでちょっと気持ちを切り替えたいとか人を惹きつけたいなというところで転調しているだけなんです。10回くらいパートを変えながら転調をして、結果的になぜか最後には元に戻っているんですけどそれも偶然でした」
INO「転調は最後に元に戻ると美しいですよね」
小西「そう。でも、あれは戻んなくてもいいやって思って作っていたんです(笑)」
INO「曲も素晴らしいけど歌詞もまた短編映画を観ているような、次を追いかけたくなる内容で面白いんです」
小西「児玉(裕一)監督がエンディングテーマなのに、『PizzicatoOneの“日曜日”みたいな曲がいい』とおっしゃって『えっ、本当にそれで良いんですか?』と(笑)」
INO「(笑)。本当に素敵な曲ですけど、ライヴはかなりスリリングでした」

――小西さんはヴォーカリストとしてのINOさんを見てどういったところを引き出したいですか?
INO「それは聞いたことないですね」
小西「難しい。というのは、今回のアルバムを聴いて改めてINOさんは自分で作る曲が一番合っていると思ったから。絶対INOさんは自分が作った曲が一番良いです」
INO「意外とそうでもないですよ(笑)」
――逆にプレイヤーとしてのINOさんの魅力は?
小西「聴いている音楽が近いですし、そういう意味で信頼できるんですよね。実は僕は歴代スタジオミュージシャンでお願いしているキーボードプレーヤーが何人も変わっているんですね。巧い人はいっぱいいるけれど自分に合う人はなかなかいなくて。でもINOさんは音楽のバックグラウンドが凄く近いから合うんです」
INO「とんでもないです」
小西「でも制作ということでいうと、僕は曲を作ったり仕上げるのがもの凄くはやくて、INOさんと時間の使い方がずいぶん違うんですよね」
INO「僕は自分でレーベルもやっているから良くも悪くも締め切りがないんです。今回のアルバムも5年ぶりですし。ただ、考えすぎたり時間をかけすぎても良いものは生まれないですね」
――それで言えば、アルバム2曲目“奇蹟のランデヴー”は1時間で完成されたとか。とても良い曲でした。
INO「小西さんからも言われたのですが、心がけているのは“一筆書き”ということですね。もっと感覚的に作ることができたらなあと思います」
小西「そうですね、僕はいつも“良い曲は一筆書き”と言っています。でも写真なんてもっと一瞬じゃない?」
INO「最初の1テイク目が一番良かったりしますし、写真も一緒なんでしょうね」
小西「言い換えると、凄い光景、決定的瞬間に遭ったときに見逃さない努力をフォトグラファーの方はしていらっしゃるんですよね。音楽の場合、浮かんだり降りてきたものを良いかどうか判断するには普段からセンスを磨いていないといけない。でもINOさんは時間をかけすぎ!(笑)」
INO「1年に1枚ペースで作れるように頑張らないと(笑)」
――ザ・ビートルズの時代は逆にリリースがはやすぎたという話はたびたび耳にしますが、あのスピード感はなんだったのでしょうね。技術が進歩している今の方がみんなどんどん時間をかけるようになっている。
小西「昔は基本的に一発撮りだったでしょう? 今は48チャンネルの時代も越えて何トラックでも使えるわけだから、できなくなってしまうのは当たり前ですよね」
INO「それだけ自由になって択肢が増えすぎると、むしろ面白くなくなるのかもしれないですね。僕はドラムのハイハットやキック、ベースも生じゃなくて1音1音アクセントや音符の長さを調整して全部自分で音を打ち込んでいるんですが、ProToolsといったDAWと呼ばれるソフトウェアを使って制作していないんですね。1990年代の昔ながらのハードディスクレコーダーを未だに使っているんですよ。自分としては一番スピーディに扱えるし性に合っているんです。でも今回は歌のアルバムだったので自分のヴォーカルのベストのキーを追求していく中で、全てのパートを録り終えて最後に歌を入れたら、『半音低い方がいいな』と思えてきたりして、最新のものだとそれがボタン一つでできてしまうんでしょうけど、僕のハードウェアは一からやり直さなくてはならなかった。でもそういうことを繰り返していく中でいろんな発見もあったので多分これからははやいと思います」
小西「へえ、ProToolsじゃないんですね」
INO「PCではあまり作りたくないんです。PCの画面を見ながら音楽をつくる気分になれないのと、アナログ的な人間味のある部分だったり未完成なデモ音源的なものに興味があるんですよ。そういうことを一人でやっていて、全て自分でやっちゃいすぎるのも良くないと思うんですけど、人に任せてしまうと気に入らない自分がいるのかな。その辺は悩みどころです」
小西「すると、何故に歌詞を僕に頼んだのか?という最初の疑問に戻るね(笑)」
INO「全部自分でやってしまうのも、こじんまりとしたものになって面白くないし、でも誰でもいいわけではなく、小西さんが良かった。自分が発想する範囲のことしか言わない人とはやる意味が無いし、とても自分では思いつかない言葉が小西さんから出てくるから、やっぱりそこがお願いした理由ですし、次回も機会があったらお願いします」
小西「ぜひ」
INO「あと、“スカイツリー”“東京上空3000フィート”は小西さんに詞先でいただいて取り掛かったんですが、その行為自体が僕にとって初めてだったので、最初はできるのか不安でしたが、作っていくうちに楽しくなってきて。できあがったものを聴いていただいたら、『予想以上でした』と言っていただいてよかった。今後は先に歌詞を書いて曲を後で付けてみるのもいいかなと気づかされました」
小西「僕は曲と詩が同時なんだよね。それが一番楽。あと、僕はタイトルが一番最初にくる」

――INOさんは細野晴臣さんや鈴木茂さんといった先輩方はじめ多くのミュージシャンの方々との関わりもあるけれど、今回はあえて客演をおさえたんですか。
INO「歌ものとしてスタートラインに立ったし、フィーチャリングやゲストを打ち出された音楽ビジネスのようなものに関心が持てない。でも、僕のスタートにはいつもなぜか小西さんが関わっていて、デビューアルバム『Satisfaction』も沢山アドバイスをいただいていましたし、不思議なご縁なんですよね」
小西「そもそもこの場所(Tenement)があった辺りは小学生の頃の通学路で、この前は毎日通っていましたから。何か縁があるのでしょうね」
INO「小西さんが一番最初にここに見えられた時のことをとてもよく覚えています。僕は妻と2人でこのお店を始めたんだけど、開店して間もない頃にマッシュルームヘアの人がふらっと店の前を通りかかって『あ、小西康陽だ!』って妻が飛び出して話しかけたんです。それから1ヶ月ほど経った夜に突然来てくださって、お茶をされている間、ずっと小西さんの好きそうなレコードをかけ続けていました。すると『ここでイベントをやりたい』と声をかけてくださったのが最初の出会い。そこから2,3年ほどの間、月1ペースでDJイベントをやっていただいて、凄く楽しかったし勉強になった。当時僕はまだミュージシャンでもなくただの店員で、それから3年ほど経ってレコードを出すことになった時に、小西さんに聴いていただいて。だから、僕のことも最初に小西さんが見つけてくださったんですよね」
小西「そう考えると、当時もらったデモテープとINOさんの新譜は全然変わってないね。繋がっているし、一貫している」
――それはアーティストとしての芯があるからですよね。PizzicatoOneのアルバムを聴いても、ピチカート・ファイヴの音が蘇ってきますし。
小西「そういうの、あるよね。やっぱりデビュー作に全てが詰まっているんだと思います」
INO「人は変わっていってるようで実は変わらないものですよね。そんな中でどんどん一筆書きができるようになっていくというのが成長なんでしょう。そういった意味でもデビュー作には大切な何かが詰まっているのがわかりますね」
小西「デビュー作や初期の作品を封印しちゃう人もいるよね。『習作だった』と言って。あれはズルい気もするなあ。でも、その気持ちもわかる(笑)。僕も80年代に作ったものは一切聴きたくないと思っていたときがあるもん。昔の自分の写真を見ても『なんでこんなズボンを履いてるんだろう』というときがあるよね(笑)」
INO「恥ずかしいもんですよね(笑)」
photography Satomi Yamauchi
interview Shoichi Kajino
text & edit Ryoko Kuwahara
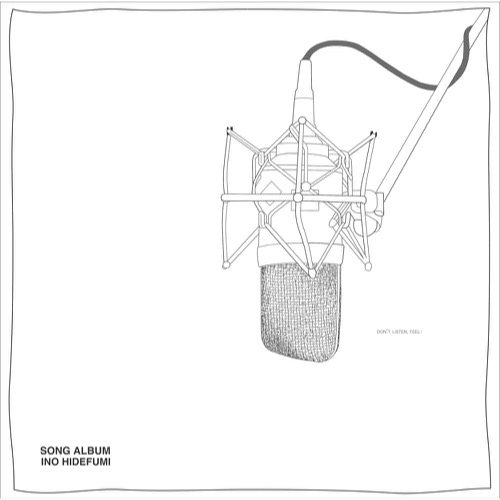
猪野秀史
『SONG ALBUM』
Now On Sale
(innocent record)
https://www.innocentrecord.net
INO HIDEFUMI SONG ALBUM LIVE PERFORMANCE TOUR 2019
老舗ライブハウスを中心に、最新バンドセットで巡るツアー。東京 B.Y.Gを皮切りに京都磔磔、金沢、名古屋、九州など全9公演を予定。詳細は順次オフィシャルHP、SNSにて発表!

『いま見ているのが夢なら止めろ、止めて写真に撮れ/小西康陽責任編集・大映映画スチール写真集』
Now On Sale
(DU BOOKS)
B5変型(横長)/上製/248頁
http://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK222
小西康陽
音楽家。1985年にピチカート・ファイヴでデビュー。 世界各国で高い評価を集め、1990年代のムーブメント「渋谷系」を代表する 1 人となった。 解散後のソロ作品に『11 のとても悲しい歌』『わたくしの二十世紀』。 著書に『東京の合唱』『ぼくは散歩と雑学が好きだった。』、片岡義男との共著『僕らのヒットパレード』他。
1997年『黒い十人の女』のリバイバル上映を企画し、旧来の映画ファンだけでなく、 邦画を見慣れない若者も熱狂させ、大ヒットを記録した。年間 500本以上の映画を劇場で観るほどの映画好きでもある。
猪野秀史
宮崎県延岡市生まれ。鍵盤奏者、シンガーソングライター、アレンジャー。フェンダーローズをメインに据え60年〜70年代の音、アーバンブルース、昭和の歌謡曲、音響的ロック、ソウルミュージック、エレクトロニックファンク、古い映画音楽など様々な要素を取り入れた独自の世界観が特徴。5歳でピアノを習い始め、後にクラシックの教育を受ける。2002年、行き届いたクオリティコントロールの実現のため1レーベル1アーティストをコンセプトに「イノセントレコード」を立ち上げ、レコード会社にもプロダクションにも所属せず完全インディペンデントで活動。7インチレコードにこだわった7インチシリーズ11作をはじめ自身の作品をDIY精神で大衆へ発信。2006年リリースの1st.アルバム「Satisfaction」がスマッシュヒット、店頭での試聴や口コミなどで全国に広がりオリコン18週連続チャートイン、海外のメディアからも高い評価を獲得。演奏からプログラミング、ミックスダウン、アートワークまでをひとりでこなし様々なミュージシャンとの共演、作品にも参加。自身のプロデュースするINO BANDではワンマンツアーをはじめ、フジロックなどの音楽フェスやイヴェントにも出演。2018年10月発表の新作「SONG ALBUM」には細野晴臣、小西康陽、鈴木茂、林立夫、常磐響、沖祐市、ハマ・オカモト、馬場正道らがコメントを寄稿。ミニマルに削ぎ落とされたシュールな音とことばの世界、まっすぐに乾いた声で歌い上げる独自のグルーヴと浮遊感で幅広い層の心を揺らしながら浸透中。






























