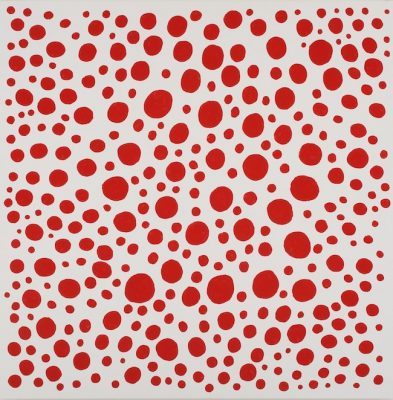フランスを代表する作家のひとりであるマルグリット・デュラスによる自伝的小説『苦悩』。ナチス占領下のパリで、レジスタンス運動のメンバーである夫を逮捕された作家のマルグリットが、その長く終わることのないかのような不在に心身ともにおかされていく壮大な愛の物語だ。この作品に心酔するジャン・リュック=ゴダールの弟子であるエマニュエル・フィンケル監督がメラニー・ティエリーを主演に据えての映画化を果たし、フランスをはじめとするヨーロッパで大きな話題を呼んでいる。ブノワ・マジメル、バンジャマン・ビオレら名優と堂々と渡り合い、難しい役どころを圧倒的な演技力で魅せたメラニーに話を聞いた。
――マルグリット・デュラスの名作がどのように映画化されるのかと思っていたのですが、古典的な風格を備えた、フランスらしい作品に仕上がっていて、それを支えていたのがあなたの演技でした。大げさなアクションよりも微細な表情の変化や仕草をとらえるようなクローズアップが非常に多いカメラワークだったのは女優にとっては大きなチャレンジだったと思います。さらに日記を読むという行為(ナレーション)も印象的で、その発音や息づかいも繊細にとらえられていました。監督はこれらの演出をどのように行い、あなたはどのように会得していったのでしょう。
メラニー「監督と演者の関係はダンスのパートナーのようなもので、ベストな相手に出会いさえすればあとはとてもスムースなもの。彼は私にとってまさに最高の相手でした。これほどに全ての物事がシンプルでやりやすくなる相手と出会えるのは稀ですが、私たちは直感的にお互いのことが理解し合えるのです。もちろんより注意すべき点や修正点などは撮影中に出てきますが、意思疎通ができているのでそれも全く問題なく進みました。監督にとって一番大変な部分は、自分が思い描く像にぴったりくる役者を選ぶことでしょうけれど、彼は時間をかけて私を選んでくれました。一旦その決断を下したからには、私を通じて思い描いたものを語らせるという以外の選択肢がないので、他の人が演じていたらこうだったかもしれないという“もし”は葬り去って全信頼を置いてくれました。二人の関係は錬金術のようで、一緒にクリエイションをしていくという感じでした」

――監督は『苦悩』に大変深い思い入れがあり、20歳のときに初めて読み、さらに30年後に再読しての映画化ということで、おそらくマルグリットの人物像を完璧に描いていたと思います。あなたは原作を読んで彼女にどういう印象を抱きましたか。また、どうやって互いの人物像のすり合わせを行なったか教えてください。
メラニー「私が『苦悩』を知ったのはドミニク・ブランという女優の方の朗読劇です。その朗読劇と本作で異なるのは、朗読劇ではのちにマルグリットが日記を読みながら回想しているという作りで、映画では現在を生きているマルグリットを描いているところです。この文献は素晴らしい内容で、いち個人の内面が勇敢かつ親密に描かれています。演じるに当たって難しかったこととしては、デュラスはオフィシャルには当時の日記のままで手直しをしていないということでしたが、彼女は複雑で人で、嘘つきであることもみんながよく知っていますよね。だから読んでみると、明らかに後に名を馳せたあのデュラスの文体が如実に表れていて、明らかに30歳では書いていないだろうと感じられるのです。彼女はタッチしていないというけれど、後の彼女が書き直した部分があると。しかし映画は現在形で描かれているので、若かった彼女の当時の生き生きとした感じを表現しなくてはいけない。その統合を図るのが一番難しかった点です。彼女の一番最初の文献『ラヴィー』を読めば、明らかに名を馳せてない頃の文体はその後と違うので、絶対手直しはしていると思うんです(笑)」

――現在形のマルグリットであるという点で、作品には自然光の鮮やかさが多く用いられているのでしょうか。1944年という時代設定としてはモノクロームであってもおかしくないのですが、現在形を意識しての光や色の用い方だったのかなとお話を聞いていて思いました。
メラニー「技術的なことは監督ではないので申し上げられないのですが、監督は少人数で撮影するスタイルで、機械を手でもって動かしたり、照明を調整したりというようなスタッフたちがいません。パリのロケでも、4時間もかけてセッティングして照明を調整してということがなく、即座に本質を撮るということで、カメラがあって監督がいて女優がいさえすればいいのです。本質をそのまま撮るということが重要だったので、作り込まれた照明ではなく、自然光であのように撮られていたのだと思います。監督が非常にこだわっていて、正しかったと思うのが、当時のパリの壁は黒っぽくてそれが重厚感を与えていたので、映画でもそう見せるための工夫がなされているところです。いまは洗われて綺麗になっているので、後から黒く見せる編集するのかと聞いたら、撮る前から少し壁を黒っぽく撮る方法があるそうで、その手法を用いてパリの重厚感を出しています」
――なるほど。先ほどあなたが言ったように、デュラスは非常に複雑な人物です。もしかしたらその後からの書き直しが影響しているのかもしれませんが、日記も書く(エクリチュール)と語る(バロール)の複合になっていると思います。あなたはそのどちらを重要視されましたか?
メラニー「演じるにあたっては、内面からこの役を生きるということに重点を置きました。彼女は生きている肉体であり、混乱をしているけれども、どこか引いて自分の思考を巡らせていくという部分があります。作家ではあるけれども、まだ若く青いがゆえに客観的になりきれてはいない。生きていく上では食べ物が必要なように、書くにあたっても養分となる経験が必要なので、欲望や不安をどこか客観視しながら書いているのです。私は現在を生きているマルグリットを演じると同時に、それを要素としながら何か書いていこうとするマルグリットという二つに注意しながら演じました」
――最後に、エマニュエル監督もまさにそうですが、あなたが仕事をしてきた監督はチャレンジングな人ばかりです。そういう監督を選び、サポートしながらアートを作ってきた理由とは。
メラニー「自分が映画館で観たいと思う作品、好きでご一緒したいという監督と仕事をするというシンプルなスタンスで臨んでいます。私のことを知ってくれていたのかという監督から声をかけていただく幸運にも恵まれて、テリー・ギリアムやスペインのフェルナンド・レオン・デ・アラノアの作品で少しは名を知られたかもしれません。そうした、自分がその役を通してどういう人間なのかを観てもらえるような作品には挑戦していくようにしていますし、これからもそうしていくと思います」

photo Sachiko Saito
text Ryoko Kuwahara
『あなたはまだ帰ってこない』
2019年2月22日(金)より、Bunkamuraル・シネマほか全国順次公開
公式HP: hark3.com/anatawamada/
1944 年、ナチス占領下のフランス。若く優秀な作家マルグリット(メラニー・ティエリー)は、夫のロベール・アンテルム(エマニュエル・ブルデュー)とともにレジスタンス運動のメンバーとして活動していた。ある日、夫がゲシュタポに逮捕される。マルグリットは夫を取り戻すためにゲシュタポの手先のラビエ(ブノワ・マジメル)の力を借り、恐ろしい危険に身を投じることを決意する。愛する夫の長く耐え難い不在はパリの解放後も続き、心も体もボロボロになりながら帰りを待つマルグリットだったがーー。
監督・脚本: エマニュエル・フィンケル
出演: メラニー・ティエリー『ザ・ダンサー』『海の上のピアニスト』、ブノワ・マジメル『ピアニスト』、バンジャマン・ビオレ『パーソナル・ショッパー』 グレゴワール・ルプランス=ランゲ 『キリマンジャロの雪』、エマニュエル・ブルデュー
原作:マルグリット・デュラス「苦悩」 原題:La Douleur 2017 年/フランス・ベルギー・スイス/フランス語/126 分/ビスタ 配給:ハーク
メラニー・ティエリー
1981年サン=ジェルマン=アン=レー生まれ。子供時代からモデルとして活躍し、1999年に『海の上のピアニスト』で映画デビュー。同年に公開された『カジモド』で名を知られるようになり、2008年にはハリウッド映画『バビロン A.D.』、イギリスのTVドラマ『ホロウ・クラウン/嘆きの王冠』に出演。2010年の”Le Dernier pour la route”でセザール賞有望若手女優賞を獲得し、年齢を重ねるにつれて着実に演技の幅を広げている。マルグリット・デュラスの小説の映画化である本作で高い評価を得た。