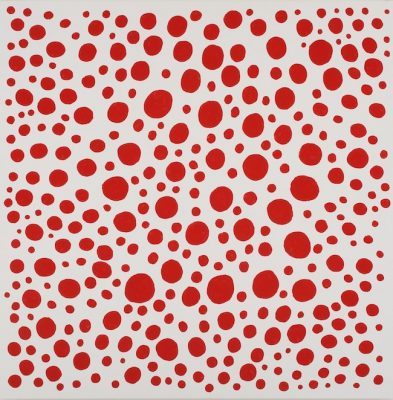森村泰昌展や奈良美智展など数多くの重要な展示を成功させ、現代アートの名裏方として名高い天野太郎。その天野が様々なゲストを迎え、アートの定義や成り立ち、醍醐味を語る連載企画の第3弾。今回は、各界から注目を集める建築家であり、銅版画やドローイングの作品集を出版するなどアートにも造詣が深い光嶋裕介との対話を通し、これからの美術館のあり方、建築のあり方を探った。
(中編より続き)
光嶋「日本の八百万の神、つまりなんにでも『神が宿る』という感覚を現代人は忘れられつつあると思うんです。建築というのは元々ある特定の場所に建つわけで、更地の場合もあるし昔の家が建ってる場合もある。さっきのスクラップ・アンド・ビルドの話でも、何があっても残せということではなく、数値化できないけれど残すべき、伝えるべきバトンというものをどこまで感知できるかを建築家は意識していないといけないと思っています。
それを発見する行為こそが建築家の最大の仕事だと思うんです。その発見したものをしっかりと空間化できればそれはその人にとっての固有のものになると。僕は本で尊敬する建築家たちの名前を出していますが、ダイレクトな模倣は絶対にしたくない。そのような表面的なまねごとはあまりにメッキが剥がれやすい。例えばテート・モダン(ロンドンにある発電所が美術館へと転用された)のような美術館を作ろうとしてもできないんですよ。なぜなら元々レンガの発電所であったという文脈に対してヘルツォーク(スイスの建築家)が出した答えなわけで、違う場所にいきなりあれを真似して作るのは無理なんです。
そういういろんな文脈を読み解く力は建築家一人ではできるものじゃないと思う。それは対話を通してしか発見できないだろうし、他の建築を真似ても仕方ない。ただ建築に限らず、異分野などの絵画、彫刻、演劇など何からでもものづくりの本質みたいなものは抽出して大いに模倣できると思っています。我々の世代も人間の叡智として何かバトンを発見できるんじゃないかという行為、それは『他者への想像力』に支えられた建築家としての最大のチャレンジです」