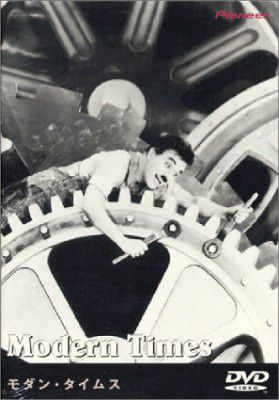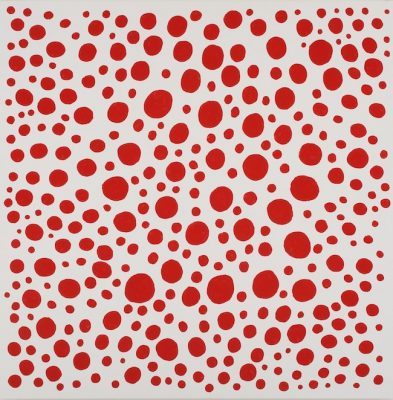スクリーンを見つめる私たちとは別の人生を送る人物たちの行く末を見守り、彼らに感情移入することは映画体験の醍醐味と言える。また映画は、私たちの感情だけではなく身体をも連動させる。1895年パリにて初めてシネマトグラフ(活動写真)が上映された際、画面の中でこちらに近付いてきた汽車にぶつかるとパニックになった観客たちは慌てて逃げ出したという(『ラ・シオタ駅への列車の到着』)。初めて映画館で3D作品を観たときに勝手に体が動いてしまった経験を持つ者なら納得できる出来事だろう。映画と身体の関係性は意外にも密接である。映画の中で描かれる身体は時に、何よりも自由で普遍的なものとして存在する。映画の中の身体表現は何を語ったかを2つの作品から読み解いていきたい。
1.『モダン・タイムス』(1936年)
身体的なアクションを使って見せる喜劇スラップスティック・コメディは、サイレント映画時代、非常に人気の高い映画ジャンルだった。トーキー前の映画においてはセリフによる物語展開が不可能だったために、視覚的に観客を楽しませる必要があった。観客はアクロバティックな演技を楽しむ一方で、役者の身体表現から登場人物の感情や物語の展開を読み解いていた。
そしてスラップスティック喜劇の大スターといえば本作を生んだチャールズ・チャップリン。彼は世の中が次々にトーキー(音声付き)映画へ移行しスラップスティックが衰退する中で抵抗しこの『モダン・タイムス』の制作に着手した。彼は伝記でこう語っている。
“わたしがトーキーに乗り出すということは、あの浮浪者とも永久に縁を切ることだった。なに、しゃべらせればいいじゃないかと言ってくれた人もいたが、わたしにはとても考えられないことだった。一言でも口をきいた瞬間から、彼は別の人間になってしまうはずだ”
浮浪者とはチャップリン映画でお馴染み、山高帽にステッキがトレードマークの「チャーリー」である。チャップリンは、話し言葉によって訛りや話し方から出身地や身分を特定できる具体的な人物として描くのではなく、スラップスティックならではの身体のみの表現で自分自身の分身である「チャーリー」をより普遍的な人物として世界中のどんな観客にも自己を自由に投影出来るようにした。
本作『モダン・タイムス』のチャーリーは、産業革命後工業化により誕生した工場労働に馴染めず精神に異常をきたす。歯車として働くことを強いられ、精神と身体が断絶した末に操縦かんを失った彼の身体をベルトコンベアが飲み込み歯車と一体化するシーンはあまりにも有名だ。身体の個性の消失がやがて身体そのものの消失に繋がることを、この象徴的なシーンで指摘した。
工場の統制されたシステムを乱す彼はクビになり、浮浪者となって社会と言うシステムからも追放されてしまう。効率性と生産性を重視しすぎるあまり機械化が著しく進み、人間の精神と身体をおざなりにする資本社会への風刺がチャールズ・チャップリン最大の特徴である抜群の身体表現とペーソスを持って描かれている。そして、身体は言葉よりも自由であるという彼の姿勢が最大限に引き出された作品だ。
2.『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』(2011年)

天才舞踏家ピナ・バウシュの名を知らずとも、彼女の作品を見れば誰もがそれの持つ生命力を理解するだろう。振付けを意味する“choreography”は「書くこと」を指すギリシャ語に端を発する通り、ピナのコレオグラフィはダンサーの身体という媒介を通じて「命」そのものが宿され、ステージの上で物語を紡いでいく人生そのものだ。またカンパニーのダンサーは「彼女は画家、私たちは絵具」と話している。
全体を一つの意味に回収しない多様な断片の中でダンサーの個性が際立つ彼女の作品は、「インプロヴィゼーション」という手法によって生み出される。新作を作る際、まずダンサーに無数の質問を投げかける。「愛とは何か」「一番望むことは?」「欲しいものが手に入らないときはどうするか」などといった質問に、ダンサーたちはダンスで応え、言葉ではないその“なにか”を表す動作の中からコレオグラフィをしていくやり方だ。
またその心は、観客にも開いている。その都度の公演で観客との間に彼女自身も意図していない“なにか”が起こる瞬間こそが、最も望まれるものなのだ。
長年ピナを敬愛した監督ヴィム・ヴェンダースは、25年にもわたりピナの作品を映像に収める最良の手段を模索していた。本作を単なるコンテンポラリーダンスにおけるパイオニアのドキュメンタリーにするのではなく、彼女の作品そのものを生命力とともに収めたいと考えていたからだ。映像の平面的な表現では不可能かと諦めかけていた矢先の2007年、3D技術の誕生によって彼の模索は終止符を打つ。
ヴェンダースの誠実なまなざしは3Dカメラを通じて舞台空間を見事にとらえた。ダンサー同士にある空間は、空と地、水と土、人と人との間の中で存在する人間の身体を本質的にあぶりだす。3D技術は、舞台芸術そして空間のなかにある“なにか”を表現するピナの作品を描くうえでヴェンダースが抱えていたジレンマを解決した。
「すべては言語と同じで読み取れるものなのよ」。こんなにも肉体は雄弁で、饒舌なのか!言葉にできない“なにか”を追い求めたピナ・バウシュが紡いだ物語は、ダンサーの呼吸とともに永久に残る。
text Shiki Sugawara
『モダン・タイムス』
『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』