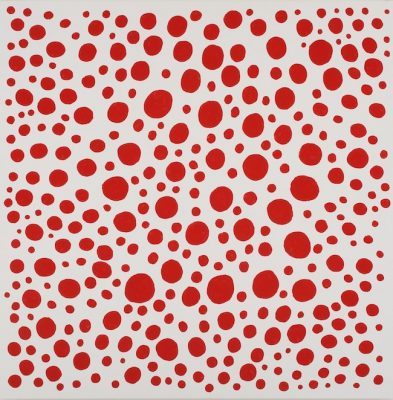——一方アナスタシアですが、彼女はこの作品以前に俳優としての経験がなかったわけですね。どのように彼女からここまでの演技を引き出したのでしょうか。
アンジュラン「ヴァレリーはあらかじめ彼女と読み合わせをしたり、撮影が始まるまでたくさん準備に時間をかけたんだ。もちろんオーディションのときに、彼女はできると確信したわけだけど」
ヴァレリー「そうね、オーディションのときとても自然に演技ができるとわかった。そのあと準備期間にいろいろと学んでもらったわ。映画ーーむしろヨーロッパ映画をたくさん観てもらって、ヨーロッパ映画のエネルギーを感じてもらったのと、とくに反抗的な主人公の映画を観てその感じを掴んでもらった。それから長い時間をかけて読み合わせをした。セリフのひとつひとつの意味を一緒に考えたりして。彼女にはすごく集中力があって、こうしたことをひとつひとつ自分のものにしていったわ」
——たとえばどんな映画を彼女に観るように勧めたのでしょうか。
ヴァレリー「たくさんあったけれど、ヒロイン像という点でいうと、たとえばイギリス映画の『Fish Tank』や、『アデル、ブルーは熱い色』『君と歩く世界』。ジェーン・カンピオンのテレビシリーズ『トップ・オブ・ザ・レイク』も興味深いヒロインが出てくるから勧めたわ。あとはフランス映画に親しんでもらうためにベルトラン・ボネロやオリヴィエ・アサイヤスの映画を観てもらった」
——たとえば『オール・ザット・ジャズ』や『リトル・ダンサー』など、すでにあるダンス映画は参考にしましたか。それともあえてあまり影響を受けないようにしようと思いましたか。
アンジュラン「もちろんそれらは好きな映画だけど……『ウェスト・サイド物語』とかもね。でも僕らが作ろうとしているのはこうしたコメディ・ミュージカルとはまったく異なるタイプの映画だった。それに実際に踊ることができるキャストたちとダンス映画を作ることができるのは素晴らしく恵まれたことだったから、それを台無しにしたくないという思いがあった。何か新しいことをやりたかったんだ」
ヴァレリー「アメリカのコメディ・ミュージカルは大好きだし、物語としても優れたものが多いけれど、わたしたちの映画の場合、ポリーナを通してクラシックからコンテンポラリーまで、異なるダンスを観客に観て欲しかった。もちろんこれはドキュメンタリーではないけれど、ポリーナと一緒にさまざまなダンスを発見してもらいたかったの」
——この映画ではとてもリアリスティックな物語の部分と、ダンスシーンの美しく詩的なシーンとが調和をもって共存していて、それがユニークな魅力になっていると思います。物語のリアリスティックな強さというのは、もしかしたらヴァレリーさんがこれまでドキュメンタリーをたくさん撮られてきたことが影響しているのかなと思ったのですがーー。
ヴァレリー「たしかにそうかもしれないわね。たとえば身体を映すとき、それはダンスをカメラに納めるというだけでなく、ドラマの部分に関しても身体を通してエモーションを語りたかった。ポリーナが家族と踊ったりするときに表現される家族の絆もそうだし、身体表現を通して感情やあるいはキャラクターの社会的な背景なども浮き彫りにしたかった」
アンジュラン「それにポリーナはおしゃべりなキャラクターではないから、身体とともに存在するというか。ダンスをするときもそうだし、日常生活のときも同じ。きっとその共通性が、映画に一貫性をもたしているのではないかな。彼女は言葉では大したことは言わない。むしろ身体を使って表現するんだ」
ヴァレリー「それは往々にしてダンサーに共通していると思う。これまでいろいろなダンサーをみてきて思うことは、彼、彼女たちはえてして寡黙だけれど、ひとたび舞台に立つとその身体を使ってとても豊かに感情を表現する。ポリーナも同じで、見かけは控えめだけど内側に強い力を秘めていて、それが身体を使って表現されるの」
——この映画の冒頭のとても印象的なものに、学校帰りの幼いポリーナが歩いているうちに自然にダンスをし始める場面がありますね。あそこですでにポリーナの強いキャラクターや反骨精神が示されていると思いました。あのシーンはどのように思いつきましたか。
アンジュラン「たしかに彼女の内面を表現するということでとても大事なシーンだった。クラシックバレエを習っていたポリーナが、内側から自然に沸いて来る欲求に従って踊るということを見せるために。バスから降りて雪の上を歩くうちに何か心が解放されて、心の奥底にあるものを表現するんだ」
——あのシーンの音楽も印象的ですが、作曲を担当した79Dにはどのように依頼したのですか。
アンジュラン「この作品の前にも彼らとは仕事をしていたからやりやすかったよ。あのシーンの映像を送って、ポリーナの足並みに揃えてリズムを作ってもらった。ダンスの厳格さを表現するちょっとメカニックでインダストリアルなところがある一方で、心の解放を表現するようなメロディも少し入れてもらった」
——ラストでアナスタシアがジェレミー・ベランガールと踊るシーンですが、あそこでもっとも表現したかったことは何ですか。
アンジュラン「それまで彼女がやってきたことのある種の達成と、クリエイティビティの解放。と同時に、映画的な表現も大事だった。あれはデュオのダンスだけど、カメラもダンスのように動いていたから、まるで三位一体のように構築した。実際この映画ではダンスを撮影するのに3つの方法を使ったんだ。1つは手持ちカメラ。動きが激しいシーンなどに使った。それからより詩的で美しいシーンにしたいときはトラベリング。そして最後のシーンでは、ダンサーがいて観客もいるという複雑な構図だったから、クレーンを用いた」
——撮り方という点では、ポリーナが初めて舞台でオーディションを受けるシーンも、真上からの俯瞰カメラが印象的でした。どうしてあのように撮ろうと思ったのですか。
ヴァレリー「ちょっとオマージュの意図もあったわ。以前、50年代に作られたボリショイ・バレエ団のドキュメンタリーというかドキュ・フィクションを観たことがあって、ああいうシーンがあったの。少女たちが朝学校に来て、ボリショイの大きな舞台に立つ……その構図で彼女たちの小ささが強調されて、とても美しく印象的だった」
アンジュラン「それにチュチュのボリュームが、上から撮ることによってよくわかる。前からだと、チュチュは平面的にしか見えないけれど、俯瞰だとまるで花が咲いているかのように美しく見えるからね」
——ダンスのシーンによって、撮り方やカメラの動きを仔細に考えたというわけですね。
ヴァレリー「ええ、わたしたちにとってダンスをいかにカメラに納めるかというのは、最初からとても大事なポイントだった。今回シネマスコープのサイズを選んだのも、最後にふたりが踊るシーンで彼らのまわりの空間も一緒に納めたかったからよ」
——この映画の最後でポリーナは自分のアーティスティックな声を発見します。アナスタシア自身もまたこの映画を撮ることでそれを体験したのでは?
アンジュラン「そう思うよ。彼女は僕らとの仕事によってダンスのまったく異なる世界を発見した。だから、今まさにいろいろと考えている最中なんじゃないかな。これからたぶん映画も続けたいかもしれないし、コレオグラフィーも手掛けたいかもしれない。この映画の体験を通して彼女自身もより解放されたと思う」


『ポリーナ、私を踊る』
10月28日(土)より、ヒューマントラストシネマ有楽町、 ヒューマントラストシネマ渋谷 ほか全国ロードショー
監督:ヴァレリー・ミュラー&アンジュラン・プレルジョカージュ
脚本:ヴァレリー・ミュラー
出演:アナスタシア・シェフツォワ、ニールス・シュナイダー、ジェレミー・ベランガール、アレクセイ・グシュコフ、ジュリエット・ビノシュ
原作:バスティアン・ヴィヴェス「ポリーナ」(原正人訳、小学館集英社プロダクション刊)
配給:ポニーキャニオン
2016 年/フランス/フランス語、ロシア語/108 分/カラー/5.1ch/PG12/字幕:古田由紀子/ 原題:POLINA, DANSER SA VIE
©2016 Everybody on Deck – TF1 Droits Audiovisuels – UCG Images – France 2 Cinema