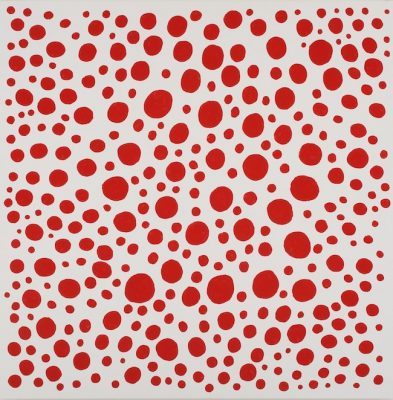フランス漫画界期待の新星バスティアン・ヴィヴェスのグラフィックノベル『ポリーナ』。BD書店賞やACBD批評グランプリに輝いたこの人気作が映画『ポリーナ、私を踊る』と して、いよいよ幕を開ける。一人の天才バレエ少女が、成長していく姿を描いた物語では、バレエをはじめとした様々なダンスの美しさに触れることができる。監督は幅広いジャンルの作品を手掛けているヴァレリー・ミュラーと、バレエダンサーでありコンテンポラリー・ダンスの振付家としても世界的に活躍するアンジュラン・ プレルジョカージュが共同で担当。作品の肝となるダンスと俳優に見事に生命を吹き込むことに成功したふたりに話を聞いた。
——おふたり一緒の監督作というのは今回が初めてですね。そもそもの出会いと、どんな経緯で今回の映画を監督するようになったのか、教えて頂けますか。
ヴァレリー「わたしはそれまでずっとドキュメンタリーを撮っていたんだけど、テレビの仕事でアンジュランのドキュメンタリーを撮ることがあったの。その前から彼とは面識があったし、彼が短編を撮ったときにアシスタントをしたこともあった。たしか90年代の終わり頃かしら。そのあとわたしもダンスを撮るようになって、ダンスをテーマにしたフィクションの映画を撮りたいと思うようになった。そんなとき、この映画のプロデューサーのディディエ・クレストがこの企画をアンジュランに話して、アンジュランが一緒にやらないかと誘ってくれたの」
(アンジュラン頷く)
ヴァレリー「それでわたしはもちろんやりたい!と言って(笑)、一緒にやることになった」
アンジュラン「3年前ぐらいだったかな」
——原作についてはその前から知っていましたか。
ヴァレリー「ええ、わたしたちはそれ以前に彼の前作『Le goût du chlore』というコミックを読んでいた。コミックのフェスティバルがエクス=アン=プロヴァンスであったとき、彼に会ったこともあるわ」
——では『ポリーナ』を読んでどんな印象を受けましたか。
アンジュラン「とても面白いストーリーだと思ったよ。というのも、ポリーナのキャラクターが現代的だったから。バレエの主人公の場合、往々にしてまるで20世紀初頭に生きているかのような、現代的ではないキャラクターになりがちだ。一方このストーリーはとても現代的で、そこが面白いと思った。でもヴァレリーはそこからもっと綿密な脚本を書かなければならなかった。というのも原作のコミックはとても簡潔でミニマルなものだったから。ヴァレリーはそこに深みを与えることに成功したと思う。たとえば映画のなかではポリーナの家族がもっと重要になっているし、彼女はより多くのことを経験する。原作は様式化されたもので、もちろんそれはそれでコミックとして美しいと思うけれど。だから脚色する段階で、もっと肉付けをした。その脚本をもって僕らは資金集めをした。と同時にふたりで準備を初めながら、お互いの役割を決めた。演出はふたりでするけれど棲み分けをする感じで、ヴァレリーは俳優の演出を担当し、僕はフレームやカメラの動きに気を配る。編集も僕が担当する。でももちろんやっていくうちに自然に役割が混ざっていったけれど(笑)」
ヴァレリー「1テイク撮ったあと、一緒に観ながら意見を言い合って、変更したりね。現場はとてもダイナミックで、撮影は早く進んだわ。そのなかでお互い意見を言い合って、俳優の要望も聞きながらコラボレーションをした。とても臨機応変でエネルギッシュだった」
——映画化に関して、ヴィヴェスはまったくタッチせずあなた方に任せたのですか。
アンジュラン「彼は脚本を読んだけど、最初から好きにしていいよと言われた。コミックと映画の違いをよく理解してくれていたんだ。ちょっと前に完成作を観てもらったけれど、とても満足してくれたよ」
——ニールス・シュナイダーはまるでダンサーのように素晴らしいダンスを披露していますね。この映画のために特訓を受けたそうですが、オーディションのときはそれほど踊れなかったわけですよね。彼をキャストするに至ったのはどのような理由からですか。
アンジュラン「ダンスに関して、たしかに最初不安はあったよ。でも彼の演技は際立っていた。だから僕らは、もしも彼がうまく踊れなかったら、最終的に踊る部分を減らせばいいんじゃないかということにした。でも彼はとてもよく踊れるようになったから脚本を変えることはなかったし、ほとんどプロのダンサーたちと対等に踊っていたと思う」
ヴァレリー「彼はとても才能があるわ。動きをすぐに会得したし、それをちゃんと覚えていることにかけても優れていた。ダンスの場合ポーズだけでなく、ムーブメントが大事で、その流れを身体が覚え込まないとだめだけど、彼はそれにも長けていた」

1 2