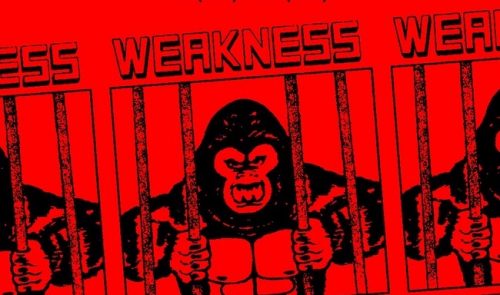アヴちゃん「わたしは作者と演出家が自分についているタイプだと思うのね。あとは身体という媒介を使って表現する言わばモデル。チャラン・ポ・ランタンはどちらも曲を作るし、どちらもおしゃれなんだけど、作者と演出家というのが姉妹で補完できているなって気がする。小春ちゃんだけでもももちゃんだけでももちろんすごくて、ももちゃんもあれだけ演技できるのすごいし」
小春「もものひとり芝居見に来てくれたんだ(笑)」
アヴちゃん「そう、素敵だった。でもふたりでひとつというわけではないにしても、ふたりで最強タッグという感じになっているから運命なんだろうなと思う」
小春「そうね、自分にないものを妹は持っている」
アヴちゃん「それってすごいことじゃない? TOO MUCHになることだってあるわけだから。赤い妹と赤い姉になることだってあった。でも赤いキツネと緑のタヌキじゃないとバシッとこないんだから」
小春「(笑)。元々正反対のふたりではあったけど、チャラン・ポ・ランタンというユニットを姉妹でやっていることによって、余計離れている部分はあると思う。ももにも小春のような部分があったりするんだろうけど、今は良い意味でポジションを囲っている感じはある」
アヴちゃん「お互いそのポジションのプロになりあってるんやね。素敵!」
小春「お互い姉妹でやってるわけだから、アヴちゃんもそういうのあったりする?」
アヴちゃん「ある。わたしたちも正反対だけど、わたしは自分のためにやっていても人のためにやっているように見えてしまうタイプなのね。存在するだけでジェンダーがどうこう、国籍がどうこう、叫びとか言われてしまう。明るい曲を書いても悲しみが伴うと言われるし、悲しみを書いても悲しみをここまで具現化できるなんて、というのが発生してしまうから、それを鬱陶しいとは思ったことないけど、そういうものなんだなって。わたしとしては好きな服を着て、好き放題にアートワークを作ってやっているつもりなんだけど、自然と教祖っぽくなるんだなって」
小春「それはもう……」
アヴちゃん「業だよね。コピーバンドとか組んだりとかなかったんだよね。楽器はじめて1年くらいで、女王蜂というアイデアを買われてデビューした。言い方は悪いけど、出会った頃は投身自殺みたいなライヴしかできなかったし、本当に1回1回ゼロになるみたいな。そうやっているとやっぱり休止しちゃって。でもいまはすごく楽しいよ。やっと俗に言う音楽というものをやれている気がする」
小春「そうかあ。出会った頃はチャラン・ポ・ランタンも始めて1年くらいだったけど、アコーディオンの音色だけで哀愁というのは付いてまわるんだよね」
アヴちゃん「吹いてるからかな。1個1個の音がすべて風が吹いているものって、そういう感じがあるのかも。打楽器ではないじゃん」
小春「そうなのかもね」
アヴちゃん「謎のビブラートとかあるのかな」
小春「それはある。周波数が440ヘルツのハーモニカと441ヘルツのハーモニカを一緒に鳴らしたりするわけだから、そのちょっとしたズレが哀愁を呼ぶのかも」
アヴちゃん「オルゴールに近いね。不思議で絶対的ななにかがある」
小春「変な倍音を良しとする楽器だから、それが自然と懐かしさを呼ぶ。古いレコードみたいに、ずっとピッチが悪いとそれが良しとされるのと同じ感じ」
アヴちゃん「そうだね。聞いた話だけど、日本はどんどんヘルツが上がっているんだって。世界もだけど特に日本が。最初は416とかで、低い頃は戦争がなかったんだって。平安くらいからどんどん戦が増えてきて、いまは440とかだけど、ヘルツを下げると戦争がなくなる説がある」
小春「マジで? 下げよう!」
アヴちゃん「うちらもレコーディングで一度下げたことがあって」
小春「そうすると……もしかして高まるものが減っていく?」
アヴちゃん「減っていくの」
小春「バラードだと良かったりする?」
アヴちゃん「バラードでもちょっとね。雅楽ってヘルツが低いんだけど、雅楽に近くなっていく」
小春「眠くなる感じなんだ。なるほどねえ」