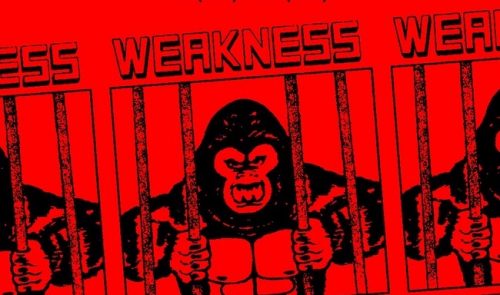——2年!それはすごいですね。
アベル「実際の撮影の段階では役者がそろうので、たとえばスピーカーに合わせてみんなで飛び上がると面白いというようなアイデアは、そろってやってみて出てきたものです。そういったことは脚本を2人で書いている時点では思いつかなかったですし、そういった意味では即興の動きも取り入れています」
——レストランのシーンは特に観ていて楽しかったです。
ゴードン「私たちも気に入っています。実はもし可能であれば、全編をあのように撮りたいんです。つまり、シナリオはすごく単純なもので、現場でいろいろ試しながら手探りで作り上げていくという方法を取り入れたいのですが、やはり映画の資金を集めるためには、どうしても書いた脚本を見せなければならないので、仕方なく書いているという感じです。それがクリエイティブな面をちょっと限定的にしてしまっている部分はあると思います」
アベル「チャップリンの『街の灯』は、確か3年くらいかけて撮影されたんですよね。ほとんどシナリオがなくて、現場で撮っては試して、またやり直しという作業を繰り返して作った映画だと思います。それがバーレスクコメディを作る最高の方法だと思うのですが、今となっては不可能ですね」
——言葉のない、フィジカルな動きによる感情表現が興味深かったです。
アベル「実は僕らは、黒澤作品をはじめとした日本の映画が大好きなんです。彼の作品ではフィジカルなアプローチが大切にされていますよね。それはレアなことで、アメリカやヨーロッパの作品ではあまり見られません。『七人の侍』を観ても、農民の描き方だとか、各シーンが非常にフィジカルに描かれていて興味深いです。僕に言わせれば、ああいったアプローチはバーレスクや映画の始まりに近いものなのです。
——おふたりの演技はもちろん、劇中ではマーサ役のエマニュエル・リヴァさんの演技がとてもチャーミングでした。
ゴードン「私たちの親も年を取ってきて、ドミニクのお父さんは意識がだんだんはっきりしなくなってきましたし、私の母はどちらかというと身体的に衰えてきました。西洋では、高齢者は社会の重荷だという意識があるんです。そんな中で、もっと高齢者の方々を称えたい、彼らの価値を語りたいという気持ちが強くありました」
——なぜエマニュエル・リヴァさんをマーサ役に抜擢したのですか?
ゴードン「最初は別の役者を考えていたのです。というのも、私たちは普段はアマチュアの役者を好んで起用します。アマチュアの役者は自分のやっていることをうまくコントロールできないので、そこで感動や面白みが生まれるんですよね。でも本作では、これだけ高齢のアマチュアの方を見つけるのが難しかったですし、2週間の撮影期間に耐えられる人もなかなかいなかったので、プロの方を探しました。
そして、ある人が『ニューヨーク・タイムズ』紙が作った、エマニュエル・リヴァが出演した絵葉書ビデオという動画を教えてくれたんです。彼女は非常にシリアスでドラマティックな女優として知られていたのですが、その動画を観ると、すごくいたずらっぽかったり、チャップリンの真似をしたり、スーパーマンのケープをかぶっていたり、ちょっと踊ってみたり、おどけてみたり、遊び心のある人だということがわかって、彼女だったらうまくいくかもしれないと感じました」