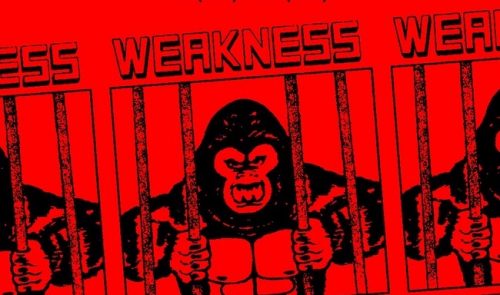「ユースが消費されている」と思うようになったのはいつからだろう。メディアにはミレニアル世代を形容するありとあらゆる言葉が並んでいる。そこで描かれる彼らは、なんでもやってのけてしまいそうで、力強くも見える。でも、そうである必要は何もない。彼らは商品じゃない。弱くても、悩んでいても、何者でなくても、たとえ何者にもなれなかったとしても、魅力的なユースはいる。足りないのは、今のユースの本当の姿を、出来るだけまっすぐに伝えるということ。ただそれだけ。
日本の新人写真家の登竜門とも言えるキヤノン主催の公募コンテスト、写真新世紀が今年も開催される。著名な写真家を多く輩出してきたこのコンテストに参加を決めたユースのありのままの姿とは。公募締め切りを目前に控えた6月12日、応募者の一人である岩渕一輝氏に今の心境を語ってもらった。
——今回写真新世紀に応募した作品は岩渕さんのお祖父さんが亡くなるまでを記録されたものですよね。
岩渕「そうです。今回の写真が自分の写真家としての第一歩になったらいいなと思って応募しました。それくらい自分にとって意味のある写真だったんです。お祖父さんが与えてくれた最後のもので、最高のプレゼントでした」
——私も作品を見せていただいたとき、すごく心に届くものがあるなと思いました。人の「死」という悲しい事柄を切り取っているはずなのに、強いパワーを感じたんです。
岩渕「『容態が変わった、もう保たないだろう』と岩手の実家から連絡をもらったとき、ふと、いまなら何か撮れるかもしれないという気がして、カメラを持って帰省したんです。岩手に着いてからは、お祖父さんの病室で無我夢中でシャッターを切りました。写真の中には、悲しいとか寂しいとかいう感情は入っていません。ひたすら冷静に病室で写真を撮り続けていたから、悲しくなる時間もあまりなくて。泣いたのは3回だけです」
——その3回はどんな時でしたか?
岩渕「1度目は病院の先生から『○時○分、ご臨終です』と言われたとき。残りの2回は棺に遺体を入れて蓋を閉めたときと、火葬の着火ボタンが押されたとき。死を実感した瞬間だけですね。あの写真にとってお祖父さんが死んだっていう事実は、そんなに重要ではないんです。お祖父さんという被写体を淡々と撮り続けるだけで、何も考えていませんでした。出来上がった写真を見てはじめて、写真でこんなことが出来るんだと気付かされました。死じゃないものが撮れていたんです。お祖父さんの身体が新しい生命体みたいに写っていました」