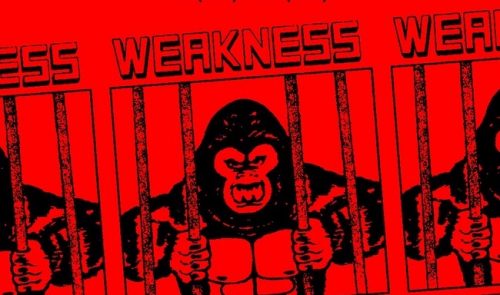──お喋りのリズムの心地よさでは、エリック・ロメール作品も思い出しました。これもまた突拍子もない連想ですが。
大森「ははは、それも全然考えてなかったな。でも俺もロメール、けっこう好きですよ。同じヌーヴェルヴァーグの流れだと、ジャック・リヴェットの作品もいい。『セリーヌとジュリーは舟でゆく』(1974年)って長い映画があってね。ロメールと同じで、これも女の子たちがひたすらお喋りに興じてる。ああいう軽やかさを映画にするのって、すごく難しいんだよな。仕上がりは『セトウツミ』とまるで違うけれど、そういうところは少し重なってるかもしれませんね」
──あえて動きの少ないエピソードを選んだとのことですが、それで娯楽映画として成立するんだろうかという懸念はなかったですか?
大森「それ、皆さん質問されるんだけど、僕自身はほとんど心配してなかったんですよ。だって、魅力的な俳優2人が喋ってるのをちゃんと切り取れれば、それは間違いなく作品として成立するわけで。もちろん適正な尺の問題はあります。でも自分としては『みんな映画という表現を、まだまだ狭く捉えてるんだな』と、むしろ意外だった」
──なるほど。骨太なストーリーとかアクションとか、背景のバリエーションとか、全然ない映画もあっていいじゃないかと(笑)。
大森「もちろん、しっかり物語性のある映画も好きなんですよ。自分でもそういう脚本もちゃんと書いてるし(笑)。ただ同時に、映画界に長くいすぎて、そんな制約に飽きてる自分もいるわけ。そもそも物語って、動きがあって起承転結がはっきりしたものには限らないじゃないですか。その枠には収まりきらない何かを、いかに映画として成立させるかというテーマは、今回のオファーをいただく前からわりと考えていて……」
──たしかに映画という表現分野のなかで、分かりやすい「意味」とか「メッセージ」の部分ばかり肥大化すると、ちょっと息苦しくはなってきます。
大森「そう。それは最近めっちゃ感じてます。最初にも話しましたけど、たしかに高校生を題材にする際、不良とか恋愛とか部活っていう切り口があると分かりやすいですよね。それこそ観る人が意味を見出しやすい。でも現実には、そうじゃない青春だっていっぱいあるわけで…。最近の映画は、それをまるごと取りこぼしてる気もするんです。一方『セトウツミ』は、そういう思い込みから自由な感じがあってね。だから、僕の中でもうまくタイミングがはまったんだと思います」
──そういえば作品中にも、内海君の「この川で暇をつぶすだけのそんな青春があってもええんちゃんか」ってセリフがありました。
大森「あれ、マンガだともっと軽いタッチなんですけどね。映画ではハイスピード撮影を使って、池松君の表情が少しダークに見える撮り方をしていて。あそこは良くも悪くも、ちょっと意味ありげな感じになっちゃってますね(笑)」
──今回のロケ地は、大阪の堺市。この川べりは、原作者の此元和津也がモデルにされたのとまさに同じ場所なんですね。
大森「ええ、櫛屋町のザビエル公園。文字どおり、何の変哲もない場所でした。奥行きもなくてね。だから太陽が傾くと、すぐ建物の影が入っちゃうんです。すごく撮影しにくい場所だったんですけど……そういう場所をちゃんと映画的な空間に仕立てるのも、1つのチャレンジなのかなと。実際やってみると面白かったですよ。たとえば2人の全身が写る引きの絵は、なるべく午前中に撮っておいて。影が入ってくる午後帯には、アップの芝居を集中的に撮るとか。いろいろ手順を工夫しながら進めてました。あと、2週間くらいの撮影日数で約1年間──春先から冬までの四季を見せなければいけなかったので。雑草を抜いたり、枯葉を置いてみたり」