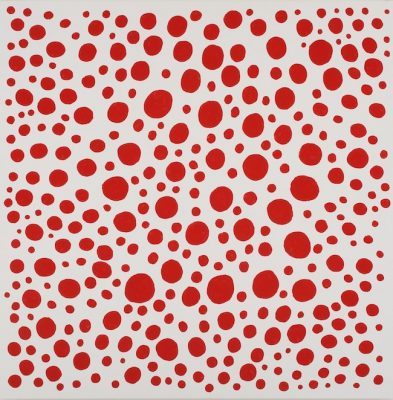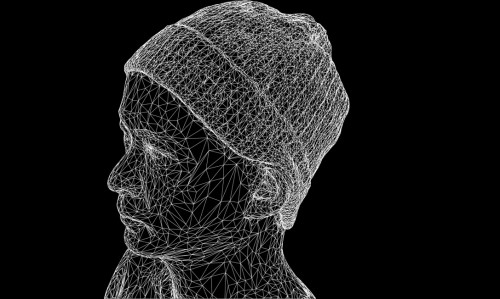――そこがお二方の共通のコアなんですね。空間と建築というところでは出会いは必然なのかなと思いますが、知り合われた経緯は?
齋藤「某携帯会社さんが新しいブランドを作った時に、うちがそのデジタルコンテンツを作ることになって、初めてJTQのオフィスに伺ったときに初めてお会いしました。今でも忘れないのが、多人数がうごめいている中、谷川さんが大きな紙にぶわーっと絵を描いて提案したら、それで即決まっていったこと。その時に具体化できる力はすごいという勉強になった。イニシアチヴをとっていけるんだなと」
谷川「2008年の秋口ですね。みんなでその携帯電話を体験できるブースを作ったんですよ。空間はシンプルだったけど、中ではウェブとリンクするとかやたら難しいことやってて。全部のソリューションを使って、1個のブランドの体験を全方位的に形にするという走りだったんだよね」
齋藤「すごかったですよね。面白かった」
――お付き合いができて、お仕事だけじゃなくアイデア交換されたりする時間もあったんですか?
谷川「いや、とにかく現場主義だったので、全てプロジェクトベースでしたね」
――お仕事のマッチングがうまくいった要因は?
齋藤「僕が惹かれた部分は、谷川さんの具現化する能力。一番優れている人って全体のプランのミクロとマクロの行き来が早い人だと思うんです。要は万里の長城でレンガ1個1個を積み上げながら、これは全体的に何になるんだということが同時に見える人。そういう人はなかなかいないし、訓練しないと絶対できない。僕もその訓練をしようと思いました」
谷川「最初はものすごい数の人がいたので、特段齋藤さんの印象はないんです。テクノロジー系の人は特に多かったですしね。ただ、ちょうどメディア芸術祭という文化庁のイベントも空間構成の仕事でお手伝いをしていた時期で、仕事で関わった死にものぐるいで働いている人達がそちらでは受賞者なんですよ。それが僕にしてみればものすごくライヴ感とリアリティがあって面白かったんです。
テクノロジーと呼ばれるものの解釈や定義というのはすごくいろんな種類があるんだけども、1つ乱暴な括り方をするならば、結局持っている技ですよね。その技をどう主体たる人たちの目的に合わせて、活かしながら、期待しているような目的に辿り着くか。受け止めた人の中に感情などを巻き起こせるものに加工できるか。僕が見る限り、そこがテクノロジーを使っていろんなことをやってる人たちに共通する面白さ。
僕らが作るものはインテリアや建築とは違い、一定の時間が経つとなくなることが多い。だから記憶に残らないと作った意味がない。直接的なものに加えて副次的な広がりを生み出すきっかけとして、どこかで匂いを出すことがとても大事なんです。その匂いを出すときに2つ大切なことがあって、1つは時代を作っていること、もう1つは時代を飛び越えてヘリテイジになっていくこと。これは今でもありだよねというムードを持ったものにいかに近づけていくかという時に、あまり目に見えるものにフォーカスするよりも、目に見えにくい領域にフォーカスして膨らませる方が時間が経っても色あせない傾向にあると気が付いて、そこから特に僕の領域は、あまりその時代のトレンドを追いかけるような床天井を作る仕事じゃなくて、ある種どうやって“コト化”するかを考えるようになったんです。そこにテクノロジーというのは大事な役割を果たしてくれるわけです」
――なるほど。
谷川「床壁天井の進化というのは、どこまでいってもサーフェスなので限界がある。あまりすごいことして歩けなくなったら床の意味がないんです。役割が明確なものは比較的限界値があるんだけど、そこがヴィジュアル化されたら空間の役割や位置付けが変わる。そういう組み合わせは無限だなと思って、テクノロジー系の方たちと積極的にいろんなことをやっていきたいと考えました。その中でも、アーティスティックで、みんなの共感軸を強度に持っていながらも、ちゃんと形として作ることができる職人的なスキルをもった人たちと仕事をしたいと。そこにライゾマティクスがいたという流れです」