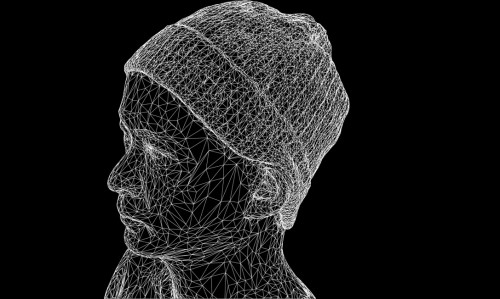今年で4回目を迎える、最先端のテクノロジーカルチャーを実験的なアプローチで都市実装するリアルショーケース、MEDIA AMBITION TOKYO [MAT]が開催中。都内各所を舞台に最先端のアートや映像、音楽、パフォーマンス、ハッカソンやトークショーなどが集結し、都市の未来を創造するテクノロジーの可能性を東京から世界へ提示するこのテクノロジーアートの祭典は、回を追う毎に国内外で注目を集めている。主催であるMAT実行委員会の谷川じゅんじと齋藤精一に、MATの始まりから、コンセプト、可能性、導かれる未来図までを聞いた。
――まず、それぞれのお仕事の紹介をお願いできますか。
谷川「僕の仕事は空間を題材にしながら、コンセプト、空間、体験という3つのデザインを切り口として、これらを繋ぎ合わせることで、ブランディングという領域に様々な施策を押し上げていくことです。そのセンターにあるのは人で、体験によって人の記憶を作る仕事とも言えるかもしれません。食であれば食べておいしい、一緒にいた人と話して楽しい、あるいは展覧会で電気が流れるようなショックや感銘を受けたとか、そういう様々な経験ですね。直接的な体験も大切ですが、副次的に知ったり、関わってくれることも大切で、どういう風に記憶が繋げていくかというところでアウトプットのバリエーションが多いので、全体観は僕もわからないです(笑)」
――(笑)。ユニクロやマークジェイコブスなどの展示ブース、虎ノ門ヒルズのオープニングなど、谷川さんが手がけられたお仕事は幅広いですが、中心は“人”なんですね。ライゾマティクスはテクノロジーの最先端というイメージが大きいと思うんですが、ボディハックという思想があったり、実際は同じく“人”というところにフィーチャーされているのかなと。
齋藤「ライゾマというのは、テクノロジーがあまり表層に出すぎず、だけど裏ではたくさんすごいことをやってもらっていることが当たり前になっていくような、社会なのか街なのか、人なのか、もしくは人が身に着けているものなのか、そういうものに関わっていけたらなと思っている集団だと思っています。
うちが作っているものは、コンピューターやモーター、ギアだったりで、すごくハイテクなことをやっているけどどこかアナログ感があるんですよね。人肌の温度のあるような、そういうテクノロジーの使い方をしちゃってる。できてるんじゃなく、しちゃってるんです。この数年、携帯電話などいろんなものがスマート化しましたが、テクノロジーが出すぎるモノは消えていっている。だから、使う人間も、社会の中も含めて、テクノロジーがあまり前にでてこないものが普通になっていく気がしていて。今の社会はいい意味でやっと人間にフィーチャーされてきているから、その波と合っているのかなと。
今回、ライゾマティクスはアーキテクチャ部門(Rhizomatiks Architecture)を設立したんですが、なぜ建築かというと、やっぱり具体的に人に触れるところ、要はヒューマンスケールがあるからなんです。ウェブサイトにそれがあるかと言ったら、やっぱり二次元を通して、もしくは1.5次元を通してでしかなくて。そういう意味でも、10年やってみて、場所やモノを作ると最終的に“人”に行き着くんだなとつくづく思います」
谷川「そうですよ。ファッションに例えたら、いいブランドというのは、結局そのブランドを誰がいいと言っているかがメイン。受け止めてもらいたい層とコミュニケーションができているかがブランドのポテンシャルだと思うんです。受け止める人達が全部の価値を決めていくので、そういった意味では全ては人が中心に行く気がするんですね。そこがもしないならば、あってもなくてもいいものだというのも言える。人は結局全て人のために生み出すと思っています」