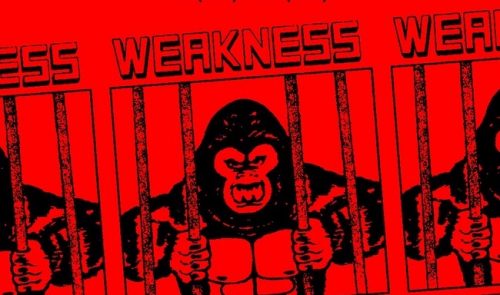八重瀬, 2014 (絶景のポリフォニーより)/2014年/インクジェット・
石川「端的に言えば、それだけ間口が広かったから。カメラというのは誰でも触れて、ボタンを押せば写るというイメージがあった。だけど僕はそれができなかったんです。その試行錯誤のうちに、たぶん写真には可能性というか、できることはたくさんあるという気がした。要は、初めに撮った写真に不満がたくさんあったんです」
天野「撮ろうと思ったけど撮れてないこととか」
石川「多分そこですよね。そこが楽しかった」
天野「それをほかの誰よりも楽しいと思うわけですよね。僕らから見ると写真にハマっちゃうと、みんながその人生を変えてしまう。せっかくいい銀行員になれたのに、いい会社に入ったのに、辞めて写真の世界に入っていく、みたいな。もうこれしかないという、写真には、それが生きてく上で伴侶になると思わせることがあるんだと思うんです。一文無しになっちゃうからやめようとか思わない。それはなんやろう」
石川「夢を見せるんですよね、触りやすすぎて。簡単になんでも作れてしまうという誘惑に負けてしまう。だってカメラを持てば誰でも撮れるじゃないですか」
天野「実際の目の前の世界を撮れることが大きい?」
石川「自分のことを考えたら違うな。なんでハマったんだろう。自分で形にすることは簡単だけど、中身を掘ろうと思えば掘れるみたいな」
天野「写真の中身って何?」
石川「僕の場合、結局は自分です」
天野「撮ってる本人?」
石川「それもあるし、ある部分では自分の中でもコントロールできない部分でもあるし、それを瞬間的に形にできるからなのかな。ものを作るって、そうやって動いて変化していくものだし、それが簡単だから」
天野「絵は描かなきゃいけない。彫刻は掘らなきゃいけない。カメラは全部やってくれるから」
石川「だからこそ、いちばん重要な内容のことは普段の生活に関わってくる。自分がどうあるかみたいなことにかかってくる。だから生き方みたいなものがそのまま出る」
天野「出ますよね」
石川「写真も絵のように自分の内面を映し出すものでもある。ただ絵などは画力や費やしてきた時間も労力もわかりやすく出るけど、写真は差異をなくすようなところがある。そこに何があるか。絵や音楽もどういう歴史を継承しているとか、そこにその人の感覚がうまく表れてるんだということにもなってると思う。天野さんが言ってたように、人だけが何も変わってないとは言わないけど、小手先でやっていることほど人は早く進まないってことですよね。でも1つの欲望の現れではあると思う」
天野「写真はある意味視覚の欲望の塊だから。例えば、カメラは戦争のたびに進化している。特に1950〜60年代の東西冷戦航空写真。NASAも宇宙から撮ってるし、何万眼も撮れる技術を生み出して、それが20世紀のカメラに反映される。つまり写真やカメラは産業に支えられている、これも他のジャンルとは違うところ」
石川「でも絵画も産業だった時代がある。僕はメディアやツールは次の媒体が出てきて初めてそこから自由になれると思います。行き詰って初めて広がりが出てくる。絵画や音楽もそうだと思っていて。その当時絵に求められていた何かが写真に取って代わられたときに、初めて本当の絵が見えてきて、中心が見えてきた。そこから広がりがでてきたというイメージがあるんです。それは勝手な僕のイメージですけど」
天野「うん」
石川「写真はそこの可能性がまだあって、まだ行き詰ってないと思われている。だけど、実際にはもしかして行き詰っているかもしれない。もっと時間がたったときにそれを見て、あの時には行き詰ってて、そこから広がりが出てきたよねとなるような感じがあって。そういうことは結局は後になってからしか判断つかないことだから」
印画鏡02/2010年/ゼラチンシルバー・プリント