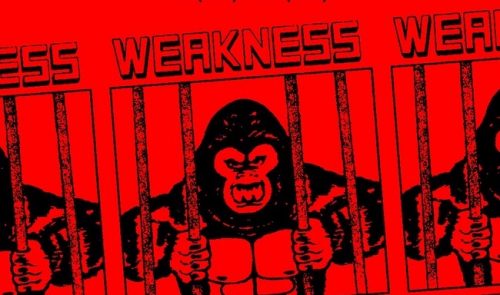「ピー」
と笛が吹かれたかと思うと、一斉にレースが始まった。やけにボールを地面にぶつける音が大きく耳に響く。次から次へと、見ず知らずの同じ背格好の男女が、黙々とボールを弾き、受け渡している。どうやら、僕らのチームが少し遅れを取っているようだった。あと、二人で出番となったとき、とうとう緊張は吹っ飛び、心の中に闘争心が燃え始めた。
「逆転してやるぞ!」
と覚悟を決めた。とうとう一個前の子がコーナーを曲がり、こちらに向かって走ってきたとき、僕は相手チームのアンカーをチラッと眺めた。
そこには、僕より少しだけ背の高いひょろっとした男の子がいた。顔は、これでもかと云うほど、豆に似ていた。おまけに、周りの子から
「ユウタ!ユウタ!」
と熱い声援を受け、まんざらでもない顔で頬を赤く染め、その表情は猿そっくりだった。
「こいつがここの山のボス猿だな」
と、悟った。絶対に負けられない、ともう一度心に決め、僕は少し遅れを取ってボールのバトンを受け取った。そこから、無我夢中にボールを叩きつけ、走った。コーナーを曲がって、とにかく最終ゴールに向かって、ひたと走った。何故か、姉が小学校の研究で飼っていた蚕たちが頭の中でぐるぐると浮かんでいた。繭から必死に躯をもがき出し、蛾となり飛び立って行った、かつての蚕たち。姉二人は気味悪がって、キャーキャーはしゃいでいた。僕は、背中から羽が生えたような錯覚を覚えた。
「もっと速く走れる!」
とそう感じて、たまらくなくなった。初めての感覚だ。
何とかゴールラインにたどり着いたとき、勝敗はほぼ同時だった。いや、完全なる同時と云って言いだろう。会場にいる全ての人間が、そう判断したのだ。良いレースだった。誰一人として、勝敗を決めようとするものはおらず、劇的なデッドヒートと、新人の活躍を喜んだ。とにかく僕らは、周りの子から二人のアンカーに当てられた熱い声援を浴びながら、見つめ合いながら笑った。ただただ、笑い合った。そこには、
「お互いやるじゃないか。よろしく。」
と云う意味合いが込められていた。それぞれがそう感じながらも、僕らは自己紹介も握手もしなかった。何故しないのか、自分でも不思議なほどだった。満足そうな表情を浮かべた、香水おばちゃんが、タイミングを見計らってから、こう叫んだ。
「さぁ皆さん。人生は出会いの連続よ!」