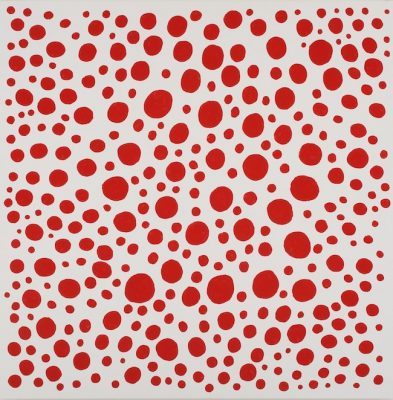──たしかに、トータルな演出力が問われますね。
小林「まぁ、たとえば観客席に音楽評論家を座らせて、『おおっ、なんて素晴らしい演奏だ』とか言わせれば一発で伝わるんでしょうけど。それはそれでかっこ悪い(笑)。とはいえ正攻法でちゃんと撮ろうとしたら、50人からいるオケのメンバーを演じる役者さんたちに全員、きちんと楽器を扱えるようになってもらわないといけない。もちろん今の日本映画でそこまで準備期間をとる大変さも、重々わかってますし。頑張ってやったからといって、自分がイメージしてるものが撮れるとはかぎらないですしね」
──でも結局は、トライする方を選ばれた(笑)。
小林「ええ、まあ。はははは」
──ズルしちゃおうとは思わなかったんですか。さっきおっしゃったようなベタな演出を積み重ねて、演奏シーンはぜんぶ手元の吹き替え映像にするとか…。
小林「でも、それだと結局、『マエストロ!The Movie』みたいな感じになっちゃうでしょう。安っぽいドラマにするのは簡単だと思うんですけど、それだとやっても意味がない」
──脚本は『八日目の蝉』(2011)や『おおかみこどもの雨と雪』(2012)などを手がけた奥寺佐渡子さん。オムニバス形式っぽい原作の持ち味を生かしつつ、オーケストラ再生にまつわる骨太な物語に仕上げておられます。
小林「たしかに原作は、もうちょっと短編集っぽいんですよね。登場人物それぞれに“いい話”があって。楽器にまつわるウンチクなんかもたくさん入ってます。その中からどうやって映画の背骨となるエッセンスを抽出するかというのは、奥寺さんとけっこう話しました。エピソードの断片をつぎはぎするんじゃなくて、むしろ原作を一回バラして。原作の核にあったエモーションみたいなものを、奥寺さんと一緒に再構築していったという感じでしょうか」
──そのエモーションというのは、具体的には?
小林「うーん……月並みですけど、やっぱり“音と命”ということじゃないですかね。どちらも一瞬で消えてしまうんだけど、だからこそ心が震える。クラシックという音楽を通じて、そういう感じを出せればいいなと。ただ、僕も奥寺さんも、2人のプロデューサーもクラシックについては、具体的には何も知らなかったので。だから今回、音楽を担当してくださった上野耕路さんに、いちから講義をお願いしました。それこそ、『ベートーヴェンってどんな人なんですか?』っていうレベルから始まって、『そもそもソナタ形式って何ですか?』みたいな(笑)。あとは、実際のオーケストラのリハーサルを見学させてもらったり。何だかんだで、半年くらい“お勉強期間”があったと思います」
──物語のプロットを考える前に、本当にベーシックなところから取り組んだわけですね。その勉強を通じて、小林監督の中でクラシック観が変化した部分はありましたか?
小林「オーケストラって、知れば知るほど社会の縮図みたいなところがあるんですよ。知的で高尚なイメージがあるかもしれないけれど、中味は決してユートピアみたいな場所じゃなくて。技術とプライドを持った一匹狼の集りだから、むしろものすごく人間くさい。指揮者は『なんでこいつら、俺の思うとおりに演奏しないんだ』とイライラしてるかもしれないし。音楽観の違う楽団員同士が、見えないところでいがみあってることだって、そんなに珍しくはないと思う……実際見たわけじゃないですけど(笑)。でもその一方で、どこか1つのパートが欠けても演奏が成立しないのも現実なんですよ。たとえばヴィオラなんて、一般にはあまり馴染みのない楽器ですけど、いなくなった途端にオケの音が味気なくなってしまう。そうやっていろんな不満を抱えつつ、日々なんとかやっていく姿って、僕らが生きてる社会と同じなんじゃないかなと。そう思えたのは、自分にとっては発見でしたね」
──美しいハーモニーも、次の瞬間には空中に消えてしまう。この映画のテーマにも直接関係します。
小林「そう。たしかに音楽は、至福の時間を体験させてくれるけれど、演奏が終わればまた苦しい日常が待っている。でもまぁ、人生そういうもんだと思うんで(笑)」