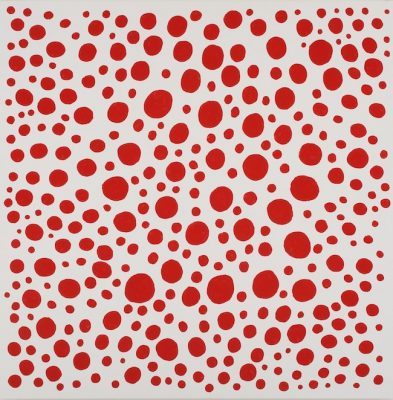──じゃあ、脚本より先に特訓だったんですね(笑)。
松坂「はい。ただ、原作のマンガは先に読ませてもらって、クラシックという音楽をすごく身近に感じさせてくれる作品だなぁと思いました。僕自身もそうなんですけど、やっぱりクラシックのコンサートって特別感があるというか……。ちょっと敷居が高いじゃないですか。でも海外だと、若いカップルが映画を観にいく感覚で気軽に出かける文化があったりする。だから映像化に際しても、この映画がクラシックへの間口を広げるきっかけになればいいなという思いは、すごくありました」
──11億円もするストラディヴァリウスを弾いた感想は?
松坂「ストラディヴァリウスって、実はすっごく軽いんですよ。本当に紙のように軽い。風でフワッと飛んでいくんじゃないかと思うくらい。で、弓が重いんです。弓にしっかり重みがあるので、手で押さえなくても、弓の重みですっと吸い付くんですよね。いいバランスで、ちゃんと構えとしてぶれずに弾けるというか」
──香坂という主人公への共感はいかがでした?
松坂「彼は思ったことをあまり口に出さないタイプですが、うちに秘めた思いは深い人。小さい頃から父親にヴァイオリンを教わってきて、『この世で一番美しいものは音楽だ』と言い切れる強さを持っています。彼が求める音楽がものすごく高いところにあるというのは、台本を読んでも、現場で彼を演じたときにもすごく感じましたし。でも、そういった感情をわっと露わにせず、いわば青い炎を内にふつふつと宿しているところは、自分の中で共感する部分はありました」
──コンサートマスターを演じるにあたって、楽器以外の部分で工夫した部分は?
松坂「現役でコンサートマスターをやられている方に何人かお話を伺いました。ただ、やっぱり答えは1つじゃなくて……。『オレについてこい』という指揮者とガンガンやりあうコンサートマスターもいれば、自分はパイプ役に徹し指揮者の意図をオケのメンバーに伝えようとする方もいる。たとえば団員たちに合図を出すときも、イケイケの人は身体全体でガッと合図を出すし、調整型の人はヴァイオリンのネックを控え目にクイッと上げるだけだったりして(笑)。人によって本当にさまざまなんですね。その中から、うまく使えそうなところを自分なりにピックアップして人物像を作っていきました」
──映画を観ていても、最初はバラバラだったオーケストラのメンバーが次第に団結していく感じが、手に取るように伝わってきました。
松坂「それは嬉しいですね。最初は香坂1人が空回りしている感覚だったのが、だんだん指揮者と団員の間に化学反応が起きていって。終盤戦になると、彼自身も体験したことがない未知の音楽の状態へとどんどん入っていく。その過程を楽しんでいただければと思います。僕自身、内に秘めた青い炎がぼっと点く瞬間というのかな。香坂を演じるにあたって、ある種のクールさと情熱の振り幅みたいなものは、すごく意識しました」