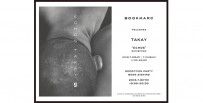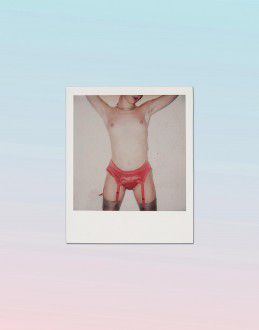
—マドンナはあなたの意見を素直に聞いてくれたようですが、デボラ・ハリーはそうでもなかったとか。
Maripol「デボラ・ハリーの衣装は、彼女と同じマンションに住んでいたスティーヴン・スプラウスによるものでした。彼女はとても心の優しい人で、人を傷つけるということが絶対できない人なので、彼の顔を立ててあげたかったのだと思います。その衣装はロングドレスで、カバーではそのまま写っていますが、中のヴィジュアルでは私が作ったベルトで短くしているものもあれば、長い丈の時も腕にそのベルトを巻いてアクセサリーにしている写真もあります。今もショーで会ったり、彼女がコラボレーションしたフランスのミュージシャン、Etienne Dahoを紹介したり、友人関係は続いていますよ。その曲はNYのダウンタウンについて歌ったものなんです」
—バスキアやキース・ヘリングの映画のディレクションも手がけていますが、写真と映像ではやはり意識は異なりますか。
Maripol「映画のほうが痛々しい(笑)、もとい難しいですね。長い時間がかかりますし」
—バスキアが主演した『DOWNTOWN81』は資金難で公開までに約20年の月日がかかっていますしね。
Maripol「当時は辛かったのですが、結果的には良かったと思います。その時に公開されていたら、人の記憶にこれほど残ることなく流れて行っていたのではないかと思うのです。今そのフィルムの高画質版の編集をしていますが、色の奥行きが出ていてとても楽しいですよ。そのバージョンがいつ公開になるかはわかりませんが、私は『DOWNTOWN81』を愛しているからこそ労力をかけることを厭いません。1981年からずっと頭から離れない映画です」
—差し支えなければバスキアと初めて会った時の印象を聞かせていただけますか。
Maripol「彼はとてもシャイでした。もしかしたら私もね。最初に会ったのは、グレン・オブライエンのテレビ番組で、私はそこでカメラを担当していて、彼は隣で小さなポストカードサイズのコラージュを作っていました。まだグラフィティ・アーティストだった頃です。そういう静かな出会いでした。彼は金髪のモヒカンでしたけどね(笑)」
—(笑)。現在のクリエイションとしては、写真、映像のほかにどのようなことを行っていますか。
Maripol「今はもうスタイリングの仕事はしていないけど、やるならまだビッグになっていないけどなる可能性を持っている人がいいですね(笑)。今のファッションはすごく簡単になってしまっていますし、これがファッションだという定義が出来てしまっているので興味が持てないのです。私は今と当時を行き来するようなことをやっていて、過去のポラロイドのアーカイブをどう使うかと考えたり、きれいにプリントにしたスペシャルエディションを作ったりもしていますが、最近ではポラロイドでのファッションストーリーを撮ってほしいという依頼も多く来ていたり、映画の制作に関わっていたり、結局昔からやっていることは変わらない気がしています(笑)。けれど、その時々でパーツがちょっとずつ変わっているという感じでしょうか」
—絶え間なく表現を続けるあなたの原動力は?
Maripol「息をするように自然とクリエイションをしているのです。本の中にそのような詩もあったかもしれませんね」
—素晴らしい言葉をありがとうございます。では、最後の質問です。あなたはメガネもコンタクトもしないと聞いていたのですが、今手元にメガネがあるなあと……(笑)。
Maripol「あははは! 最初にNYに来た時に、裸眼で見ると美しかったのにコンタクトだとあまりに汚くて嫌気がさしたんですよね(笑)。でもその後、必要にかられてコンタクトをつけるようになりました。今日は疲れていたからメガネですけどね(笑)」