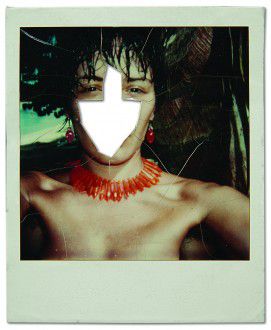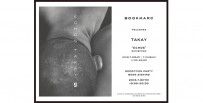—なるほど、すごく興味深いです。NYのシーンについても聞かせてください。あなたがフランスから移住した70年代後半から80年代のNYは刺激に溢れていた時代ですね。やはりアーティストにとってはスペシャルな場所でしたか。
Maripol「最初にNYに9ヶ月間住んだ後、一度フランスに戻ったことがあるのですが、なぜ戻ってきてしまったのだろうとすぐに後悔しました。それくらいNYは魅力的でしたね。その頃のNYはうまく機能しておらず、世界は真っ二つに分かれていました。アップタウンでは安全で綺麗、一方ダウンタウンは汚く、犯罪が多く危険きわまりない場所というように。
私は当時の彼と1979年にダウンタウンに住みだしたのですが、アーティストは広いアトリエを求めて必然的にダウンタウンに集まっていたのです。そこはとても小さなコミュニティだったので、わざわざウォーホルと知り合うためにファクトリーに行くというような感じではなく、誰もが自然と顔見知りになっていました。私も自然とファクトリーに通っていたし、STUDIO54が出来た時も、マーケティングしてああなったというのではなくその当時に一晩行く場所として自然と成り立っていたのです」
—その中でポラロイドカメラを常に持ち歩くフランス人のあなたは、人々からどのように見えていたのでしょうね。
Maripol「私は泥酔したり、ドラッグに溺れるということに興味がなかったので、唯一正気でカメラを持っていた存在でしたよ(笑)。そんなことよりスナップしているほうが楽しかったのです。もう一つとても重要なポイントとして、当時は記録として残すという意識はなかったのですが、ヨーロッパから来た人間としてはどこかよそ者という意識があり、自分の中にジャーナリストとしての様相があるというのは感じていました。アメリカの写真家やジャーナリストもいますが、彼らとはおもしろいと感じるポイントが違うので、ああいう写真になったのだと思います」
—ジャーナリスティックな目線であったというには、被写体のパーソナルな側面が色濃く出ていますね。
Maripol「70年代というのはロンドンやヨーロッパで起きた60年代のデモから10年後であり、ロンドンからパンクシーンが流れて来たり、どんどん過激なものがアメリカに集まってきた時代です。人々はファッションやビューティで遊び尽くし、自らどんどん過激になっていっていました。
まだハイファッションというものがなかったので、ヴィンテージショップから60年代のドレスの一番素敵なものを選んできたり、とにかく個性的な人が多く、題材としてとても面白かったのです。私自身も大学ではパターンも学んでいたし、アーティストでありながらファッションにもとても興味がありました。だからその頃はとにかく人の顔や美しさ、ファッションが撮りたかったのです。被写体も、カメラを向けられることを『私のことを見てくれているのだ』という愛を感じて曝け出してくれていました」
—あなたは写真だけではなく、デボラ・ハリーやグレース・ジョーンズのスタイリングをしたり、フィオルッチでアクセサリーデザインをしていたりと多様な表現をしていました。それらの多様な表現はどのように生み出されていったのでしょう。
Maripol「色々なことをしていたというよりは、自分の性格の一連の中で全ての表現をしていたのです。当時はスタイリストという職業が確立されておらず、自分のスタイルがある人が頼まれて行っていたというだけです。そのスタイルというのも自分にとっては計算してやっていることではなく、自然に生まれたもの。アクセサリーも欲しいものがなかったから自分で作ったというだけ。フィルオッチに勤めていた頃はよく香港出張に来ていたのですが、その途中に必ず東京に立ち寄っていました。ラバー・ブレスレットは日本でインスピレーションを受けてできたものなんですよ」
—確か、配管などの工業製品から着想を得たとか。
Maripol「そう、工業的な部品を違う方向に活かすという表現でした。まさかこんなに流行るとは思いませんでしたが(笑)」
—あなたのラバー・ブレスレットはマドンナの『Like A Virgin』のカバーにも使われたことでも知られていますね。あのジャケット撮影時にはアート・ディレクションという形で関わっていたのですか。
Maripol「別のアート・ディレクターがいたのですが、彼が提案していたのはゴシック的な衣装でした。私はマドンナと元々知り合いでもあったので、それでは面白くない、『Like A Virgin』と歌うのならば徹底的にそこまで遊んだほうがいいと提案したのです。最初にスタイリングをしたのはMTVアワードでのショーで、スカートを煽って撮影したり、そんな歌なのに宗教的なクロスをつけていたりと非常に話題になりました。彼女にとってはよかったですよね(笑)」