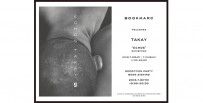—では最初から記録ではなく作品という意識で撮っていたのですか。
Maripol「意識的ではなく無意識にそうしていたのだと思います。私は写真を撮るだけではなく、様々な表現をやっていました。その中でポラロイドというのは今で言うiPhoneのような非常に便利なツールだったのです。もうひとつ、私がアメリカではなくヨーロッパの人間だというのも大きなポイントだと思います。アメリカ人はより合理的で、例えばナン・ゴールディンは自分の人生を題材にして、ドラッグやセックスを使ってひとつのアートフォームを作っていますが、私は自分の感情のままにポラロイドを使っていました。自分をシンディ・シャーマンと比較するつもりはないけれど、ご存知のように彼女はセルフポートレイトでの表現を行っていて、私にもそのように自分を題材にしたものが多くあります。ただ、私の場合は誰かに見られることを前提とした作品というよりは、悲しみや怒りなど自分の中の感情を出すためのものだったのです。
当時はそのように感情としてやっていたことでしたが、今は自分の写真がアートになりつつあります。先週、ラスヴェガスにポラロイドミュージアムがオープンしたのですが、ウォーホルの作品も私の作品も展示されていますし、MFAH(The Museum of Fine Arts, Houston/ヒューストン美術館)の館長が写真に造詣が深く、私の写真をコレクションし始めているんですよ。実は私はオリジナルを一枚も売ったことがなくて全部保存しているので、それをどのようにアーカイブしていくのかも考えているところです。元々はそうではなかったものがアートとして認識され、これからどのようになっていくのかはわからないけれども非常に楽しみですね」
—作品の中には切り取られたり、ペイントされているものもありますが、あれらも感情の表現のひとつだったのですか。
Maripol「当時は遊びやアートの延長線でした。ゲルハルト・リヒターも、ものの上にアートを加えるという手法をとっていますよね。私の別のアートブック『Little Red Riding Hood』のカバーでは目の上にペイントを施していますが、あれはネイルでやっているんです。グラフィックとしての遊びもあれば、綺麗ではないところを隠すためにやることもあり、時には自分を破壊するような意味合いでやることもありました」