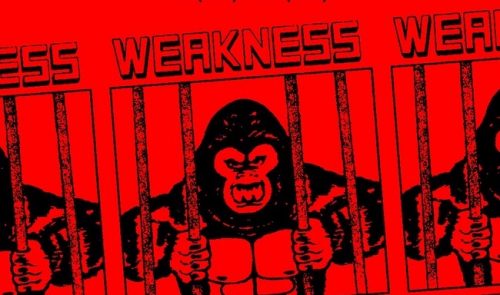──アルバムでいうと、『Bone Machine』(1992年)あたりのサウンドなんてまさにそうですよね。じゃあ、その一斗缶の記憶がそのままオープニング曲“Neon Sign Stomp”に繋がっていったと。たしかにこの楽曲、“♪ズッタン、ズッタン、ズッタン”という強烈なストンプビートが基調になっています。
森「あのビート、実はパーカッションのAsa-Changさんが、本当に一斗缶を叩いてくれてるんです。名打楽器奏者にそんなお願いするのは、申し訳ないとも思ったんだけど。おそるおそる聞いてみたら『あ、浅草のあのオッチャン。俺も大好きなんだよ。光栄です』と返事が返ってきて。あ、これはいけると(笑)。そこからはいつもの通り。まず僕が基本となるギターのコードをループで演奏して、そこによっちゃんが自由に歌詞を乗せていく感じで──」
中納「私的にはやっぱりドラマのオープニングなので。曲調的には疾走感というか、後ろから何かに追い立てられてるような切迫感は出したかったんですね。で、森君がリフを鳴らして、そのモチーフを2人で膨らませたり削ったりしていく。そうやってセッションを重ねていくと、自分の中で鍵になるフレーズが自然と生まれてくるんです。例えば今回は“街頭のBlues”とか“一斗缶のRhythm”がそうなんですけど。そこから手探りで歌詞の世界を広げていった。基本的な作り方は、いつものエゴと変わらなかったですね」
──歌詞のイメージを広げる際には、シナリオも参考に?
中納「いや、どっちかというと先に読んでいた原作マンガの印象が強かったかな。あとは自分なりに、浅草の風景を想像しながら……。何やろう、このシリーズって登場するのは奇妙な人ばっかりやし、話の設定もかなり変わってますけど、読後感が妙にリアルなんですよね。こうやっていろんな荷物を背負い込んで生きてる人は、現実にもいっぱいいるんやろなと思って。切ない気持ちになる。でも、そのヘヴィーさが嫌いかというと、むしろ反対で。キレイゴトじゃないから信用できるというか。読んだ後ちょっと希望がわくような気もする。その感覚は大事にしたいなと」