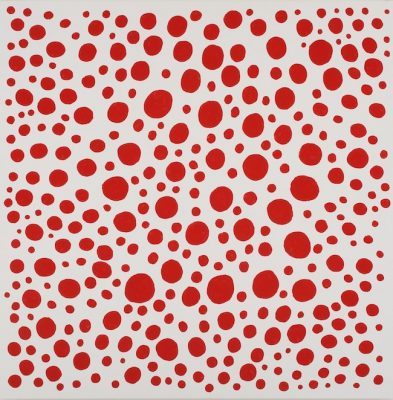3月8日の国際女性デーに合わせ、女性をエンパワメントし、ジェンダー平等を考える3月の特集「IWD 持続可能なわたしたち」。2022年のIWDのテーマは「持続可能な明日に向けて、ジェンダー平等をいま」。ジェンダーギャップ指数が先進国の中でも著しく高く、性的な搾取や家庭内でのケア労働など、とかく女性が消費される構造で成り立っている日本。女性が消費されず、尊厳や選択を持続可能なものとするための問いを投げかける。
2020年に刊行された『持続可能な魂の利用』(中央公論新社)で、SFと現実を織りまぜながらアイドル業界と日本社会の構造の類似を指摘、「おじさん」がいない世界での女性たちのあり方を描いて見せた作家・松田青子。日本の怪談にはびこる家父長制の罠をユーモラスに解き明かし、世界幻想文学大賞・短編集部門を受賞した『おばちゃんたちのいるところ』(中央公論新社)など、松田が綴る既存の価値観に依らない女性たちの解放された姿は、少し先の未来を映して希望をもたらしてくれる常備薬のよう。作家/翻訳家として、また一人の女性として、持続可能なあり方を模索してきた軌跡について聞いた。
――松田さんはご自身が持った違和感を種にしてお話を紡がれているように思うのですが、「おじさん」「家父長制」が染み込んだこの社会や教育では、従来の価値観に違和感を持つことすら難しい場合があり、それが問題の矮小化に繋がっていると感じています。松田さんはどのようにして違和感を持つようになり、それを持続させていきましたか。
松田「違和感については、私の場合は2段階ありました。1段階目の違和感は、人間として生きていくうえの違和感で、私は幼少時にアトピーがひどく、体調が悪いことも多かったんですね。当時は今よりもずっと理解がなかったので、外の世界に出ると、大人も子どもも、こっちを“異形”として見ているのがひしひしと伝わってきました。“普通”とされている状態に私は入れないと感じていましたし、できない“普通”がたくさんありました。たとえば、学校の体操着は化繊だったんですが、他の子たちにとってはそれが“普通”でも、自分は肌が荒れたり湿疹が出たんですよね。みんな同じでいなくてはならない学校生活が本当にしんどくて、不登校の時期もありますし、中学生の時には円形脱毛症にもなりました。しかも私、左利きなんですよ。これもやっぱり、日常的に“普通”が自分とは逆に設定されていることを意識させられる一つの要素ではありました。だから、もう十代の頃から「普通」に入れていないし、絶えず“普通”を意識しながら生活しているような状態で、違和感=私の日常、という感じでした。『アダムス・ファミリー』のウェンズデーや『ビートル ジュース』でウィノナ・ライダーが演じたリディア・ディーツのような暗い子たちに共鳴したし、暗い、明るい世界に馴染めない子たちが物語に出てくることに救われていました。そういう子ども時代だったこともあって、自分の身を守る方法を自分で模索しなければならないという意識もはやくからありましたし、その意識が今もずっと続いています。
2段階目は女性として生きるうえの違和感で、十代もそうですし、特に大学に入ってからの二十代に自分が経験した、変だったり、理不尽だったりする出来事の数々が、女性差別や社会構造の問題に起因しているのだと、はっきりとわかるようになったのが20代後半でした。30代手前になった頃、手に取りやすいジェンダーに関する本が出てくるようになって、それらの本を読んだことで、それまでの違和感をもたらしていた原因が理解でき、視野が広がったような明るさがありました。周りにもそうした話ができる人たちが増えてきて、私は今42歳ですが、年々楽になっていくなと感じています。世の中の変化もあるし、自分も経験値が積まれていくから、以前だったら『自分も悪かったのかな』『これってどういうことだろう、でもいい人だし……』とモヤモヤすることがあったのが、これはあかん、と一瞬で答えを弾き出せる。レベッカ・ソルニットの『説教したがる男たち』でマンスプレイニングという言葉が生まれたように、共有されて説明不要になった事柄も多い多いですよね」

――どちらの段階でも松田さんの希望や土壌となったのは本や映画。多々の作品でどのような人生観やジェンダー観に触れられてきたのでしょうか。
松田「幼少期は児童文学や少女漫画をたくさん読んでいたのですが、今思うと、それが私の土台を築いてくれたと思います。『長くつ下のピッピ』のピッピは自由気ままで、『メリー・ポピンズ』のメリー・ポピンズは不遜でつんとしている。「普通」の枠の外にいる女性に物語の中でたくさん出会うことができましたし、それらの物語の価値観を吸収していたことが、大人になってからの私を救ってくれていると感じてきました。これらの作品が女性作家によって書かれたいたことの意味を、作家になってから痛感しています。大島弓子さんや岩館真理子さん、楠本まきさんの作品を中学生の頃から愛読しているのですが、彼女たちの作品に出会えたことにも、とても感謝しています。
ジョセフ・ヘラーの『キャッチ=22』を読んだ時は、自分と同じことを考えている人がいるのだと本当に嬉しくなりました。戦争を風刺した作品なのですが、主人公の兵士は第二次世界大戦時にイタリアのピアノーサ島に派遣されていて、戦いたくも死にたくもないのに、死ななければ帰ることができない。不条理の極みの中にいる兵士たちがいかにサバイブするかという話で、それが現実に対して自分が感じる気持ちととても近く、人生のバイブルになっています。大学では英米文学を専攻していたのですが、やはり授業で取り扱うのは圧倒的に男性作家の作品が多かったです。でも、短編小説のクラスなどで、女性作家の作品を読んだ時に、自分の心が共鳴することに気づきました。シャーリイ・ジャクスンの「くじ」には衝撃を受けましたし、スーザン・マイノットの「欲望」という、個人的な性体験の経験を簡潔に並べることによって、女性であること、を端的に示してみせた短編には、短編にはこういう可能性があるのかと目を見開かされました。
十代の頃を考えると、当時はインターネットもなかったので、雑誌を主に情報源にしていたんですが、本や映画がたくさん紹介されている女性誌でも、真から女性の観点で選ばれたものが少なかった気がします。男性の選者が自分たちの観点から女の子に読んでほしいと思うものを選んでいたり、女性の選者であっても、男性社会の価値観を内面化してしまっていたり。若い女性たちの魂を救う作品を本当に選べていたのか、といった疑問が残ります」
――まさに『男の子になりたかった女の子になりたかった女の子』ですね。
松田「そうですね、だから、本当はすでに世界に存在しているのに、過小評価されていたり、有名じゃなかったりした女性作家の作品に出会うのが遅れてしまった、という残念さはありますね。とはいえ、そんな中でも、出会えてきた作品もちゃんとあります。二十代の頃、アニエス・ヴァルダの『幸福』(1965年)を観た時にも驚きましたね。小学生か中学生の時に彼女の『ジャック・ドゥミの少年期』(1991年)を観たのですが、『幸福』の衝撃は凄かった。作品の中の夫婦は幸せそうに暮らしているけれど、ある悲しい出来事が起こって、でも・・・というすごく恐ろしい作品。壮絶な切れ味で、社会で女性が置かれた状況を表す時にこういうやり方ができるのかと本当に驚きました。
この数年で一番凄いと思ったのはセリーヌ・シアマの『燃ゆる女の肖像』(2019年)。友人から聞いたのですが、これを観たある男性編集者が、意味がわからないし、何一つ響くところがないとSNSで言っていたそうで、この作品が必要な人にだけ届くようにつくられているのも凄いと思いました。女性だけを向いてつくられた作品が、世界的にしっかり届いていることにすごく希望を感じます。パク・チャヌクの『お嬢さん』(2016年)も映画館で観た時、喜びで震え、後半ずっと号泣でした。私はずっとジェーン・カンピオンの『ピアノ・レッスン』(1993年)を愛して生きてきたのですが、彼女の後に28年ぶりに女性監督がカンヌ映画祭のパルム・ドールを獲った『TITANE/チタン』(2022年4月1日日本公開)も、女性監督がたどり着いた一つの境地だと思いました。監督のジュリア・デュクルノーはインタビューで、「ステレオタイプを見たら殺そうとしている」と言っているのですが、あらゆるステレオタイプを避けるように、揺れ続け、固定されない物語のつくり方がとても刺激的な作品でした」

――挙げていただいた作品も、松田さんの作品も、既存の価値観に阿る社会に対しての批評性を持っています。そうした創作物は社会にどのような影響をもたらすと思いますか。
松田「やっぱり毎日目に入る創作物の影響は大きいですよね。日本はジェンダー感覚が古いまま、コマーシャルやテレビ番組がつくられている場合も多いですが、自分の原体験として、100パーセントそうかといえば、そんなわけもなく、心に残る作品はいくつも思いつきます。
女性が出世、なんて笑い話だった時代に、女性の出世を描いた『悪女(わる)』は原作の漫画もドラマも本当に面白かったし、『カバチタレ!』『きらきらひかる』『七人の女弁護士』などなど、女性たちが協力しながらあらゆる問題に立ち向かっていく作品は当時からあったので、そういった作品をテレビで見ることができた、というのは大きなことでした。サブリミナル効果と同じで、目に入るものが人々の意識に浸透し、それが社会を形づくっていくので、これまで生きづらかった人たちを救う、既存の価値観を揺るがす作品が増えることは大切なことです。ずっと言われていることですが、作品や広告などをつくっている人たちは、そこに対する意識を常に持たないといけないと思います」
――政権や会社の組織図を見ても意思決定者が男性ばかりだと、その地位には女性はつけないような誤った認識を与えてしまうのもその一環です。
松田「それが社会なんだ、そういうものなんだと思って育ってしまいますよね。ニュース番組やラジオ番組でも、メインキャスターは男性で、女性は基本的に横にいて、進行で入るだけで自分の意見を言わないようにつくられている番組が多い。そういうところから変えていくべきなのに、そこを怠っているのではないかと感じることが多いし、多分変わらなくていいと思っている人も多い。だからこそ既存の社会を壊す力を持つ本や映像作品がこの世界にさらに増えて、それらに出会うことができた若い人たちが、大きくなって社会を変えられるような良い循環をつくっていかないといけないですよね。大人ももちろんですが。そのためにも良い作品が過去のものになってしまったり、絶版になってしまったりして糸が切れてしまうことがないように、上の世代が下の世代に本を贈ったり、情報を提供したりして維持することも大切ですね。たくさん好きな本はありますが、今私がパッとおすすめするなら、石井桃子『幻の朱い実』、ジャネット・ウィンターソン『オレンジだけが果物じゃない』、アーザル・ナフィーシー『テヘランでロリータを読む』、キム・ホンビ『女の答えはピッチにある 女子サッカーが私に教えてくれたこと』、フランシス・ハーディング『嘘の木』などでしょうか」
――おっしゃるように作品は時代、世代を超えて残るものなので、変化の芽として重要ですよね。『82年生まれ、キム・ジヨン』も、友達同士でプレゼントしてベストセラーになって韓国社会を動かしました。松田さんも『持続可能な魂の利用』で「おじさん」のいない未来図を描き、『自分で名付ける』で育児にまつわる従来の慣習や価値観とは異なる文脈を拓かれています。
松田「最初にお話しした通り、幼い頃から“普通”にできなかったので、それが続いているだけなんです。あと、世の中で有名だったり、大きな賞を受賞したりしている作品を読んだり見たりしても、自分的にはぴんとこない、という経験がたくさんあったので、社会で評価されていたとしても、自分にとってそうじゃないものに興味がないんですよね。なので、自分が小説を書く時に、評価を既存の文学の世界に求めなかったことが私を救ってきたと思います。この前、SNSである日本の男性批評家が、私の作品を評価しない、と言っていた、というようなことが書かれているのが偶然目に入ったんですが、それを見て、この人に評価されたいと思ったこと一度もないな私、と思って。ショックとかは一切なく、全然評価されたいと思ってなかった、よかった、と清々しく気づくことができました。それは生活も一緒で、今の社会に自分の評価を求めないという生き方をすることが結果的に自分を救っています。今の社会で認められる=男性に認められる、ということだったりもするように、文学の世界もいまだすごく男性的な場所だと感じますし、ひどいこともおかしなことも多々見聞きするので、極力関わらずにいかに生き延びるかということを考えてきました。そうすると、経済的な不安に直結するのですが、そういった時に、もちろん皆さんはそんな私の気持ちは知らないのですが、主に女性誌など、さまざまな媒体がエッセイや書評の依頼等を定期的にくださったことで、なんとかやってこれました。そのことに本当に感謝しています。そういえば、ほとんど依頼されたことのない女性誌があるのですが、その理由が、ライバル誌で私がエッセイの連載をしているからだと最近聞いて。別に私に依頼がないのはいいのですが、ライバルとか、そういう考え方はこれからの社会にとっていいことが一つもないので、もう本当にやめたほうがいいと思いました。「あなたは強いから」とか「フリーランスだから」とか「偏屈だ」とか言われることもあるんですけど、強いのではなくて、そうじゃないと自分を守って生きてこられなかったし、これが私の必死なんです。なのでそういう風に言われると、やっぱりちょっと悲しいというか、遠い目になりますね」

――そのように自分自身の視点を持ち、今の社会に自分の評価を求めないことが松田さんを持続可能にしている。
松田「その考え方をつくってくれたのも、やはりいろんな本を読んできたことだと思います。好きな本の中に出てくる他の本を数珠つなぎに読んでいったり、翻訳の作業をしていても、あらゆるものについて調べないといけないです。読書を通じて“調べる”ことが日常の中にありました。そうすると1つのことを提示された時にそれが絶対じゃないとわかるんですよね。物事の多面性を予めわかっているので、結果に飛びつかずに慎重でいられる。『持続可能な魂の利用』は、アイドルにまつわる構造と日本社会の女性の置かれた構造が同じだ、とある時気づいて、重ね合わせて書こうと思ったのですが、そういうマッピング能力も読んでいる過程で培われたもので、日常にも仕事にも活かされています」
――最後に、松田さんの短編にしても長編にしても、自分が感じていることや体験したことが描かれているように思えて驚くことがあります。「私」の物語を「私たち」の物語とするために、どのようなことを心がけていらっしゃいますか。
松田「物語の中に自分がいない作品を書かないようにしています。『持続可能な魂の利用』に出てくる小さいエピソードなどは、その頃の数年間で自分が実際に居合わせたり、経験したりしたことのある物事を意識的に入れていますし、やはりそもそもは自分のために書いているところがあるので、作品を通していかに自分が生きていける世界をつくるかが大切です。アナイス・ニン(フランスの作家)が、「作家は自分が生きられる世界を創造しなくてはならない」というようなことを言っていて。親たちの世界とも、戦争の世界とも、政治の世界とも違う、自分自身の世界をつくらなければならない、と。ある時、その言葉を知って、私がやろうとしていることはこれだと思ったんです。あと、最初の作品集『スタッキング可能』が刊行された後に、今「エトセトラブックス」を経営している松尾亜紀子さんが、「(この本を読んだ)私の周りの女性たちがみんな喜んでます」と言ってくださって。それも一つの指針となっていて、これからも、彼女たちが読んで「今回もよし!」と思ってもらえるような作品を書き続けたいと思っています。自分の中の声をまず大事にして、そこから交信するように誰かの声と繋がっているような気持ちで書いています」
photography Mariko Kobayashi
text Ryoko Kuwahara
松田青子
『持続可能な魂の利用』
(中央公論新社)
https://www.chuko.co.jp/tanko/2020/05/005306.html
『男の子になりたかった女の子になりたかった女の子』
(中央公論新社)
https://www.chuko.co.jp/tanko/2021/04/005427.html
『おばちゃんたちのいるところ』
https://www.chuko.co.jp/bunko/2019/08/206769.html
松田青子
1979年、兵庫県生まれ。同志社大学文学部英文学科卒業。2013年、デビュー作『スタッキング可能』が三島由紀夫賞及び野間文芸新人賞候補となり、2014年にTwitter 文学賞第一位。2019年に短篇「女が死ぬ」がアメリカのシャーリイ・ジャクスン賞短篇部門の最終候補に、2021年に『おばちゃんたちのいるところ』がレイ・ブラッドベリ賞の候補となったのち、ファイアークラッカー賞、世界幻想文学大賞を受賞。その他の著書に『英子の森』『持続可能な魂の利用』『男の子になりたかった女の子になりたかった女の子』『女が死ぬ』、翻訳書に『狼少女たちの聖ルーシー寮』『レモン畑の吸血鬼』『AM/PM』『問題だらけの女性たち』『彼女の体とその他の断片』(共訳)、エッセイ集に『ロマンティックあげない』『じゃじゃ馬にさせといて』『自分で名付ける』などがある。