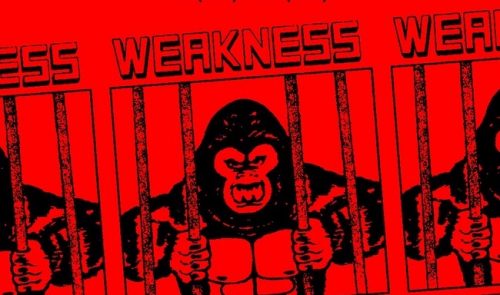東京・中目黒のマンションをシェアして暮らす、堤小春(三吉彩花)と清川彩乃(阿部純子)の四季を映した『Daughters』。イベント演出家とアパレルのプレスという職業の近さからも、自立しながらも互いに頼れる友人として快適な暮らしを続けていた二人の生活は、彩乃の突然の妊娠によって変化していくーー。過度にドラマティックな演出や旧態依然とした価値観を押し付けるキャラクターを排し、淡々と二人の人生、そしてその選択を描いた本作は、女性を祝福し、こんな生き方もあるのだとその重荷を取り除くのではなくともに分かち合うような、まさに2020年という今の作品だ。脚本、監督を手がけた津田肇、そして過度な演出がないがゆえに一層際立つ主人公二人の空気感や関係性を何ひとつ損ねることなく自然に、繊細に演じた三吉彩花と阿部純子に、制作のプロセス、想い、現在の女性を取り巻く状況についてまでを聞いた。
――いまの価値観がしっかりと反映された女性を祝福する映画です。本作は監督ご自身の経験がもとになっているそうですね。
津田監督「22歳から29歳まで7年間の個人的体験が凝縮されています。友人たちと6年くらいルームシェアをして、その直後に結婚し、子どもができたという。その体験を女性二人という形に置き換えたのは、今は女性を描いた方が圧倒的に面白く、新しいものが生まれそうな気がしたからです」
――着想から制作というプロセスを経る中で、作品の中でブラしたくない、もっとも大切にしたい魂のようなものがあったとしたら教えていただけますか。
津田監督「難しい質問ですね。脚本を書いてから撮影まで5年ほどあったのですが、僕自身も色々生きることに対しての価値観のアップデートがありましたし、それに伴い作品の核が変わっていったりもしたんです。だから“絶対にここはブラさない”みたいなことは逆になくて、アップデートに従って脚本も直しました。書き始めた頃は“傍にいる人を大切に”というようなわりとミニマルな友情の話だったけど、時間が経つにつれて“生きるとは”とか“輪廻”みたいなことをもう少し反映していきたいなとぼんやり思っていたんです。それがCOVID-19もあってまた“傍にいる人を大切に”という意識に戻っていったり」
――三吉さん、阿部さんは脚本を読んだ時にどのような第一印象を抱かれましたか。また、それぞれの役を演じるうえで、どのようにして監督と共通の視点を築いていきましたか。
三吉「私はフランスの映画が好きなのですが、脚本を読んで、ストーリー自体はそのニュアンスに近いものを感じました。ですが、この脚本の中に描かれているものが、自分たちが立体的に演じることによってどうなるかという想像があまりできなかったです。そのどういう風になるのかわからない感じをむしろ楽しみにしていました」
阿部「女性の心の動きが繊細に丁寧に描かれていて、私自身も女性であるはずなのにそのセンシティブな感性に驚かされるというか、最初に読んだ時はそういった印象を受けました。役作りに関しては、まだリハーサルとかもちゃんとしていない、しかも三吉ちゃんともそんなにたくさんお話をしていない最初の段階で、『私たちが暮らしているアパートに二人だけで行ってみない?』という提案を三吉ちゃんがしてくれたんです。その時間が映画を作る前段階においての安心感というか、三吉ちゃんとだったら小春と彩乃で発信できるという確信になったと思います。監督もそれを了承してくださいましたし、私たちの関係性を尊重してくださったように私は思います」

――お二人の信頼関係が本作の一番のポイントですが、あの自然な雰囲気はそのようにして生まれていたんですね。
三吉「各々の役というより、二人がひとつ屋根の下で一緒に暮らしているその空気感や関係性を監督も含めてみんながとても大事にしていて。クランクインする前に家で1日を過ごしてご飯を食べたりしたのも、なるべくお芝居を演じている感じにしたくなかったからなんです。よく見れば見るほど繊細で、細い心の動きみたいなものがたくさんある話なので、自分たちがそこにいるだけで彩乃と小春になるようにするにはどうしたらいいかと考えていったら普通に家で過ごすこと、その家で一緒に過ごすことが一番だなって」
阿部「一緒にずっと名前を呼びあっていたよね」
三吉「そうね。彩乃、小春って。現場に行くときも普通に家に帰ってきたようなテンションで行って、今日は撮影だ、よしやるぞという感じにしない。何も考えないようにして過ごしていました。セリフも、一言一句その通りに言うことよりちゃんとその時々で相手の芝居を受けて、ニュアンスは変わらないようにするけど気持ちで受けて喋るということを大事にしているので、よりナチュラルに感じてもらえるのではないでしょうか」
津田監督「照明の演出や部屋の内装などでは非現実的なことをやろうと思っていたのですが、演技やお芝居はちゃんとリアリティを出していかないといけない。だからセリフはそのままでなくていい、自分の言葉に置き換えてもいいと伝えていました。僕は嫌われてもいいからこの二人だけは仲が悪くなってほしくないというのは撮影に入る前から思っていて、『純ちゃんとご飯に行ったんです』と聞いて、『ああ、本当によかった!』って(笑)。そんな感じでした」
――(笑)。作中の二人は東京で働く自立した女性であり、お二人も東京という街で働く女性ですが、本作との出会いを通し、この街で女性として生きる、働くということについて考えさせられたことはありますか。また、それらを監督へフィードバックなどされましたか。
三吉「私はあまり自分とは照らし合わせなかったです。わりと最初から彩乃と小春でちゃんと二人がそこに存在していたので、自分自身のニュアンスは入れたくなくて消していました。自分は自分で、小春は小春で考えて。ただ小春を演じている期間は基本的に自分のスタンスがずっと小春だったのであまり違和感なくできたのですが、改めて完成した映画を観て、こういう人生もいいなあと思ったんです。やっぱりこの二人の関係性ってとても特別なものだし、そこに新しい命が宿って、二人だけではなくなる。彩乃にとっては自分一人だけの人生でなくなったところから誰かに頼ったり、お互いに頼りあったりーーそういう誰かに頼ったりちゃんと傍で支えてくれる存在がいるという安心感。自分が演じた作品は、どうしても最初にお芝居を気にして観てしまいますが、この作品に関しては、『この人たちの人生、この関係性って素敵だな』って、自分が演じてない全く別の映画のような気持ちで観ることができて、それは不思議な感じがしました」
阿部「私は東京で暮らしている中でいろんな選択肢があるんだなということに気づいて、自分自身についても考えさせられました。彩乃はバリバリ働きながら子どもを産むという決断をするわけですけど、シーンでもあったように、妊娠の報告をした時の会社の中での反応や、もといた役職から外れないといけなかもしれない局面に陥ります。そういった、女性にとっての働きやすさを考慮しきれていない環境って、社会全体から見たらその潜在力を活かせていないのかなと感じるところがあって。ワークライフバランスを考える上で、その選択肢はより多い方がいいから、どうやったら選択肢を増やせるんだろうなという風に考えました。撮影中に『82年生まれ、キム・ジヨン』を読んでいたのですが、それについて監督にお話しした時に、監督も『確かに女性の働き方や人生の選択の仕方はこれからたくさん増えていくと思うし、正解は一つじゃないよね』とおっしゃっていたことを覚えています」

――私は彩乃は元の役職に戻る気だと思っていますし、その選択肢がない社会はおっしゃるように未来や可能性を狭めるもの。この作品の延長である社会ならば彼女は戻っていると思います。
津田監督「そうですね。僕も戻ると思ってます」
――選択肢というお話が出たので、監督にお聞きしたいのですが、本作の価値観や彩乃の性格、生き方からしたら避妊の主体性を人任せにしないと思うんです。だから低用量ピルを毎日飲むなり、なんらかの主体的な避妊の方法をとっているはず。そこが描かれていないのは、ある程度意図的に妊娠の可能性を選んだと思っていいですか。そうでなければピルの飲み忘れのシーンがなくては納得がいかなくて。
三吉「確かに女性でピルを採用している人は多いですよね。リアルな意見だと思います」
津田監督「その話は脚本初期の段階からあって、彩乃には妊娠してもいいという意思はあったと思うんですが、曖昧にしたくもあって。だからその前後の会話も全部省いているんです」
――避妊の主体性に関しては本当は曖昧にしてほしくないんですが、ひとまず引き下がります。産婦人科のシーンには感銘を受けました。白々しくなく、カーテン越しじゃなく彩乃が自分の身に起きていることを目撃しているところにもアップデートを感じましたし、そのような小さいけれどしっかりとしたリアルが日常と離れた虚構に見えないベースを積み上げていて。
津田監督「カーテンをつけるかどうするかという議論もしたのですが、産婦人科の先生が、つけなくてもおかしくはないということでつけませんでした。そもそも僕の妻が通っていた産婦人科の場合はなかったんですよ。基本的にはファッションイベントの演出という仕事を続けながらの制作だったので、かけ離れたものではなく、取材がなくても書けるような身近な題材がメインになっていて。小春の仕事は僕がやっている仕事だし、彩乃の仕事は妻の仕事です。でも産婦人科の部分だけはちゃんとやらなくてはと思って4軒の取材に行き、その中で一番最先端だと思うものをピックアップして採用しています」

――妊娠出産というライフイベントはあるものの、この作品はアップダウンが激しいドラマティックな演出がないのも特徴で、そのぶん表情での演技が要求されています。三吉さんはそのまま小春でいたということですが、阿部さんは妊娠する役所でもある中でリアルさを保つために大切にしたことはありますか。
阿部「二人の女性が妊娠をきっかけに関係性が揺れ動いていくところが大きなテーマの一つだと思うのですが、妊娠という自分では経験したことがないことを演じることに最初は不安や緊張を覚えました。でも監督からたくさんの資料をいただいたりお話をうかがっていく中で、女性の揺らぎは人によってそれぞれ本当に違っているものなんだなと気づいて、それからは少し楽になりました。例えば手が痺れるシーンでも、それが一体どれくらい痺れているのか、その苛立ちはどんな感じなのか、経験されてる方がいらっしゃるのに自分はこれで本当に大丈夫なのかという迷いがあって、監督にわからないと感じたことは正直に相談しました。だからこそ、実感を伴わないことへの戸惑いや葛藤を役にも活かすことができたのかもしれません。彩乃自身の変化していく身体に焦る気持ちなど、複雑な心情を織り交ぜる演技につながったんじゃないかなと思っています」
――先ほど三吉さんもおっしゃったように、新しい家族や人生の選択肢もごく自然な形も描かれていて、こういう人生もいいなと思える2020年の作品です。制作するにあたって参考となった作品や本などはありますか。
津田監督「特にないです。『82年生まれ、キム・ジヨン』など、この5年くらい韓国も含めて世界的に女性を主導とした動きがあるということはキャッチしてるんですけど、それをこの映画で無理に反映させようとは一切考えなかったですね。でも、自分に子どもができて子育てをするとなった時に、女性の社会進出がどうと言われているけど、社会における男性の価値観が遅れているということはとても感じました。社会というより旦那さん、男性を変えていくべきという苛立ちはあって、そういうのはなんとなく反映させたりしています」
『Daughters』
9月18日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開
公式HP : https://daughters.tokyo
ストーリー:中目黒。桜が並ぶ川沿いのマンションの1室で暮らす友人同士の小春(三吉彩花)と彩乃(阿部純子)。共に27才。ライフスタイルの似ている二人は、よく働き、よく遊び、自由を謳歌したルームシェア生活を送っていた。そんな生活に、変化が訪れる。突然、彩乃からの妊娠の告白。そして、父親のわからないその子供を、産む決意をする彩乃。楽しかった二人だけの生活は、少しずつ変わっていく。過去を振り返りながらも変化を受け入れる彼女達を、小春側の視点で描く、苦くも美しい10ヶ月の物語。
脚本・監督:津田肇
出演:三吉彩花、阿部純子、黒谷友香、大方 斐紗子、鶴見辰吾、大塚 寧々
©「Daughters」製作委員会
公式Instagram : https://www.instagram.com/daughterscinema/
公式 Twitter : https://twitter.com/daughterscinema
公式Facebook : https://www.facebook.com/daughterscinema/
Ayaka Miyoshi
Jacket , dress BELPER/Inner tiit tokyo
others stylist’s own
Junko Abe
dress , tops . skirt tiit tokyo
others stylist’s own
photography Yudai Kusano
hair&make-up RYO
styling Miki Takanashi
text & edit Ryoko Kuwahara