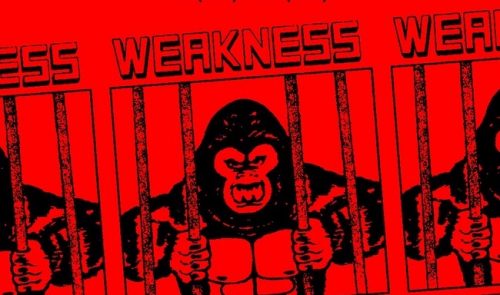夏目漱石は癇癪持ちだったと知ってから、それを慰めとしてきた。あれほどの人が、家庭の中では不機嫌で横暴にしていたのだから、自分程度の人間が、たまに怒るのは仕方ないのだと。
いつのもようにきっかり17時に店を閉めると、外のテラス席に座り、コーヒーを飲みながらぼんやりとオホーツク海を眺めた。夫は1時間ほど前にすでに斜里へと出かけてしまった。戻る時間を伝えなかったのは、いつものことだが、おそらく21時には戻るだろう。それもいつものことだ。
喧嘩はいつも些細なことが発端になる。あとで気恥ずかしくなるのだが、その時は無我夢中で怒ってしまうのだ。結婚して12年になり、ほんの数日前に記念日を祝ったばかりだというのに、どうして喧嘩を無くせないのだろう。人間は成長するものではないのか。
夫の気さくさは、本来愛すべき長所なはずだ。馴染みの客が来たら1時間ぐらい話し込むこともあるだろう。だが、小さな店とはいえ満席になったら、私一人では捌ききれない。そういうことを夫も分かっているはずなのに、話に夢中で、私が右往左往しているのに手伝ってもくれなかったのは、やはり夫の非ではないか。
だが、私も怒りすぎたのだ。客が引けたあとで、大声で罵倒することはなかった。これもいつものことだ。仕方がない。癇癪持ちなのだから。
北海道の夏は短いと誰もが言う。きっとそれは間違いではない。一年の半分が雪で、春と秋と冬とが残り二ヶ月ずつだという冗談があるくらい夏は短い。
私たちが二人で知床にやって来たのは、今年の五月。コーヒーショップを継いでくれないかと打診されたのが、去年の暮れだったので、塾考できたかどうかは疑わしい。
春には一人娘がオーストラリアのパースに留学するので、身軽になるのを見越しての決断でもあった。
北海道か沖縄にいつかは住んでみたい、という夫婦の共通の夢の実現が突然現れたのだから、戸惑いつつも胸は高鳴った。ああ見えて慎重派の夫は、連日ネットとにらめっこをし続け、最終的には私が決断を促した。別に死ぬわけじゃないし、契約期間も特になく、ひとまず店を継げばいいだけじゃない、飽きたら頭を深々と下げて詫びればいい。そんなことを声高に言って夫を納得させた。
実際リスクは皆無だった。私たちよりもちょっと年下の夫婦が10年続けたコーヒーショップを、親の介護のために一旦退かなくてはいけなくなり、復帰するまでの間、家賃も何もいらないから住み込みで入ってほしいということだった。その間の売り上げや損失は私たち夫婦の働きにかかってくるというだけ。

夫はもともとグラフィックデザイナーであり、私はイラストレイター。お互いに、そんなに羽振りは良くなかったが、細々とどうにかやってこれた。ネットさえあれば、どこに暮らしてもそれらの仕事は継続できるし、コーヒーショップの売り上げもちょっとは期待できるので、悪い話ではなかった。なにしろ北海道の中でも、手つかずの自然が最も残っているといわれる知床に暮らせるチャンスなんてそうあるはずがない。
私は、短い夏の真っ只中にある八月のオホーツクを眺めながら、コーヒーを口に含み、知床に住むに至った経緯を反芻しながら、ゆっくりと喉から胃へと流していった。
千葉の幕張からの東京湾の眺めも悪くはなかったが、やはり自然の懐の奥行きが、ここでは怖いくらいに美しい。今こうして眺めている視野のどこかにはシャチがいて、アザラシがいて、カニがいて、昆布が揺れ、冬になれば流氷がシベリアからやってくるのだ。私は確実にその接点で暮らしている。そう思うと、ありきたりだが、さっきまでの激昂が次第にしぼみ、馬鹿らしくなってきて、夫の不在を寂しく感じ始め、早く帰ってこないかなあと待ち侘びたりするのだ。この夕暮れの美しさは一人で鑑賞するには大きすぎる。時刻は17時23分。21時までは、あと3時間半もある。カレーを食べて、ビールを飲んでも、持て余してしまう。私はオホーツク海に向かって小さなため息をついた。
よし、どうせなら、それまでの間、怒りについてしっかり向き合ってみよう。漱石が癇癪持ちだからって、私までそれに習うことはないはず。せっかく千葉から北海道に移住したのだから、私も何か変わりたい。怒ることから卒業して、もっと楽に生きるべきだ。オホーツク海は穏やかだったけど、私は妙な高揚感に包まれて、試合前の選手のような感じだった。
とは言っても、いったい何から手をつけていいやら。確か本があったはず。このコーヒーショップの書棚は実に充実していて、読書家のオーナーの選書は、多分野に渡っていたが、どれもツボを得ているものに違いなく、その中に、怒りについての背表紙があったはずだ。
私はコーヒーを飲み干すと、オホーツク海に一瞥してから、店内に戻り、カウンター席の横にある書棚の前にしゃがんだ。床から五段の幅2メートルほどのスペースにぎっしり詰まった文庫、新書、四六判、写真集、雑誌などに目を凝らし、「怒り」とう単語を見つけようとした。

確かに、怒りのしずめ方、怒りとの付き合い方、みたいなタイトルの本があったはずなのに、何度見返しても出てこない。時々常連さんが一声かけて借りていく。もしかしたら夫が受け持ったのかもしれない。だったら、なんでそれを私にも伝えてくれないのだろう。オーナーの本を大切にしようという気持ちがあったら、妻にもシェアしようと考えてもいいはずだ。もしくはノートを作るとか。私はオホーツク海を眺めておさまったはずの怒りが、またもやぐつぐつと煮立ち始めるのを感じた。だが、さっきの今だけに、さすがに客観視もでき、それを収めるために深呼吸を繰り返した。なにかの本に、気持ちが揺らいだら深呼吸をすればいいとあったからだ。
その甲斐あって、怒りはどうにか収まった。一旦、怒りから離れてしまうと、入れ替わって後悔と自責の念に包まれる。つまりネガティブな連鎖が始まるのだ。
私は再びテラス席に出て、オホーツク海を眺めた。わずか10分ほどの間に、闇がかなり近づいて来ていた。巨大な生物のような闇がその触手を私の方へ伸ばしている。私はその荘厳さに心打たれ、今日は終わるんだ、と当たり前のようなことをつぶやいた。
私は、それからしばらく、体の芯が冷え始めるまで、そこに立ち尽くし、自分が闇に覆われていくままに任せた。店内の電灯は全て消してあったので、秒刻みで世界の変化を感じることができた。
「ここにはアイヌだけでなく、北方の少数民族も暮らしていました。ナーナイ、ウイルタ。網走には有名な遺跡もあります。オホーツク文化と呼ばれたものがあったのです。国境がなかった時代の話です。その子孫は混血して一般的な日本人として普通に暮らしてます。差別の歴史があったので、あえて名乗ったりしませんが」
ある観光客が私にそう語ったことがあった。その時は特に興味も生じなかったが、今闇に包まれながら、なぜかその言葉が思い出された。そうか、私が眺めている海には、かつて船に乗った他の民族がこの土地にやってきて、根付き、暮らしたこともあったのか。野生の動物たちだけでなく、様々な人間もこの土地に暮らしていたのだ。
私の心は、急にしんと静まりかえり、もしかしたらこのまま泣いてしまうかもしれないと思った。40年も生きてきて、こんな風に泣いたことがなかったので、本当に涙が出てくるのかどうか、自分でもわからなかったが、とにかく泣きそうな感じだった。

その時テラスの端に白い大きな影が音もなく降り立った。微かに爪がテラスの木を掴む硬い音がしたが、それだけだった。
私は、その姿に身が凍りついたようになった。その生き物は、いつもそうしているかのような落ち着きで、海に面したテラスの木柵に留まり、こちらをじっと見つめた。私に怯えた様子もなく、どちらかといえば家来の仕草に目を光らす主のような尊大な態度であった。
図鑑の解説では、留まった時の体高が60センチほどもあり、枝にいる時の姿は人間の子供が膝を抱えて座っているのに似ていて、羽を広げれば2メートル近くに達するとあった。知床を中心にわずか300羽しかすでに残っていない絶滅危惧種だ。人里で目撃されることは少ないが、昨夜見たよ、などと言う客もいるので、いつかは見てみたいと夢見ていた。特に夫は大の鳥類好きで、動物園にはそれ目当てでわざわざ出かけるほどであった。
その瞳はなおもじっと射抜くように私の瞳を見つめている。私は瞬きもできずに、目を逸らさないようにし続ける。アイヌでは神様とされる鳥だけに、美しさを通り越した崇高な、気高な、なんといっていいか分からない神々しさがあった。一秒でも多く、この時間が続きますように。私は心の中で願った。
その時、店の駐車場に一台の車が入ってくる音がした。夫のものであることがエンジン音でわかった。早すぎる、と21時の帰宅を予想していた私が感じ、鳥を見つめるもう一人の私が、夫にも見せてあげたい、どうにかもうしばらくここに留まって、と願う。その間も鳥と私は目を合わせたままだ。
ガチャリとドアを開く音がする。私はそっちを見ない。鳥を見ている。鳥は微動だにしない。夫の帰宅すら予見していたかのように。
夫はテラスでじっとしている私を見つけ、大丈夫か?と店内から声をかける。夫からは鳥が見えていないらしい。夫が近づいてくる。私は夫を見ない。夫が静かにテラスに近づいてくる。そして立ち止まる。きっと鳥に気づいたのだ。私は嬉しくなって微笑んだ。その瞬間、鳥は音もなく中に羽ばたき屋根の上へと舞い上がり、どこかへ飛び去っていった。
私は、その行方を目で追ったあとで、ようやく夫を見た。夫は目を閉じ、手を胸の前で合わせ、シマフクロウがいたテラスの隅に頭を垂れていた。
#1 裏の森 はこちら
藤代冥砂
1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある。