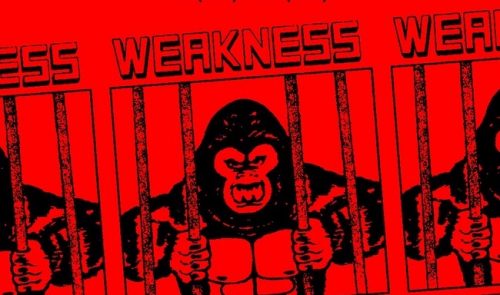全世界で120億円以上の興行収入を叩き出し、日本でも大ヒットを記録したBBCアース・フィルムズが贈るネイチャー・ドキュメンタリー『アース』(2008)。そこから10年の時を経て、第2弾となる『アース:アメイジング・デイ』が日本公開される。本作の監修を務め、『すごい動物学』『しくじり動物大集合』などの著書でも知られる動物行動学者の新宅広二に、映像クリエイターにして無類の動物園好きである野崎浩貴が、ネイチャー・ドキュメンタリーや動物園のあり方について、そして大人への入り口である“14歳”の頃からどのような道を歩き現在の仕事に辿り着いたかを尋ねた。
野崎「動物ドキュメンタリーは色々観たのですが、『アース:アメイジング・デイ』には大型の動物から昆虫までが登場するのが特徴だと思いました」
新宅「本作を製作したBBCは世界トップクラスのイギリス公営放送局なんです。最初にTVチャンネルを作ったのもBBCで、NHKとタッチの差で先に始めました。そんな歴史がある放送局が、ネイチャー・ドキュメンタリーを設立当初の70年近く前から製作している。つまり、昔からメディアの大事な作品としてネイチャー・ドキュメンタリーがど真ん中にあるんです。本作を製作するにあたっても、昨日今日ではない歴史があるからこそ作れるものになっていますし、撮る技術というもの自体を面白がって考えながら撮っていますよね」
野崎「カヤネズミのところとか、よくこんな近くで撮れるなというシーンもありましたよね。ああして活発に動いている姿はなかなか見れないので興味深かったです」
新宅「大きい動物は撮影が簡単なんですが、小さい動物、特にネズミは近寄るのが本当に難しいから、そこに着目したのはさすがですね。撮影はカメラマン一人で近寄っていくわけではなく、何十人単位のクルーで動いているのですが、その中で臆病な小動物を撮れることでスタッフのレベルの高さがわかります。BBCのスタッフはケーブル捌きをしているアシスタントでも博士号を持っていたりするんですよ。専門家がついてスタッフに指示するのではなく、ファインダーを覗いている人自身がその動物が次にどの動きをするかをわかっている。だから、本作でも動物が常に画面の真ん中にいます。他の局が撮ったものは動物を追いかけてしまうのでどうしても真ん中に収まらないし、長回しして何かいい画が撮れたら使おうという感じですが、BBCは絵コンテまで事前に描くんです。動物の習性を踏まえてこういう感じの画を撮りたいと、偶然ではなく狙って撮る。だから、観ていてもストーリーがあるんですよね」

野崎「ナマケモノが別のナマケモノに会いに行って、振り返ったら子供がいるシーンなんかもオチがあって面白かったです(笑)」
新宅「あそこは良かったですね(笑)。作る側にもそういうクスッとさせるものを作る余裕があって、それがまたゴージャス感を際立たせているんだと思います」
野崎「あと、“かわいい”にフォーカスしすぎないのも良かった。“かわいい”というところから動物に興味を持つのは良いことだと思うのですが、あまりにキャラクター化しすぎることには抵抗があって……必死に生きている動物をかわいいだけで片付けるのはどうかなって。この作品では命がけで生きているウミイグアナのマッドマックス顔負けの場面をカメラにおさめていて、そういうところも素晴らしかったです。蛇とウミイグアナのシーンでも、普通だったら蛇を怖い存在として描いてウミイグアナを観客が応援する構図を作るじゃないですか。でもイグアナを食べようとした蛇も失敗して落ちていくところを映すことで、どちらがどうではなく同じ必死に生きている生き物として見ることができる」
新宅「日本は良くも悪くも“かわいい”と“かわいそう”の2チャンネルが特化しがちですが、文化的にこの作品のようなものを見慣れているイギリスの国民性とその期待に応える作り手というところからできる作品は手応えがあります。スタッフがこういう場面を沢山見続けているので、どの動物が一番だとかかわいそうだというようなことが世の中にはないと理解しているんですよね。毎回切り口もBBCが考え出した最先端のもので来るのでとても楽しみなのですが、この作品は1日24時間の中で同時に地球上で何が起こっているかという、ありそうでなかった視点を突いていて。海の中やアフリカやアジアという別の地域で時間が進んでいっているのを同時に映しだす見せ方ですが、時間という単位で動物を描くのは新鮮でした」
野崎「モンカゲロウだったら寿命が短いので、1日の中でいかにメスを見つけるかが重要だったり」
新宅「そうなんです。私はこれを観て、なんとなく“独りぼっちじゃない”と感じました。今どこかでこういうことが起こっているんだと気づかされますから」

野崎「ヒカリキノコバエも多摩動物公園でも見られますが、こんなに凄い映像だと動物園で見る遠くの方にポツポツと光るヒカリキノコバエの幼虫とはまた違った見え方で。そのあたりでは、動物園の存在意義を考えさせられました。野生の動物とは別に、動物園の良さもあるし」
新宅「動物園が嫌いな人は檻が嫌いということではっきりしていますよね。牢屋のようなイメージだからだと思うのですが、それは誤解で檻は心理的に動物を守るものなんです。檻があることで人間がこちら側に来ないと動物たちに伝わるので、見られている中でも眠ることができる。最近よくあるアクリルの塀はむしろ動物にとってはストレスになってしまい、前を通るだけでバッと起きてしまう」
野崎「お堀はどうですか? ハーゲンベックが考えた展示(無柵放養式展示、堀を使用など。ハーゲンベックは19世紀のドイツの動物園・サーカスの園長の名前)ですよね?」
新宅「“ハーゲンベック”をご存知とはさすが(笑)! お堀は最高です。動物園側のテーマは、いかに檻を感じさせないかということなんですよね。どんな猛獣、仮に恐竜でも檻をガチガチにすれば飼えるわけですが、そんな物理的なものでなくともサイエンスを用いれば飼えるんです。跳躍力のない動物は上を囲わなくていいし、チンパンジーのような泳げない動物は水を一本引くだけでいいし、そうやって極力動物にとっても人間にとっても隔たりをなくしていければ同じ空間にいるような感覚になれますから、それが動物園側のテーマでもあり、考えるのが面白いところでもありますね。囲っちゃうと面白くないです」
野崎「もっと動物のスペースを広くした方が良いという声がよく出ますが、ただ広くしたところで動物は一箇所にしかいなかったりもしますよね」
新宅「それも檻=牢屋という誤解と同じで、広い方が動物にとっては圧倒的なストレスになってしまうんです。私たちだって東京ドームの真ん中で寝ろと言われても寝づらいじゃないですか(笑)。寝る時は隅っこのほうが落ち着きますよね。動物も同じで、運動するときは広いところが良いけれど寝る時や休む時は暗くて狭いところの方が安心します」
野崎「野生においてテリトリーのある動物もいれば、ホッキョクグマのように移動の多い動物もいますし、そういう特性に応じても今後も新しい展示法が出てくるかもしれないですね」
新宅「そうですね。動物園の人はもっとアイデアで遊んでいかないといけないと思うんです。動物愛護の思考ばかりだと今後行き詰ってしまうと私は思います。動物園は保護施設ではないですから、“生きた博物館”として教育的に面白がらせる必要がある。それはやはり遊ばないとできないですよね。例えば僕は今、猟師さんについて教えてもらっています」
野崎「え、猟師?」
新宅「動物園は条件付きで人が飼うという環境ですから、人に慣らすということをしていく中で、動物のやさしさや親子の絆に触れました。今は動物の一番面白いところである“本気を出したらどこまでいくか”というところに興味を持って、そこを知るために猟師の方に教えてもらっているんです。動物観が全く違っていて、“教科書に載っていた今までの知識は何だったんだろう”と衝撃を受けました。そういう違う側面からの知識もあるとまた発想が増えると思います」

野崎「なるほど。そもそも新宅さんは、動物園で働く前は、霊長類の研究をしていたんですよね? なんで霊長類学の研究をしたいと思ったのですか?」
新宅「アフリカに行きたかっただけなんです(笑)」
野崎「チンパンジーに会いたかったとか?」
新宅「そうです。実は僕は大学生まで動物園に行ったこともなかったし、昆虫採集もしたことがなかったんです。人並みに動物好きではあったけど、仕事にしたいとまでは思っていなくて。でも高校の時に母国語で最先端の勉強ができる学問は何だろうと考えたら、当時も今も霊長類学において日本は最先端をいっていて、欧米の凄い大学にいる人たちが日本に霊長類学を学びに来ているんです。それは欧米などキリスト教文化圏にはサルがいないからなんですが、国内で最先端の学問ができるというのがきっかけでこの道に入り、その流れで研究所に入りました」
野崎「大学内に動物園並のサル山があると聞いたことがありますが? 現在日本の動物園にはいないボノボもいたとか?」
新宅「当時、日本モンキーセンターに1頭オスが日本にいましたね」
野崎「ボノボはチンパンジーと違って、ケンカすると疑似交尾をしてケンカを落ち着かせると聞いたことがあります」
新宅「基本的に彼らは争いが嫌いで、唯一の共産主義的な動物なんです。例えば動物は基本的に食べ物を分け与えたりしません。子供が親の持ってきた食べ物を持っていくのを許すことはあっても分け与えている意識ではない。でもボノボは果物やサトウキビをパキっと折って仲間に均等に渡すんです。独り占めしない」
野崎「へえ! もともと分けるという意識があるんですね」
新宅「はい、“分配行動”というのですが、面白い特徴です。あとよく“一番いやらしい動物は人間”と言われますが、ボノボの方が凄い(笑)。自分の遺伝子を残すための〝交尾〟ではなくて、コミュニケーションのための〝セックス〟をします。研究者はユニークな生態映像をたくさん記録していますが、ちょっとテレビでは放映できないものも… …(笑)」
野崎「それは人間と同じ感覚でやっているのでしょうか? それともケンカを落ち着かせるためにやるのでしょうか」
新宅「僕の先生の説で感動したのが、生き物全てに共通する”異性を取り合う”、”居住地を取り合う”、”食料を取り合う”という3つの争いがありますが、ボノボは異性を取り合うことをせずに乱交型にすることで性の競争をなくしているというものです。ヒッピーのフリーセックスと全く同じです。そうすることで、食べ物を分配する余裕もできるんですね。異性の取り合いという強烈な柱の一つを廃して、落伍者が出ないようにする考え方に進化したのではないかという先生の説は僕も同意です」
野崎「ヒッピーでも好きな人ができたり嫉妬する人は出てくるじゃないですか。でもボノボに関しては貫いているんですね」
新宅「多少は嫉妬もあるのでしょうけれど、基本はそうです。同じ近縁種のチンパンジーは殺し合いをしたりしますからね。我々ヒトはボノボの系統の子孫ではなくチンパンジーの系統なので、チンパンジーの残酷性を持っているんです。僕が見た中で一番凄かったのは、権力争いでお母さんチンパンジーからオスがむりやり赤ちゃんを奪い取ってみんなの前で引き裂くといった映像がありました。見ていたチンパンジーも興奮し始めて、お母さんが死体のもとに行くのを喜んで見ているオスたちがいて。そうやって自分の力や恐ろしさを示すという、チンパンジーのダークサイドもあります」
野崎「人間もそういうのいっぱいありますよね……」

新宅「そう、他人ごとじゃない感じがします。チンパンジーのダークサイドを我々は引き継いでいて、だからこそいじめも戦争もダメだと言いながら見ていると興奮してしまうというのは残念ながらヒトの本能としてある部分です。人間の場合はそうならないように理性的に教育や文化的なもので負の部分を抑えていこうとしていますが……なかなかうまくいっていないようです。うっかりするとチンパンジーの残酷性が出てきてしまう。また、これも私の先生の受け売りなんですけど、動物はケンカや死闘はあるにせよ、基本的には殺すために戦っているわけではないんです。ルールがあって、一方が負けを認めるとそれ以上攻撃しないというのはほぼすべての動物に共通している。その一線を越えているのがヒトなんですね。相手を根絶やしにするとか、徹底してやってしまう。それで、過去にヒト以外の人類が17種類くらいいたのですが現在では他を根絶やしにした我々1種類しかいなくなってしまったんです。動物の中にもその残虐性はそうそうあるものではないです」
野崎「一つの犠牲で他の大勢が団結するみたいなことは本当に怖いし、自分がそういう大勢のうちの一人になってしまうことだってあると考えると怖いですね。研究所の後、動物園に勤務されたのは?」
新宅「初めて動物園に行ったのは大学の研究用に動物を借りるためだったのですが、そこで動物園には動物が生まれる瞬間から死ぬ瞬間までが全部記録されていると知り、“宝の山だ”と驚いて。動物園では動物を飼う仕事をするのではなく、一生を記録する仕事をしているんですよ。例えば大学の研究で野外調査でも、連続して観察できるのは3ヶ月とか、1年だったりします。だから動物像としては足りないパズルのピースが出てきます。だから、動物園で見た動物の一生の記録は、壮大なサーガで衝撃的でした。日本でも一番古い上野動物園に行ったので、凄い記録が整然と並んでいるんですよ。さらに、日本の動物園は欧米と成り立ちが違うことも知りました。欧米では博物館的要素が大きくて、自国では見られない動物を展示するという目的ですが、日本では戦後に本格的な動物園となっていくその経緯が敗戦と関係しているのです。終戦後、日本は焼け野原となって孤児が沢山いましたし、家族や大事な人を失った人も多くいました。そこで当時国策として、希望を失った子供たちのために公立の動物園を作ろうという世界でも他に類を見ない試みが実行されたのです。戦争で傷ついた子供たちのためという一点に力を注いで、世界で唯一子供からお金をとらずに運営したんですね。ふれあい動物園も日本が考えたもので、あたたかみや絆がベースとなっているんです。見世物のようでかわいそうだという意見もありますが、そういう安っぽいものではなく、先人たちの強い思いが込められている。戦争に対する先人たちのメッセージが動物園には強烈に詰まっているんですよ。世界一たくさん動物園がある国が日本というのは、そういった背景があるのです。
私は学校の先生もやっているのですが、大学のように、学費を払えて、一定の偏差値で、同じ目的で集まっている層の中で教えるのはそんなに難しくも面白くもない。でも動物園にはいろいろな人が来ますし、勉強するつもりではなくただ遊びに来たり、絵を描いたり、ただいるだけの人もいて。そんな自由な中でなにか学びを持って帰ることもできる教育的な場だと思うし、それが動物園で働きたかった理由でもあります。つまり、そこで働くということは学校の先生のような意識を持ってやらなくてはいけないですし、先達のようになにかメッセージを残すこともできる可能性があるのです。学校の先生になりたい方には、考えようによっては動物園でもそういったことができるわけです。専門用語をどうしたらわかりやすく伝えられるかなどを考える監修業にも通じるものがあるのですが、お勉強をお勉強と感じさせず、学校で学ぶ以上のものを持って帰らせるというのが僕がやっていることだと思います」

――最後に、“自分ならではの道”を選択し、歩んでいらっしゃるお二人におうかがいしたいのですが、振り返ってみて14歳の自分に何か一言残せるとしたらどんな言葉をかけますか?
新宅「何になりたいかではなく誰と出会うかが重要。運命的な出会いがあればその人が導いてくれますし、自分だけで運命は切り拓けないと思います。目指すことはもちろん大事なことですが、思ってもみないところで人生がドリフトしていくことがあります。私の場合は色々な仕事を転々としてきましたが、その時々でアドバイスしてくれる人がいましたし、人との出会いなしに良い世界には行けないような気がします。自分の意見だけでは小さい世界で終わっちゃうんじゃないかな。出会いは自分では作れないものだからこそ貴重ですし、アンテナを張ってビビッとくるものがあればそれに従ったり勝負をかけて良いと思います。私はそうやってきました」
野崎「僕はいま、会社員でもないし何の職業かもわからない状態なのですがーーー楽観的なことを言うと、凄く好きなことをずっと好きでやっていけば何かしらの形で繋がっていくことがあるんじゃないかな。例えば僕は小さい頃から映画を観ていて、14歳の時点では映画監督を夢見ていました。でも全く勉強ができなくて、高校にも受からないんじゃないかと危機感を感じていて、映画も好きだったけど作っていたわけでもなかったですし、とにかく特別なことは何もしていなかった時期です。大学も立教の映像身体という映画に関わる学科に入りたかったのですが、入試に落ちて、経済学部に入って。就職も権利処理というお堅い仕事に就いた。これにかけるということができない、ビビりなんですよね(笑)。でも経済学部に行っちゃったから自分の夢が終わったかと言えばそうではなかったし、一個一個の進路を真剣に考えすぎる必要はないと思います。あとは、自分で技術を磨いてできることもあるけど、僕の場合は人に助けられて好きなことをできているところがあるので、新宅さんもおっしゃっていたように出会いを大事に。もちろん出会いが全てではないし、迎合しろというわけではないですが、これだけ多くの人たちがいる中で自分と相反する人がいたとしても会って話を聞くのも良いと思います。だからといって一人がダメと言うわけではなく、一人も凄く大事です。誰かに話して解決する問題もあるけれど、ぼーっと動物を眺めながら考えることで解決するようなこともあると思うんです。僕がここまで頻繁に動物園に通いだしたのは、大学卒業と震災が重なったり色々なことがあって自分が何をやりたいかわからなくなってしまった頃です。もう亡くなっちゃいましたけど、井の頭自然文化園に当時はな子さんというアジアゾウ(享年69歳)がいて、そういった動物たちを見ていたらそれぞれの動物がそれぞれの動物時間で生きているということがわかったんですよね。生き物を見ることで物語が見えてきて、生まれてくる動物もいれば亡くなる動物もいますし、改めて死自体はドラマチックなものというより身近で当たり前なことだということもわかりました。急いでいた自分がばかばかしく思えてきちゃった。だから長い目で見て、とにかく一つ一つの決断に後悔したとしても悲観する必要はないし楽観的でいいと言ってあげたいですかね。でも60歳の僕は“いや、お前はあのときもっとこうしていれば良かった”とか言っているかもしれないし、わからないな(笑)」
新宅「(笑)。今度、一緒に動物園に行きたいですね」
野崎「ぜひ! 今日は本当にありがとうございました!」



『アース アメイジング・デイ』
https://earthamazingday.jp
11月30日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開
監督:リチャード・デイル、ピーター・ウェーバー、ファン・リーシン/プロデューサー:スティーブン・マクドノー/
製作総指揮:ニール・ナイチンゲール/音楽:アレックス・ヘッフェス/
脚本:フランク・コットレル・ボイス、ゲリン・ヤン/製作:BBCアース・フィルムズ
日本版ナレーター:佐々木蔵之介
2017年/イギリス・中国/94min/5.1ch/アメリカン・ビスタ/
原題『Earth:One Amazing Day』/監修:新宅広二
配給:KADOKAWA
© Earth Films Productions Limited 2017
新宅広二
動物行動学者。専門は動物行動学と教育工学で、大学院修了後、上野動物園、多摩動物公園勤務。その後、国内外のフィールドワークを含め400種類以上の野生動物の生態や飼育方法を修得。狩猟免許も持つ。大学で20年以上教鞭をとる。監修業では国内外のネイチャー・ドキュメンタリー映画や科学番組など300作品以上手がけるほか、動物園・水族館・博物館のプロデュースも行う。著書は動物図鑑の執筆・監修など多数。
野崎浩貴
映像クリエイター。ほぼ毎週動物園に通っている。
photography Shuya Nakano
text Ryoko Kuwahara