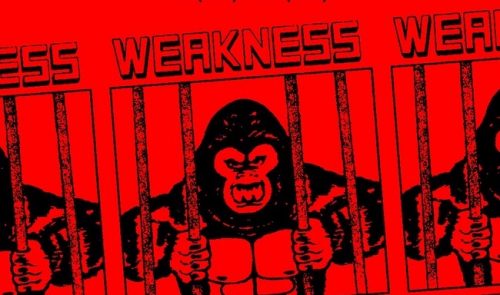自身の親族への聞き取り調査によって韓国から日本へ渡った移民の歴史や背景を紐解いた『家(チベ)の歴史を書く』(筑摩書房)などで知られる社会学者、朴沙羅。ヘルシンキに移住した彼女が大学で教鞭をとりながら2人の子どもを育てる中で見えた景色や聞こえてきた言葉を記した新作『ヘルシンキ 生活の練習』は、エスノグラフィー(行動観察調査)的な側面だけでなく、筆者が社会の中で問題に直面した際に様々な人々から提示された具体的な解決法や、解決するための糸口をどこに見つけるかといった視点や思考を読者が疑似体験することで、日常にもそれらの技術を活用できるように導く実用書としての側面も持つ。
――『ヘルシンキ 生活の練習』を拝読して、日本と異なる「個人と社会の前提」について考えさせられました。ヘルシンキでのお話をうかがう前に、朴さんがヘルシンキに向かわれた動機として「状況を変えたかった」「逃げた」と明確に書かれていることについて触れさせてください。息苦しい社会を変えるための動きが必要な一方、当事者が自分にとって好ましくない環境から離れるというのは自分を守る上で大切なことでもあると思うのですが、社会学者として、また個人の視点から「当事者になることを避ける」ことの大切さを聞かせていただけますか。
朴「前の職場の同僚でレイシズムやカルチュラル・スタディーズの研究をされている小笠原博毅先生(神戸大学)が、『社会学の良いところの一つに、自分のせいにしないことがある』とおっしゃっていたように記憶しています。もうちょっと広い言い方で、『周りのせいにする』だったかもしれないですけど、私はそれを聞いた時にとても納得したんです。ピエール・ブルデューの『ディスタンクシオン』でも、自分の才能や努力だと思っていたものがそうではなくて、親なりもっと上の代から受け継がれた資本であることが指摘されています。あるいは男であるとか都市圏に住んでいるとか、健常者であるとか、そういった様々な理由によって無数の下駄を履いて楽々世の中を歩んでいることについても、研究があります。そのように、ある意味で自分が自分の力でできていることはほとんどないと気がつくというのは社会学の大きな魅力の一つだと思いますし、社会学を勉強してきたものとして、その視点は常にあります。
そして私個人としては、子どもの頃からずっと当事者性を考えざるを得ない状況がありました。例えば名前が原因で韓国人だ朝鮮人だといじめられた時に、父が『それはイジメではなくて民族差別である』と言ったんです。ミクロに見ていけばもしかしたら私にも何か悪いところがあったのかもしれないけど、もし仮にそうだったとしても、お前のその行為は嫌だということではなく、朝鮮人はこうだという文脈にのせて言ってきた瞬間にそれは民族差別になる。向こうがそのように言ってきた以上、それはお前の責任ではないとパッと問題を変換した。本作の冒頭であのように書いたのは、同じような出来事が仮に私の息子なり娘なりに起こった時に、自分はあんなにうまく変換できるかということでした。できない不安があるのなら、組み合わせを変えた方がいいということです」
――そこからヘルシンキに移られてからの日々の出来事を、日本との優劣をつけないことを前提に書かれています。ヘルシンキではきちんと助けを求めない限り勝手には助けてはくれない一方、助けを求めたら具体的な解決策が提示されるなど、個が頑張りを背負わされすぎず社会や制度という構造が補完するようになっていることが読み取れました。以前、アイデンティティは他の人とのやり取りやその場の状況によって決まるとおっしゃっていましたが、他者の視点を常に慮る日本の社会と異なり、ヘルシンキのような他との距離感の社会では個のアイデンティティはどのように扱われているのでしょう。
朴「少し別の話になってしまうかもしれないですが、ヘルシンキでの授業で出会った学生たちは、セクシャルマイノリティであることや学習障害を持つことなどをとてもナチュラルに伝えてくるんです。カミングアウトということではなく、例えば自分は将来的にパートナーと同性婚をしたいけれど日本ではまだ難しいんですか、結婚できないとしたら事実婚の制度はどれくらい整ってるんですか、という感じで自然に訊いてくる。トランスジェンダーの学生が日本では手術を受けるのは難しいんですかと聞いてくるとか、学習障害がある学生が、パワーポイントを見ながら話を聞くことができないからパワポだけ24時間前にアップしてくれないかとメールをしてくるとか、自分自身のマイノリティ性を頑張ってではなく当たり前のように言ってくるんですね。
日本にいた時、私は在日の子からしかそういうカミングアウトをされなかったんですよ。本当はもっと多くの性的マイノリティや被差別部落出身の学生がいたはずですが、彼らはそれを言わなかった。日本だとエイヤッ! と頑張って言わなきゃいけないし、聞く側も悪いことを言って傷つけないようにとか、どうするのが適切な対応だろうかとか考えて構える。ヘルシンキで働いていて、そういう感じはしていません。なぜかというと、そこで差別的な発言をしたら間違いなく処分されるからではないかと思います。
2021年に話題になったニュースの1つに、キリスト教民主党の党首が、同性愛者に対して聖書の教えに反していると複数回発言をして、訴追されている事件があります。そうしたことが大きく報道されるし、差別的な対応をする人が問題なのだというコンセンサスがみんなにあって、実際そのように法律が動いている。そうすると、みんなが気軽に自分のことを話せるのではないかと思います」

――コンセンサスや制度が個人のあり方とも大きく関わってきているんですね。そうしたコンセンサスがある社会を作るには、当事者ではないアライ(性的マイノリティを理解支援する人々またはその考え)などの理解支援が前提にありますし、それぞれに違いを認め合うことが必要ですが、その前提はどのように作られているのでしょうか。
朴「“想像”や“共感”の練習はされていると思います。上の子の学校の授業に倫理教育というものがあるのですが、その内容というのが、最初の2ヶ月くらいはみんなで同じものを可愛がる練習をするんです。どうも10人くらいのグループになって、自分の大事なものを持ってきてそれについてみんなに話したりするらしいんですけど、そんな話を聞いたら相手に対する認識が変わりそうですよね。他にも、同じぬいぐるみをみんなが持って帰って一晩ずつ一緒に過ごして、次の日に自分がぬいぐるみと何をしたかを発表するということをやっていました。それそれの子たちが同じように可愛がっているのを知ることで、何かを大事にする気持ちはみんな同じなんだなという連帯感も育つし、それぞれ違う家庭で育っていることもわかる。7歳の子相手に難しい話をする前に、具体的な体験を通じて、他人に対して違うところもあるけど似てるところもあるという共感のようなものを実体験させていくという授業なのかなと思っています。
そもそも想像力や共感は持とうと思って持てるものではないですよね。具体的な練習が必要じゃないでしょうか。他人の感情に興味がない人は自分の感情にもすごく鈍感だから、まずは自分の感情に名前をつけたり、感情を言語化する練習をしていく。自分の気持ちを言語化したり、これが共感するということなんだという具体的な場面を複数回、作っていったりする練習をさせる。人形でのロールプレイができたら、それを現実の世界に応用するという具体的なステップを踏ませているのかなと思います。そうやって本人の中に“残るもの”にしていっている。そのように見えます。
まだ娘がその学年に達してないのでわからないのですが、いじめ教育などもどうやって行われているのかすごく興味があります。フィンランドでもいじめは深刻な問題になっているので、学校教育でとりあげないといけないんですね。個人の思いやりなどというレベルでなく解決するのなら、誰かの心持ちが悪いというようなことではなく、その状況に介入する方法を学び、状況を変えるようなやり方をするのではないかと想像しているのですが、その具体的な方法を知ることも参考になるのではないかと思っています」
――教育という面では「See The Goods」カードも印象的でした。個人が持つ良いスキルをカードで表現するというのは素敵な試みですね。
朴「本に書いた以外だと、最近、下の子のクラスでは、今週みんなが見つけたお互いの良いころをそのカードで表したりしてるみたいです。フィンランドでは人格は評価してはいけないと教育省から通達されているので、人格ではなく、あくまでスキルとして評価するんですよね」
―― 一概に言えないと思いますが、そのような教育の中でお子さんたちはどのように育っていると感じられますか。
朴「子どもたち二人の個人差がすごく大きいですし、年齢の違いもありますが、二人とも自分が何かをできないということはあまり言いませんね。ある意味で肯定感は高いという気はします。自分がダメなのではなくて、今これがたまたま練習が足りてないだけだと考えを変換するように教えてもらっているのではないでしょうか」

――その考え方は本当に重要だと思いますが、今の日本の教育は効率優先でそうした練習は削られる一方のように感じています。
朴「そうですね。私は博士課程1年の時にオーストラリアに留学したんですけど、そこで学内安全講座というものを受けてみたら、最初にやったのは大声をあげる練習だったんですよ。ものすごく広い敷地で、『みなさん、今ここで大声を出してください。もう一声! そんなんじゃ警備員にまで聞こえないぞ!』と、意外とスパルタで(笑)。その後はマップを見て最寄りの警備員さんの詰所まで走るんです。この体育会系な講座は何なんだと思ったんですが、練習してないととっさに大きな声は出せないわけで、やっぱり練習ってとても大事だなあと。私は普段、差別的な発言をされた時の対応も脳内で練習しているんですが、そうやって臨戦態勢をとっておくと加害性の高い人のターゲットから外れやすいような気もします。臨戦態勢のオーラが出ているというか。でも本当は、自分が頑張らなくてもよくなる方がいいに決まっているんですけどね」
――だからフィンランドでは差別的な発言は罰せられるという法制度がある。
朴「フィンランドでも、ある歴史の一時点で急にこうなったのではないと思います。日本の福祉制度の研究でよく言われるのは、70年代くらいまでは日本も先進国の標準か少し先行しているくらいだったのがそれ以降どんどん遅れていったということです。六辻彰二さんという方がヤフーニュースで書いておられましたが、保育園に入っている0、1、2歳児の割合と、親が受ける個人的なお金のサポート、それから税控除の3つが、今の日本ではものすごく低い。だから少子化して当たり前という議論でしたが、その六辻さんが引いておられるグラフを見たら、フィンランドと日本がほぼ同じところにありました(笑)。だからフィンランドでも少子化は問題になっていると言えるかもしれません。メアリー・C・ブリントンというハーバードの先生が、日本では例えば高校や大学から就職先など、ある場所から次の場所に100%移動して帰属することが大事で、この移動がうまくいかないと人生が大変になる、そういう意味で日本では“場”が大事だと指摘しています。日本ではうまくルートを歩めれば安定性が高い人生を送れるとも言える。フィンランドはもともと移民の送り出し国ですし、今でも失業率もほぼ7%と高いし、会社が倒産したり、クビになったりすることも当然ながら起こります。ある意味ずっとチャレンジし続けないといけない社会かもしれない。ごく限られた人間関係の範囲で見ているだけですが、ヘルシンキで出会う人たちの中にはけっこう仕事やお金の面でギリギリの橋を渡っている人もいるし、転職してガラリと業種が変わったりする人もいるし、この前フルタイムで働いていた人が全然違うところでインターンしていたりする。だから、日本とフィンランドとの間で優劣をつけるのではなく、違いを見たいなと思うんです。そして、この2つが全く違うとなると自分たちにはどちらかが縁のない世界に思えてしまうけど、そうでもないんだと、どちらも地続きにあるもので、コツコツがんばったらちょっとずつ変わるはずだと考えたい」
――諦めずに社会運動を続けるためにも。
朴「はい。この本で伝えたかったのは、具体的に変えられることはたくさんあるということです。いいなと思ったところに近づくのは、具体的な方法によって出来るはずなんですよね。人によるかもしれないんですけど、私は人間は生きていく上で社会運動に関わらざるを得ないと思っています。そして、日常は社会運動であり、運動はみんなでやるものです。日常生活の全ての場面は政治的な選択の中で出来上がっていると言えるので、あらゆる活動や発言、行為は基本的な社会運動になり得るはず。私は、日本では個人レベルで出来る運動はけっこう強いんじゃないかと感じているのですが、集団で何かをするとなると弱くなっている気がします。でも、世界には、いや日本にも、仲間をたくさん増やしてみんなで運動するスキルがあるはずなんですよ。スキルは小手先のものだと思われがちだし、実際そうなんですけど、精神のすごい深いところの変革を求めるとか、自らの立場性を心底から自己批判するみたいなところまでいかなくても、いろんなスキルの練習はできます。それでいいときもあるんじゃないでしょうか。右でも左でも、運動が仲間割れする一つの理由は人に求める期待が高すぎるということもあるはずです。みんな相手の精神性や人格に高いものを求めすぎているんじゃないかと。普通の人間関係で、そんな自分にも他人にも期待しなくないですか? スキルのレベルで折り合うことってたくさんあると思うんですよ。
私は学部生の時、慰安婦の方を日本に呼ぶという企画に関わっていたことがあって、大学1年生の時、その企画でいろんな学部の先生たちの研究室にカンパをもらいに回ってたんです。そのとき、いわゆる保守論客と呼ばれている先生にチラシを渡してカンパをお願いしたら、『君たちは私の書いたものを読んだかね』と。先輩が『それはそれとしてカンパください』と言ったら、その方は憤慨しながらも5千円くれました(笑)。政治思想の点で一致しててもカンパをくれない人もいるけど、政治思想の点で折り合わなくてもカンパはもらえるかもしれない。プラクティカルな目標がある場合、具体的に折り会えるところはあるはずなんです。確か外山恒一が言っていたと思うんですが、考えることも感じることも何もかも同じでないといけないのは、セクトだけです。ノンセクトならイシューごとに考えが別々なのが当たり前です。だから持続的に集合行動しにくいのかもしれませんが、でも、それはそれとして、人格ではなくスキルを見る方がお互いを嫌いにならなくて済むんじゃないかと思うんですよね。
最初の話にも通じますが、問題と自分は切り離せます。問題を自分の中に見つめてしまうと自分一人で対応するしかなくなりますが、問題の方を見れば、その問題を通じて自分以外の人とも協力できるはずなんです。当事者性にフォーカスすると誰にだって、凡庸で空虚な差別者にだって、当事者として語れる辛い事柄があるでしょうよ。だから辛さで勝負したって仕方ないじゃありませんか。お前の話をしてるんじゃないんだよ、問題を解決したいんだよって持っていきたい。そのような考え方を練習し、連帯していくことが、個々人がいいなと思う生活に近づくために必要なスキルなのではないでしょうか」
photography Park Sara
text Ryoko Kuwahara
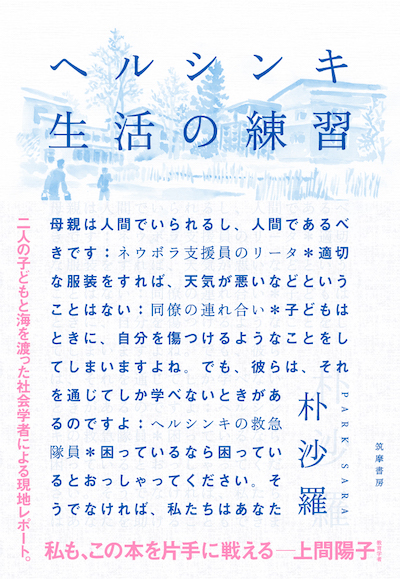
朴沙羅
『ヘルシンキ 生活の練習』
(筑摩書房)
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480815620/
朴沙羅
1984年生まれ。専攻は歴史社会学。立命館大学国際関係学部准教授を経て神戸大学大学院国際文化学研究科講師。単著に『外国人をつくりだす――戦後日本における「密航」と入国管理制度の運用』(ナカニシヤ出版)、編著に『最強の社会調査入門』(ナカニシヤ出版)、訳書にポルテッリ『オーラルヒストリーとは何か』(水声社)。