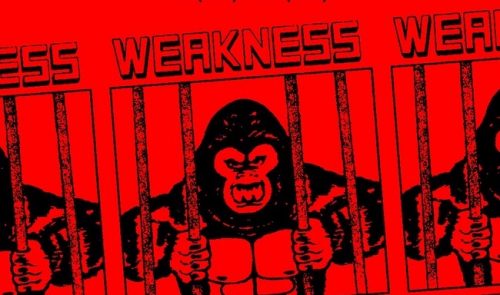温厚なカルガンの頬は一瞬にして紅潮した。きめの細かい白い肌のせいか、色の変化が分かりやすかった。口調は穏やかさを保っているが、目の色は鋭さを隠せずに、その憤りの存在の確かさを伝えていた。
藤島は、カルガンの言葉を真摯に受け止めていることを表そうと、意識的に大きく頷きながら、その目を真っ直ぐ見つめた。
イラン人が持つ日本人に対するリスペクトを、テヘランに滞在中のエピソードをユーモラスに語り終えたあとのことだった。それは、こんな話だった。20代のバックパッカーだった藤島が、パキスタンからトルコへとイランを抜ける旅の道中でのこと。どこかのバスターミナルで、ペルシア語の表記に行き先を定められずに困っている藤島を助けてくれたイラン人の男は、かつて日本に住んだことがあり、その時に日本人にとても世話になったお礼にと、会ったばかりの日本人の若者をその夜の自宅での夕食に招いた。
すでに半年以上も旅をしていた藤島は、すでに旅慣れていて、日本語で話しかけてくる輩が一番危険なことも知っていたが、その時はイラン人のその男を信じてみようという気になった。
そして、その夜の夕食は生涯忘れることの出来ないものとなった。外出時は顔と体を黒い布で覆うことを定められた女性たちだが、家の中では普通に顔を出し、服もそのままであった。当時のイランは禁酒法下であったが、自家製の酒が振る舞われ、さらには音楽が奏でられ、それに合わせて妻や娘が踊ってみせるのであった。
ペルシア人が旅人に対して最大のもてなしをするという風習は、どこかが聞いて知っていたが、それは遠い過去のことだと見做していた藤島は、ただ呆気にとられ驚くばかりであった。街で見かけるイラン人の女性は警戒心を保った鋭い視線の印象が強いのに対し、目の前で歌い踊り、旅人である藤島を心から歓迎する姿は、じつに表情豊かで明るかった。
まるで、アラビアンナイトの中に入り込んだような夜だったよ、と藤島は笑いながらカルガンに語ると、カルガンは驚きの表情で受け止めた。そして、その直後だった。彼の頬が紅潮したのは。
僕たちは、決してイランではそんな扱いは受けない。彼はきっぱりとそう言い切った。カルガンと藤島は英語で会話をしていたので、カルガンはweを使ったのだが、彼の佇まいや雰囲気からすれば、それはオレたちでも私たちでもなく、僕たちだと訳すべきだろう。
藤島は、すぐに察してこう言った。ああ、そうだった、イランとアメリカはいい関係じゃないよね、と。
いいや、即座にカルガンは首を振った。藤島は、自分が何か失言でもしたのかと、勘繰った。彼とブラジリアン柔術の練習をするのは、2回ほど。だが、体を合わせれば、その力や技の使い方から、その人の性格をある程度察することができる。その上で、カルガンは温厚で知的な人物だと仮定していたのだが、真剣な眼差しに含まれる怒りに、藤島はちょっと驚いた。
僕は、モンゴリアンだから、ペルシア人は、今でも敵だと考えている。
藤島はカルガンがモンゴル系だとは知っていた。長身でひょろっとしているが、その風貌は明らかにアジア人であり、初対面の時にそのことを彼に尋ねると、案の定、僕はモンゴル系アメリカ人だという返事だった。
モンゴルとペルシア?藤島の頭の中で、世界史のページがめくられた。モンゴル帝国がアッバース朝のペルシアを征服、ええと、バクダードの戦い、だっけ?
カルガンは、引きつった表情のまま、イラン人は1000年前の戦争を今でも忘れていないんだ。大虐殺が行われたのは確かだけど、それをいまだに忘れずにいるんだよ。
藤島は、おそらくカルガンはちょっとしたトラブルを経験したのだろうと察した。例えば、アメリカ国内で、イラン系の人ともめた、とか。そしてその体験は、彼の中では未だに未消化なままなのだろう。藤島は、そんな想像をしたけれど、それをカルガンに確かめようとは考えなかった。必要ならば、彼から言いだすだろうし、火に油を注ぐことは避けたかった。
藤島にも似たような経験があった。それは中国のウルムチでのことだった。ウイグル系だかトルクメニスタン系だか、当時の藤島にはわからなかったが、明らかに漢民族とは違う民族のエリアを歩いていた時に、通りの向こう側からイスラム帽を頭に乗せた老人に投石されたことがあった。藤島を日本人と認識したからというよりも、漢民族と間違えられたのだろう。インドの北部では、タイのチェンマイで買った麻で編んだ小さめのビーニーを被って歩いいる時に、イスラム系と思われたのか、あからさまな敵意を見せられたこともあった。
日本でのほほんと暮らしていると分からないのだが、世界は歴史上の攻防と憎悪がいまだに上書きされないまま、火種として強く残っている地点がある。もしかしたら、そういう類の遺恨が皆無の地域の方が珍しいのかもしれない。日本でもいまだに会津人は、長州人を許していないと聞く。遺恨とは、もともと消し去り難い種類のものだとしても、今日の遺恨が1000年先の未来の子孫に影響を及ぼすのだと思うと、ちょっとやりきれない気に藤島はなるのだった。
1000年かあ、と藤島は呟き、ため息をついて見せた。どちらかと言えば、共感とも同情とも取れる態度に、カルガンはちょっと落ち着くきっかけを得たようだった。
歴史は歴史として尊重するとして、できるなら私たちは仲良くやっていきたいよね、と藤島が言うと、カルガンは小さく何度も頷いた。
ところで、カルガンってどういう意味なの?と藤島が問うと、芽吹きのような感じだよ、と恥ずかしそうにカルガンは答えた。モンゴルでは女っぽいイメージがあって、男の名前としては・・・・。カルガンの表情が少しだけ曇ったので、その話はそこで終わりになった。藤島は外国人の聞き慣れない名前に対して、その意味を必ずといっていいほど尋ねてしまうのだが、それは時として苦々しい思い出を掘り起こすことにもなる。子供が名前を笑いのネタにするのはどこの国でも同じらしい。
カルガンは25歳くらいに見えるのだが、日本人の妻がいる。あと2年軍属の仕事があるから、それ以後のことは分からないけど、この島が気に入ったから、しばらく帰らずに留まるかもしれない。そんな言葉を締めにして、彼はもう1クラス参加する藤島を残して、道場をあとにした。

その彼とすれ違うようにジェニファーが現れた。2児の母であるネイティヴアメリカンの血を引く彼女は、会員唯一の黒帯ホルダーであり、70キロはありそうな、がっちりとした体型とその佇まいは武術家のそれであった。
白帯の藤島は何度かスパーリングをしているが、技の豊富さは元より、その力の強さ、もしくは力の使い方は、男の藤島をも時には凌ぎ、つまり歯が立たないのであった。だが、藤島がジェニファーに対して抱くリスペクトは、柔術家として強さへというよりも、ネイティヴアメリカンらしい容貌と佇まいに対してであった。
藤島には、遥か遠きものに憧れを強く抱く傾向があった。出自が遠く異なる者に対しての興味は、考古学者が地層を眺める時に抱く高揚と同種のものだった。
今年になって、ネイティブアメリカンの祖先が日本の縄文人という説を否定する証拠が発表されたこともあって、その点への興味が藤島の中で偶然高まっていたこともあり、ジェニファーとの会話に、いつそのことを挟もうかとタイミングを伺っていたのだが、黒い髪の話題になった時に、ジェニファー自身から、ネイティヴアメリカンの出自が語られ、藤島を納得させたのだった。
そう、わたしはネイティヴアメリカンの血を引くの。アンジェリーナ・ジョリーと一緒よ。そう言って、モデル風のポーズを取って笑わせるジェニファーだった。
ジェイムス・ブラウンやジミ・ヘンドリックス、ティナ・ターナーは、黒人とチェロキーのミックスだよね、と藤島が続けると、へえ、そうなの、それは知らなかった。でもわたしは断然アンジェリーナ側よね、と言って大笑いするジェニファーだった。チェロキーと言えば、そうそう、ジョニー・デップも確かそうよ。ああ、大事なのを忘れてた、ビヨンセ!
藤島は、混血への憧れもあった。別々の血が混じり合って、ハイブリッドして、新たな可能性を持つ。それは純血を護るという方向とは異なる可能性であると、藤島は勘を効かせていた。
藤島には、20年前に書きかけたままにしてある小説があった。それはまさに混血をテーマにした小笠原を舞台にした作品だった。
歴史的に見て、小笠原は、日本領となる前までは、太平洋の真ん中に浮かぶ、コスモポリタンな島であった。食肉目的でなく、油を採取するための捕鯨船の停泊地として、ロシア、アメリカ、日本、ヨーロッパなど様々な国の人々が行き交い、住み、大きな争いもなく調和を見せていた島であった。英語やポリネシア語などが交わされ、アロハと挨拶するような場所であった。
藤島は小説の取材目的で、2度小笠原を訪れている。現在は日本の領地なので日本人然とした風貌の人間が島民の多数を占めるのだが、様々な混血を容姿に見せる人々も少なくなく、コスモポリタンであった昔日の小笠原を容易に想像させた。そこでの滞在中に着想した小説では、宗教、民族、などの対立は、すべてハイブリッドが進むことによって解消されるのではないかという考えのもと、ボーダーを消滅さていく混血をテーマにしていた。だが、どうしてもぶつからざるを得ない思想性を消化、昇華させる力が自分には不足していることに気づき、いったん投げてしまった作品であった。
だが、混血へのベクトルはいまだに藤島の底辺にあり、やがて国家という会社のような人工物は消え去り、民族の虚構部分も流れ去り、もっと緩やかな地球が立ち上がるという夢の景色を胸の中に抱いている。
ズニ族って知ってる?藤島がスパーリングの間の休憩時間にジェニファーに尋ねた。
ズニ?うーん、聞いたことがあるような、でも、よく知らないわとジェニファーは息を整えながら答えた。
今から500年前くらいかな、遭難した日本人の一行を乗せた漁船がアメリカ大陸に流れ着き、そこでネイティブアメリカンのズニ族と出会って、混血して、子孫を残したという説があるんだよ。
ホントに?ジェニファーは身を屈めて、首を突き出して、そう言った。目に映った感情は好意的であった。でも、太平洋は、ヒュージよ、大丈夫?うーん、でも有り得ない話ではないわね。可能性はあるわ。ズニ、、、。
スパーリング開始のブザーが鳴って、その話は中断した。藤島とジェニファー、その他の仲間たちは、再びルールのある取っ組み合いの輪の中に入っていった。藤島は、取っ組み合いながら、時々訪れる間(ま)の中で、100年後、1000年後、今の我々の時代はどう記憶されるのか、もしくはされないのかについて思い馳せた。私たちは江戸時代という時代があったことは知っているが、1724年のことなんて誰も知らない。アッバース朝ペルシアがあったことは、学校の授業をさぼらなければ聞いたことがあるという風になるが、1210年にバグダードに新規開店したケバブ屋のことなんて誰も知らない。その店の主人の妻が、街一番の美人だったなんて誰も知らない。それと同様に、2021年とか2022年の出来事なんて、塵にもならないのだろう。
それでも、ルールのある取っ組み合いをして、ああ楽しかったとか、充実した時間だったとか言って、満足し、シャワーを浴びて、駐車場の車に乗り込んでエンジンを掛ける。
そういう日々の1コマを肩の力を抜いて楽しむこと。いちいち成果やオチを求めないこと。いつもハイブリッディングを受け入れて、何かを溜め込もうとしないこと。
藤島は、あの小笠原を舞台にした若き小説をいつか仕上げたいと願う。うまく書けて、ヒットして、映画化になって、それもヒットして、ハリウッドで撮り直されたりしたら、ジョニー・デップとビヨンセにオファーしたい。で、サントラには、ジミヘンとかJBとかが入る。そしてエキストラとかちょい役に、 カルガンとジェニファーと自分も押し込む。藤島は、その夢を思い描きながら、マットの上で相手の攻撃を凌いでいた。
#1 裏の森
#2 漱石の怒り
#3 娘との約束
#4 裸を撮られる時に、百合は
#5 モルディブの泡
#6 WALKER
#7 あの日のジャブ
#8 夏休みよ永遠に
#9 ノーリプライ
#10 19, 17
#11 S池の恋人
#12 歩け歩けおじさん
#13 セルフビルド
#14 瀬戸の時間
#15 コロナウイルスと祈り
#16 コロナウイルスと祈り2
#17 ブロメリア
#18 サガリバナ
#19 武蔵関から上石神井へ
#20 岩波文庫と彼女
#21 大輔のホットドッグ
#22 北で手を振る人たち
#23 マスク越しの恋
#24 南極の石 日本の空
#25 縄文の初恋
#26 志織のキャップ
#27 岸を旅する人
#28 うなぎと蕎麦
#29 その部分の皮膚
#30 ZEN-は黒いのか
#31 ブラジリアン柔術
#32 貴様も猫である
#33 君の終わりのはじまり
#34 love is not tourism
藤代冥砂
1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある