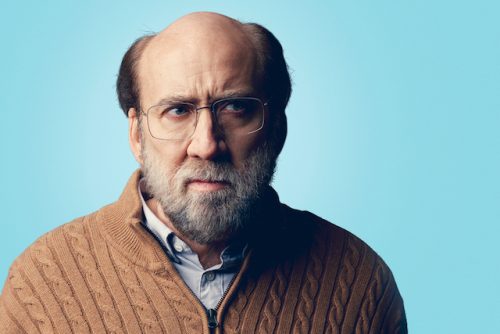近年、結末をはっきりとは描くことなく、オーディエンスがその物語を胸に抱き続けることで完成する映像作品が多く輩出されている。それは共通となるゴールが描かれる時代ではなく、多様な価値観を持つ社会となっていることを象徴するひとつの事象であり、また同時に、結末を与えられないことで各人が導き出した答えやアイデアが、現実社会でそれぞれがアクションを起こす時に呼び水となる機能を果たしているとも言える。結末のない映画が我々にもたらしてきたものはなにか。現実に拡張する、結末のない映画についての特集。編集部による3編のレビューをお届けする。(→ in English)
『時計じかけのオレンジ』
スタンリー・キューブリック監督作品『時計じかけのオレンジ』は単なる美しい映画ではなく、象徴がちりばめられた傑作だ。多くの人がこの映画を何度も繰り返し観ているが、観れば観るほどにその意味の深さに気づき感嘆する。
『時計じかけのオレンジ』は、暴力的な10代の少年であるアレックスの物語だ。彼の行動が若い女性の死に繋がり、更生のために精神医学リハビリセンターに入れられる。そこで彼は邪悪な考えを取り除かれるだけでなく、自分自身を守ることさえもできない状態に陥るーー。
この映画の素晴らしさを形作っているものは、毎シーンで見せられる全く新しいレイアウト。多くの家具がキュープリックとプロダクションデザイナーのBannyによってデザインされていることを知ると、より楽しめるはずだ。
最も象徴的なシーンの1つには、コロバ・ミルク・バーが挙げられるだろう。ミルクルームの彫刻は、この撮影のために特別に作られた。女性を象られた家具は、女性というものを人間としてではなく物体として見なす究極のオブジェクティフィケーションだ。女性のセクシュアライゼーションは、物語と室内装飾を通して、本作の中でごく普通に行われている。もちろんこれは決して受け入れられるものではないが、女性に対する男性の視線や力の用い方に男性性がどのように関係し、測られているかという洞察ができる。
映画は性差別、社会的地位、労働者階級の家族の苦悩を果敢に描いており、観るものが学ぶことができるようになっている。それによってエンタテイメントの不朽の名作となっているのだ。この1971年の映画が現代のイギリスをどのように捉えているかというのもまた興味深いポイントだ。芸術を収集する文化、階級による格差、そこに馴染めない人々を嫌うようなところはまだ依然として存在する。
『時計じかけのオレンジ』はもし性格の一部を適合するように矯正されるとしたら、アイデンティティの非常に重要なパーツを失うことを提示し、個性、創造性の重要性を物語る。この映画は、あなたが誰であるかというアイデンティティを手放さないようにするためのキューブリックからのメッセージなのだ。『時計じかけのオレンジ』の後には、『2001年宇宙の旅』を観るのもおすすめ。
キャスト;マルコム・マクダウェル、パトリック・マギー、マイケル・ベイツ他
監督:タンリー・キューブリック
1971年制作 / 136分 / アメリカ
原題:A Clockwork Orange
配給:ワーナー・ブラザース
『Survive Style 5+』
広告ディレクターの関口現が監督を務めた『Survive Style 5+』は5つ(+1)の独立したエピソードがそれぞれに絡み合い、ストーリーを作っていく、その型破りなミックスが魅力だ。とにかくシュールで、抽象的すぎるという人もいるかもしれない。
監督はその商業的専門知識を映画全体にうまく統合した。フィルムは2時間のコマーシャルのように機能し、オーディエンスの注意を引きつけ、心を弾ませ、思い出させる。
主要なテーマは機能性で、本作では機能性とプロダクションの概念を模倣しようとする。広告業界とエンタテインメント業界はどちらも、資本主義の概念に大きく依存しており、間接的にこの関係に挑戦しようとしている。ヨーコがクライアントに彼女のコマーシャルを見せ、クライアントが気にくわない時に、彼女は言う。
「CMは面白くなくちゃダメないんです。誰も観てくれませんよ、会社の一方的なマスターベーションなんて」
この映画は、資本主義イデオロギーの存在を主張するものでも否定するものでもない。新しい意見の提案だ。
セレブリティカルチャーは、もう1つの繰り返されるテーマ。映画の殺し屋は絶えず「おまえの役割は何だ?」と尋ねる。
誰もが答えるのが難しいと感じているようだ。他より多くの役割を持つ者はおらず、誰もが同じ人生とそれぞれの能力を持っている。しかし、なぜセレブリティはより価値があるように思われるのか?
この映画には、日本のコマーシャルやエンタテインメント業界に関連する独特の特徴がある。映画は、5つの相互に関連するストーリーを切り替えるが、この切り替えはそれぞれの物語を好きになるように仕向けられた楽しい遊びに思える。
長いストーリーを観るのに飽きたなら、これは素晴らしいゲームチェンジャーかもしれない。
シュールな映画が好きなら、『ナイスの森〜The First Contact〜』も是非。
キャスト:浅野忠信、橋本麗香、阿部 寛、小泉今日子、岸部一徳、麻生祐未、J・WEST、津田寛治、森下能幸、荒川良々、ヴィニー・ジョーンズ、千葉真一 他
監督:関口 現
2004年制作 / 120分 / 日本
配給:東宝
『淵に立つ』
現実のさらにその底にある現実に触れた『淵に立つ』。この映画には美しく紛れもない何かがある。
登場人物、環境、会話は、一般的な日本の家庭を描写するが、そこに寄生虫ともいうべき者が現れる。
物語は、古い知人の八坂が利雄の家族を訪ねて暮らすところから始まる。
姿勢が良く、白いシャツを着ており、丁寧で寡黙。
八坂は犯罪者とは無縁のように描かれているが、彼の存在が家族の崩壊につながっていく。静かな場面では悲鳴が大きく聞こえるのと同様に、平凡であるように見せることで、八坂の存在を増幅する仕掛け。浅野忠信は八坂を特徴づける素晴らしい演技を見せる。
八坂の沈黙から優しさの代わりに、危険を感じさせる。彼の冷静な行動は心の底の何かが欠けているようだ。
この映画は、日本で語られることのない苦しみを描いている。悲劇は起こるが、私たちはそれが起こらなかったかのように人生を続ける。誰もそんな悲劇を知る必要がないかのように。
『淵に立つ』は復讐の物語であり、それぞれの登場人物の苦痛が観る者の心を砕く。
暴力を許し、忘れることは可能か?
我々は最後まで、八坂のことをよくわからないままだ。彼には伝えるべき話があるのか、それとも秘密にしておかなければならないのか。
この映画は毎日のように起きている突然の暴力に触発されており、「波長」を伝えるプロットによって展開される。時折波長にはブレーキがかかり、感情の断片を見ることがある、というように。
本作はまた犯罪を別の見方に導く。監督の深田晃司は、犯罪を自然なプロセスの一部として説明している。犯罪者を含め、誰にも落ち度はなかったかのように。
エンディングはとても静かだが、それでいて強力な感情を呼び起こす。その曖昧な結末に飲み込まれていくようだ。
本作が気に入ったら、浅野忠信も出演している『“>アカルイミライ』もチェックして観てほしい。
キャスト:浅野忠信、筒井真理子、古舘寛治 他
監督:深田晃司
2016年製作/119分/G/日本・フランス合作
配給:エレファントハウス
text Maya Lee