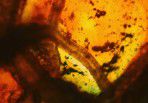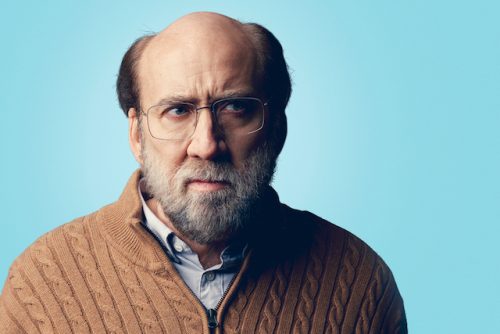―—フロントマンとしての意識もどんどん向上してるんじゃないですか?
YONCE「いや、俺は高校2年のときからずっとバンドをやってきましたけど、当時からロックスター志向があったので。『テッペンまで行くしかねえ』って感じでバンドをやっていて、そこに関してはずっと一貫してますね。変化があったとしたら、自分の歌やノリをしっかり提示できるようになったことくらいですかね。いまだにメディアではSuchmosはブラックミュージックのバンドとかシティポップのバンドって紹介されてるけど、俺のスタンスやパフォーマンスはデヴィッド・ボウイとかカート・コバーンのつもりでやってるんでっていう」
——ロックスターのつもりで。
YONCE「そう。という感じなので、俺自身は自分の存在をSuchmosの音楽性に寄せているつもりはまったくなくて」
——なるほど。独立した存在感のあるフロントマンでいたいと。
YONCE「そうですね。メンバーがタイトでクールなヴァイブスのある演奏で俺のステージを作ってるくれてるみたいな。彼らもそういうスタンスで演奏してくれているので。俺は演奏の上でいい感じに泳ぐみたいな感じです」
——日本の音楽シーンに長らくあったスター不在の季節を経て、いまはあらゆるジャンルでスターが求められていると思うんですよね。
YONCE「『スターがいないんだったら、俺がなっちゃおうかな!?』みたいなスケベ心をもったやつが俺らの世代には多いのかもしれないですね(笑)」
——高岩遼(SANABAGUN./THE THROTTLE/SWINGERZ)だってそうだろうし。
YONCE「ホントにそうだと思います」
——やっぱりお客さんにもスターに対価を払ったほうが強い満足感を得られると思うんですよね。カネを落とす気持ちよさを覚えさせるのもスターに必要な力だと思う。
YONCE「なるほど。そうかもしれないですね。『俺らは所詮こんなもんですから』みたいなスタンスで音楽をやってる人が多い気がする。これは音楽に限らない話かもしれないですけど。それはもったいないなと自分に自信があるんだったらそう言えばいいし。Suchmosのメンバーみんなこのバンドを結成するまでにいろんなカタチで音楽と関わってきて、根拠のない自信を持ってきたやつらで。そんなやつらが6人集まってみたら根拠のなかった自信が『あ、やっぱりマジで間違いないなかったな!』という確信に変わって、それをいま証明できてるから。すごく痛快ですね」